| ★今月公開の気になる作品: ★★★ラスト・キング・オブ・スコットランド ★★★デジャヴ ★★ハッピー フィート ★★アルゼンチンババア ★★★ブラックブック ★★★★クロッシング・ザ・ブリッジ サウンド・オブ・イスタンブール ★★★ひいろ |
| サンシャイン2057 しゃべれども しゃべれども 眉山 あるスキャンダルの覚え書き 大帝の剣 ラブソングができるまで プレステージ ボルベール〈帰郷〉 オール・ザ・キングスメン 300 スリーハンドレッド アポカリプト ハリウッドランド ラストラブ 舞妓 Haaaan!!! 明日、君がいない |
2007-03-22
●舞妓 Haaaan!!! (Maikohaaaan!!!/2007/Mizuta Nobuo)(水田伸生)

◆京都の茶屋で舞妓遊びをすることを高校生のころから夢み、その実現に向ってモーレツ行動を展開する男を怪優・阿部サダヲが演じる。ここで描かれている京都の茶屋や舞妓は、外国人むけの観光ガイドに出てくる「京都」や「舞妓」の域を出ないが、あまり気にならない。展開はスピーディであり、宮藤官九郎の脚本家としての才能が余すところなく出ている。
◆宮藤官九郎(脚本)らしいというか、今様というのか、阿部サダヲが演じる鬼塚公彦はウェブページを持っており、修学旅行で京都に行くと、舞妓を追いかけ、写真を撮り、ウェブページに載せる。祇園の茶屋生まれで、いまはプロ野球選手として茶屋の常連である内藤貴一郎(堤真一)も、インターネットの検索で鬼塚のサイトを発見し、いちゃもんをつけるほど「オタク」の側面がある。つまり、茶屋遊びは、本来ネットのようなヴァーチャルな世界の極北にあるのだが、この映画に登場する舞妓狂いたちは、むしろネット感覚の持ち主なのである。
◆これは、単純には、脚本を書いた宮藤官九郎がそうであるにすぎないということなのかもしれないが、トータルには(つまり出来上がった映画の構造を所与として判断する場合には)そこ(つまり生身の世界とヴァーチャルな世界との混交・混乱)がこの映画の面白いところであり、新しいところなのだ。
◆プレスによると、京都の花街を題材にした脚本を宮藤官九郎に持ちかけたのは、監督の水田伸生だというが、そのとき、宮藤に水田が「シナリオハンディング」を提案すると、「僕はシナハンしないで書くタイプなんです」とあっさり断り、『るるぶ』を参考にして書いてしまったという。水田は京都に「シナハン」に行ったというが、この映画の基本は、ヴァーチャルな京都・お茶屋・舞妓なのである。ちなみに、宮藤官九郎は、宮城県出身で、京都で育ったわけではなく、彼にとっては、京都はヴァーチャルな世界としてしかリアリティをもたないはずである。
◆映画のなかでも、このヴァーチャル/リアルの世界は、入れ子状になっている。舞妓とお茶屋の世界は、まず鬼塚の願望とイメージの世界にある。彼の彼女・大沢富士子(柴咲コウ)も、三重県出身ながら、京都人と舞妓になることにあこがれている。その2人が、京都という「リアル」な場所に移動し、カメラも京都に移る。鬼塚は、京都本社に転勤になったためであり、富士子は、鬼塚に捨てられたあと、単身京都の置屋に舞妓見習として住み込み、駒富士という舞妓になる。しかし、この京都で、鬼塚はヴァーチャルな転身をくりかえす。お茶屋で舞妓遊びをするにはそれなりの「信用」をつけろと社長(伊東四朗)に言われ、粉骨砕身、ヒット商品を生み出し、晴れてお座敷入り。ところが、そこで、天敵の内藤貴一郎(堤真一)の存在を知り、こいつを見返すためにピッチャーになる。すると、内藤の方は、その上を行って最後は京都市長になる。鬼塚は内藤に張り合ってそのつど職を替え、内藤のライバルになる。このシュールなエスカレイションが笑わせる。
◆京都の店をあつかう映画や物語のご多分に漏れず、この映画でも、「一見さんお断り」がテーマになっている。内藤が市長に就任すると、京都の置屋生まれという屈折した過去の反動で、「金があれば何してもかまへんやないか」とばかり、「一見さんお断り」廃止令を作ろうとする。これに反対するのが、非京都人という設定の鬼塚であるところが面白い。大体、(この映画とは関係ない話だが)「土地」とか「郷土」とか「伝統」にこだわるのは、土地の者よりもよそ者なのである。
◆ただし、いま京都では、「一見さんお断り」という「風習」はくずれつつある。茶屋遊びに金を使う人の意識が変わってきたことや茶屋も料亭もそんな贅沢なことを言ってはいられないからだ、とはよく言われることだが、ここには、情報環境の変化もあるだろう。かつて情報誌というものがなかった時代には、茶屋にかぎらず、レストランも料理屋も、口コミが主要な情報だった。その店と懇意な人間が基礎にあり、その紹介の連鎖のなかで常連と新しい客が生まれていた。これが、情報誌やマスコミ取材にわが身を公開することによって、世間との関係が変わって来た。店の側からすると、想像もしない価値観や感覚の人が訪れるようになる。そこで、「一見さんお断り」が登場する。つまり、「一見さんお断り」は、京都に昔からあった「風習」ではなく、むしろ、情報誌の登場とともに自己防衛的に(本来の意味を変えて)露出した「制度」なのである。
◆しかし、それからまた時代が変わった。情報誌がものめずらしかった60~70年代とはちがい、いまは情報の質が問われる時代になった。ここでは、情報を隠すということが極度に難しい。だから、いま、一般に知られている茶屋や料理屋で「一見さんお断り」を押し通しているところは少ない。予約は取りにくいかもしれないが、一応、機会均等のたてまえをまもろうとしている。しかし、「一見さんお断り」はなくなったわけではなく、『るるぶ』なんぞには絶対に名前が出てなくて、その店がまえも、何の店かわからないようなところが、京都にはある。そんなところへいきなり飛び込んだら、全く相手にされないのはあたりまえである。そもそも、一般に知られている店でも予約はあたりまえだが、そういう謎めいた店の場合は、そもそも「予約」の方法がわからないはずだ。
◆京都をあつかった映画で、京都らしいという記憶が残っているのは、ここ数年のなかでは、『二人日和』だ。『SAYURI』も、 『ICHIGENSAN いちげんさん』も、あまり京都とは関係がなかった。
◆この映画には、植木等がイキな着物姿の軽い足取りで歩いていく姿が映る。西陣の会長という設定で、京都の茶屋街では別格的存在という設定。植木等と京都というのは合わない感じがするが、奇しくも植木の最後の映画出演となったこのシーンは、植木がそのままあの世に歩いていくように見えなくもなかった。
(東宝試写室/東宝)
2007-03-20
●ラストラブ (Last Love/2007/Fujita Maiji)(藤田明二)

◆名代のカッコマン田村正和がニューヨークを舞台にテナーサックス奏者を演じるとくれば、どんな映画になるか予想がつくが、そのパターンを見てみたいと思って東銀座は万年橋のたもとの試写室におもむいた。すでに8日に丸の内ピカデリー2で「マスコミ完成披露試写会」があったが、これは敬遠した。出演者挨拶や毎度の写真撮影につきあわされるのが時間の浪費に思えたからだ。さて、その完成披露で口コミが広まったのか、今日の会場はやけにがらんとしていた。
◆ジャッキー・チェンが身体を張るのをやめたら観客が失望するように、田村がカッコつけるのをやめたら、あとには何も残らない。だから、カッコをつけるのはどんどんやったらいい。しかし、この映画で田村は、声が極度にかすれ、せりふを聞くのがつらかった。映画が終わって、「こっちが咳払いしたくなっちゃうよね」と言っている人がいたが、田村は声帯切除でもしたのだろうか? もしそうなら気の毒だが、それを隠してこの映画の登場人物のようなキャラクターを演じるのは無理である。マーロン・ブランドが演じた『ゴッドファーザー』のコルレオーネのように、昔喉を切られて、声が出にくくなったという設定ならば、わかるが、この映画での、少なくとも声が出ないことを納得させる設定は何もない。
◆映画が偶然を利用するのは一つの型としては許される。男と女がばったり街で遭い、そこからラブロマンスが始まる。そんなことが普通にあるかどうかは別にして、これがこの映画なんだと居直ることはできる。普通の生活のなかでも、偶然の出会いというものは、けっこうある。しかし、映画のなかで3回以上もそれが続くと、映画として安易だとう印象をあたえるのを避けることができない。それは、「現実」にそんなことがないからではない。映画の形式として、もっと凝ったことが考えられるのに、それを回避し、省略・節約しているという印象をあたえるからだ。
◆ニューヨークでテナーサックスの奏者として、有名ジャズクラブ、「バードランド」で仕事をするほど評価されていた阿川明(田村正和)が、妻(高島礼子)を突然失い、彼女の病に気づかなかったことで自分を責めて、幼い娘・佐和(森迫永依)を連れて日本に帰国する。このあたりは、冒頭でちらりと暗示し、詳細はあとからフラッシュバックで説明される。映画はそれから5年たったところからはじまる。親友・朝倉大吾(片岡鶴太郎)が経営する観光会社に勤め、横浜の根岸で娘と二人暮らしをしているある朝、ゴミを出そうとして、清掃車の市職員ともめる。生ごみの日なのに、田村が燃えないゴミを出そうとしたのだ。その職員を演じるのが、伊東美咲で、彼女は清掃課のキャリア組だが、その日はたまたま現場をチェックするために実務の作業に加わったという設定。これが最初の偶然。
◆見るからにひ弱な女性が、ゴミ回収のきつい労働に加わっても足手纏いでしかないと思うが、とりあえずは黙認しよう。が、これが(詳細はさしひかえるが)ニューヨークで再会し、しかも同じホテルに泊まっており、彼女が、婚約者との電話で自暴自棄になり(これもよくわからない)ホテルの窓から転落しそうになるのを、タイミングよく田村が助ける。大体、ニューヨークのある程度のホテル(映画に映ったかぎりでは安ホテルではない)で、ドアーを閉めたとき自動ロックしないようなところは少ない。しかし、田村が(それほど面識があるわけでもないのに)彼女の部屋を探しあて、ドアを押すと開いてしまうのだ。これは、偶然の利用にしては、出来すぎである。
◆田村がニューヨークを去った動機というのもあいまいすぎる。ドラマのために安易な設定にしたとしか思えない。いかに妻を愛していたとしても、ニューヨークのジャズシーンで切瑳琢磨していたとしたら、プロフェッショナリズムというものがあるだろうと思うのだ。映画の初めの方で、田村がバードランドでテナーを吹き終わると、その日が彼の誕生日だというので、客席から高島礼子が花束を持ってステージに近づく。田村のテナー演奏が、ただ形を整えただけのものだったので、このシーンは、金を払ってプロの演奏を聴きに行く場所がいきなりホームパーティの会場にすりかわってしまったのではないかという印象を受けた。
◆田村がニューヨークへ行くとき、どのクラスの便に乗るのかと思って注意していたら、「エコノミー」クラスだった。観光会社の幹部なら、「ビジネス」に乗るのが普通だろうが、それだと、「たまたま」通路をへだてた席に座ることになる伊東美咲に再会する「人工的」偶然のシーンが撮れなくなる。というのも、伊東は、キャリア組とはいえ、市の役人が出張で「ビジネス」に乗っていたりするととかくうるさいご時世で、彼女が「エコノミー」に乗るのが「自然」で、そうすると、田村の方をそれに合わせるしかないからだ。しかし、名代のカッコマンが飛行機に乗り、ヒロインと再会までするのだから、ここは「非現実的」に「ビジネス」クラスか「ファースト」クラスにしてほしかった。ちなみに、ニューヨークでジャズプレイヤーとして評価されているとしても、ミュージッシャンとしてニューヨークで生き抜くのは、そう楽だはなく、「ビジネス」クラスなどを乗り回してはいられないのが現実のようだ。
◆田村正和は、6回出て来る演奏シーンのために、稲垣次郎の指導を受けて練習したというが、彼が映画で見せるのは、全体の演奏のほんのさわりの部分だけである。ニューヨークから帰った田村が、1 回だけ山下埠頭でテナーを吹くシーンがあるが、彼が練習するシーンは一度も出てこない。プロセスがすっとばされている。同じように全然演奏できない状態から実演までこぎ着けたヒュー・グラントの『ラブソングができるまで』では、もっと「遊び」があり、実演でも不自然な印象はおぼえなかった。田村の場合は、この程度なら、吹き替えでよかったのではないか? 音はすり替えて、カッコだけ演った方がお似合いだった。
◆この映画のわずかの救いは、うまずぎるほどの森迫永依の演技。あるタイプの子供としての存在感があるので、彼女が登場すると、そのシーンが彼女のキャラクターで染まってしまうが、なかなかの才能。もともと不安気な目を持つ伊東美咲も、老年男を愛してしまう女性の屈折をけっこう直感的にうまく表現していた。
◆田村が造形する得意なキャラクターは、「生活感覚」の希薄でちょっとニヒルな男ということになるが、この映画では、田村は3度以上も涙を見せる。妻の死で泣き、途中でわかる自分の病の行く末を思って泣く。声がかすれるが、ぶっきら棒な田村節は、フィットするところではいい効果を発揮する。
◆この映画で田村が見せる「迫真の演技」は、鶴太郎とバアで飲んでいるとき、貧血を起こして倒れるところと、伊東美咲とレストランでいっしょにいる(彼は水割りばかり飲んでいる)とき、急に吐き気をもよおすシーン。無理しながら「ちょっとごめん」とか言いながら席を立ち、トイレで吐く。これは、なかなか真に迫っていた。それでふと(不謹慎ながら)思ったが、「14年ぶりにスクリーンに復帰」した田村正和が、実際にこの映画の主人公のような病を負っており(それで声が出ない?)、その進行を予想してこの映画を作り、その公開に合わせて・・・・としたら・・・。それは、カッコマンの冥利につきるのではないか?
(松竹試写室/松竹)
2007-03-19
●ハリウッドランド (Hollywoodland/2006/Allen Coulter)(アレン・コールター)

◆地下鉄乃木坂駅を出て、国立新美術館のまえを通って六本木トンネルの方に進むと、歩道で身をかわさなければならないほどの人に出会う。新美術館がオープンして、急に人の流れが変わったのだ。わたしは、美術館には(とりわけ大きいものには)距離を置いている人間なので、当面、この美術館は存在しないも同然であり、それまで静かだったこの通りがそうでなくなってしまったことを残念に思う。
◆この映画は、1951年に「スーパーマン」としてテレビ("Superman and the Mole-Men")に登場し、そのシリーズ放映によって次第にポップスターになっていくが、1959年に「謎の」死をとげるジョージ・リーブス(ベン・アフレック)の物語。架空の探偵ルイス・シモ(エイドリアン・ブロディ)が、警察が「自殺」と発表したその死を、リーブスの母親(ロイス・スミス)の依頼を受けて調査するという形態をとる。
◆が、『戦場のピアニスト』の「逃げる男」のイメージがあるエイドリアン・ブロディが演じる探偵は、どこか頼りなく、腕っ節の強さを見せるシーンはない。むしろそこにこに映画のねらいがある。シモは、別れた妻と暮らす幼い息子のことを気にする普通の父親である。妻の浮気を妄想する一人の依頼者しかいないシモにとって、ジョージ・リーブスの調査は、願ってもない依頼だったが、他方、自分の息子が、銃弾をはね飛ばす「スーパーマン」がピストルの銃弾で死んだことでショックを受けているのを見るにつけ、ジョージ・リーブスの死の謎の調査にのめり込んで行く。息子は、スーパマンは俳優が演じていたんだといくらシモが説明しても、納得しない。
◆調べていくうちに浮かび上がるのは、ジョージと(ハリウッドでは公然の秘密だった)トニー・マニックス(ダイアン・レイン)との恋愛関係だったが、それがただの「恋愛」ではなかったことが示唆されて行く。トニーは、MGMのゼネラルマネージャーのエディ・マニックス(ボブ・ホスキンス)の妻で、ジョージより8歳上だった。映画では、パーティで二人が知り合い、以後、仕事面でもトニーがジョージのめんどうを見ていくところが描かれる。夫のエディには日本人の若い愛人ヨシダがおり、夫婦で勝手なことをやっているように見えるが、むしろ妻のやりたいようにさせるのが彼流の愛情であった。妻の頼みでジョージに仕事を世話するが、彼が新しい恋人レオノア・レモン(ロビン・タニー)を作り、トニーを裏切るのを黙認できない。ここから、ジョージの死は、エディの「仕打ち」ではなかったかという世間の憶測が生まれた。現在でも「薮の中」にあるジョージ・リーブスの死のいくつかの解釈を呈示するのがこの映画の一つの流れである。
◆しかし、映画は、そういういくつかの「推測」を呈示しながら、最終的にドラマチックな結論を出すよりも、ジョージ・リーブスの過去をたどるなかで、一人の俳優の苦悩を浮き彫りにする。テレビが急速に普及しはじめるメディアの大転換期に、映画では売れなかったジョージが直面した屈折。テレビで爆発的な人気をかちえたが、その人気や収入にもかかわらず、映画俳優ではなく所詮はテレビ俳優にすぎないという意識を抜け出さないジョージ。彼は、スーパーマンとしての名声が映画の仕事を疎外するという屈折に悩んでてもいた。
◆スーパーマンとして著名になったジョージは、フレッド・ジンネマンの映画『地上(ここ)より永遠に』(From Here to Eternity/1953) に出演するチャンスを得るが、すでにスーパーマンのイメージが定着していたジョージが登場する映画のシーンに観客がスーパーマンのイメージを見てしまう。映画では、試写のときにそういうことが起こり、ジンネマン側の人間が、その場面をカットするように指示するシーンが見える。実際にはカットはされなかったが、不思議なことに、クレジットに「ジョージ・リーブス」の名はない。テレビがまだ映画よりもずっと下の媒体とみなされていた時代の話である。
◆ジョージ・リーブスの両親は複雑な結婚・離婚・再婚暦があり、ジョージの父親への記憶は希薄だったたらしい。だから家庭は母親との関係が強く、月並みな言い方をすれば、ジョージは、「父親不在」の家庭生活を経験していた。その意味で、「スーパーマン」というのは、「父親」ではないある種の「支柱」であったという点で、ジョージ自身が幼ければ、その心のささえになったかもしれないような存在だった。
◆ところで、これまた月並みな「社会統計」的なアプローチを試みてみると、テレビの「スーパーマン」シリーズが視聴率を高める1950年代は、仕事に追われて帰宅が遅くなるとか、育児が妻の仕事とみなされる率が高いなど、子供が家庭で「父親の不在」を感じる傾向が高まった時代だった。つまり、「スーパーマン」が、「父親」の不在の部分を埋めた部分が少なからずあったということだ。この映画では、その部分を、今様に粉飾しているように思う。その方が素直に受け入れられるからだ。すなわち、シモは、仕事が忙しいために息子との時間を持てないのではなく、離婚してしまったのでそうなのだという今様の設定にしてあるのである。
◆一般にアメリカで離婚率が急激に高まるのは1970年代後半以降で、映画もその動向にあわせて「離婚」をテーマにしたり、「離婚」が重要なエピソードになっている作品を作った。それによって、人々は、「離婚」や、そこから帰結する「ワンペアレント・ファミリー」や「再婚」、「ステップ・ファーザー」などの現象を、「あたりまえ」のものとみなす社会的訓練を受けた。この段階になると、家を出て行ってしまった父親を、「お父さんはお仕事で忙しいから」とか日本で言う「単身赴任」とかの理由で子供に父親の不在を納得させることはできないから、日夜働いている「スーパーマン」の存在も、以前と同じ機能を果たさなくなるわけだ。
(ブエナビスタ試写室/ブエナビスタインターナショナル)
2007-03-16
●アポカリプト (Apocalypto/2006/Mel Gibson)(メル・ギブソン)

◆メル・ギブソンは、西欧文明を大きなスケールで見直そうとしているようだ。しかし、歴史への新しい洞察を呈示することよりも、ある種「露悪的」とも言えるドギツイ映像で歴史を見せ物にしているようなところがある。映画は、どのみち見せ物だと考えているかのように。
◆冒頭に、『The Story of Civilization』のウィル・デュラントの言葉が引用される。「偉大な文明は、外部からではなく、内部から破壊され、征服されたのだ」(A great civilization is not conquered from without until it has destroyed itself from within.)。ここには、マヤ文明がそうだったということと同時に、現在のアメリカが主導する「世界秩序」(ブッシュ・ドクトリン)へのささやかな揶揄がある。
◆最期のシーン(スペインの船が浜に見える)から察するに、時代は、16世紀。マヤ帝国は、内紛にあけくれ、抗争と崩壊をくりかえしている。冒頭から、都市のマヤ民族が森に住むマヤ民族を襲い、奴隷として狩猟する悲惨でおどろおどろしいシーン続くが、ギブソンは、こうした侵略行為が、単なる残忍で狂った指導者や愚かな連中によってなされるのではなく、ちゃんとした下部構造的な必然性から生まれることをおさえている。
◆マヤ文明の崩壊には、エネルギー問題があった。都市建設に必要な石灰を供給するために労働力を必要とし、そのために奴隷が生まれた。奴隷を動員して石を切り出し、石灰を作らせた。また、石灰の生産のために森の樹木を伐採したことによって、自然災害を引き起こすことになった。
◆エキストラには、マヤの血を引く素人の人々を多数使っている。みな、しなやかな演技を見せる。とりわけ印象に残るのは、支配的な部族が森に住む人々を奴隷として狩り出し、数珠つなぎにして遠路を移動させるシーンで、疫病のために崩壊した村を通る。そのとき、病にかかった一人の少女が、支配的な部族の者に呪いの言葉を吐く。そのときの目が尋常ではなく、半端な演技をこえている。なぜこんな演技ができるのか、不思議だ。
◆アナログのシーンと同じぐらいの費用をかけたというCG処理のシーンも見ものである。ジャガー(本当は、ジャガーは人間を襲わないらしいが)が森のなかで襲撃して来るシーン、マヤ文明の遺跡に見られる階段状の建物で行なわれる、雨乞いのための生贄のシーン(はたしてこの建物は、実際にこのようなことのために使われたのだろうか?)が見せるさまざまな知恵、この映画のわずかな希望の象徴となる森の住人のヒーロー(ルディ・ヤングブラッド――ただし、彼は、マヤではなく、ネイティブアメリカンとのこと)、その妻が、襲撃を逃れた洞窟の、強烈なスコールで浸水する狭い穴のなかで赤子を産み落とすシーン、みなメル・ギブソン流にどぎついが、印象に残る。
◆映画が描く特定の時代は、いくら考証を厳しくしても、所詮は「現代」のヴァリエイションか、「現代」からの想像や願望の所産にすぎない。だから、気にする必要はないのだが、森の住人たちが、罠で仕留めた「バク」を生で食らうのは、果たして史実に忠実なのだろうか? ひょっとして、森に住む原住民だということを強調するためにそうしたのではないか? たしか、マヤは、農耕民族で、肉食であるよりも菜食であったと記憶する。
◆生贄のシーンは、それが史実であったことを裏付けるかのように、壁画(→
 )がちらりと映される。が、そのなかで描かれている血のしたたる生首は、現存するマヤの壁画には出てこないらしい。
)がちらりと映される。が、そのなかで描かれている血のしたたる生首は、現存するマヤの壁画には出てこないらしい。◆一番の違いは、森の住人たちの家族形態であり、彼や彼女らが、ほとんど現代のアメリカ人のような個人志向である点だろう。
(スペースFS汐留/東宝東和)
2007-03-14
●オール・ザ・キングスメン (All the King's Men/2006/Steven Zaillian)(スティーヴェン・ゼイリアン)

◆ 大分まえから試写をやっていたが、後回しにしてきた。アメリカでの評判がかんばしくなかったからでもあるが、LDでロバート・ロッセンの1949年の元ヴァージョンを見ていたので、必ず見たいとは思っていた。明らかに、いまリメイクを作る以上、ブッシュ政権の批判の含みがあるはずだと思ったからだ。実際、主演のショーン・ペンは、そのような発言をしている。が、見た印象は、かなりネガティヴなものにならざるをえなかった。
◆1949年版は、大恐慌後のアメリカで実在した人物をロバート・ペン・ウォーレンが書き、ピュリッツァー賞を受賞した小説にもとづいている。映画は、アカデミー賞の作品賞、主演男優賞(ブロドリック・クロフォード)、助演女優賞(マーセデス・マッケンブリッジ)などを受賞している。
◆元版を見たときも感じたのだが、このヴァージョンではジュード・ロウが演じている新聞記者ジャックの仕事ぶりに切迫感がない。遊軍記者の感じなのだ。しかし、映画のなかでは、その記事が、もう一人の主役ウィリー(ショーン・ペン)を世に送り出すということになっている。まあ、上流階級のおぼちゃんであり、記事を書く仕事は余業なのかもしれないが、この人物がナレーションをやり、映画の中心的な目になっている。◆いずれにせよ、ジャックは、ウィリーが、出納官として、地元のボスの圧力に屈せず、税金の不正を正す姿勢に惹かれ、彼のことを新聞に書き続けるという設定。このあたりは、旧作の方が説得力がある。新作では、ジュード・ロウの甘い雰囲気もあり、若干同性愛的な匂いもする。が、基本は旧作の流れが踏襲されているので、映像がスマートになっている分バランスが悪いのだ。映画を見るかぎり、ウィリーには同性愛的な雰囲気はとぼしく、彼の女好きがドラマの成り行きを左右する。ジャックが愛していたアン(ケイト・ウィンスレット)とウィリーとの関係、ウィリーの頼みで新設の病院長になったアンの兄アダム(マーク・ラファロ)がウィリーとアンとの関係を知るにつれつのらせるウィリーへの不信、ウィリーとその広報官的位置にいるセイディ(パトリシア・クラーク)との愛情的ねじれ・・・といったパーソナルなレベルの屈折が、この映画では旧作よりも前面に出る。ジャックの出生の秘密がドラマチックなものになっているのも、一つのサービス。しかし、これらは、マクロポリティクスよりもミクロポリティクスへの関心から描かれているわけではないので、もともと旧作にもあった疑問――なぜ最初「理想主義的」に見えた政治家が権力を握るとダメになってしまうのか――が、ますますあいまいなままになってしまうのである。
◆ウィリーが有名になったのは、倒壊した小学校の建物の事故の背後に建築会社の手抜き工事をジャックが新聞で書き立てた(という設定だが、彼がそんなに働いた感じはしない)ことが大いに影響したが、それによって高まった評判をタイミングよく利用しようとしたのは、市の役人で黒幕的な存在のタイニー・ダフィー(ジェイムズ・ガンドルフィーニ)だった。彼は、ウィリーに知事選に出馬することを薦める。これが、票をちらせる策略であることをすぐにジャックが見抜き、ウィリーに教える。彼は、すでにウィリーの「官房長官」の役柄をつとめていたわけだ。
◆旧作でも、自分がどうせ捨て駒なのだと気づいたウィリーが捨て鉢的に演ったアドリブの選挙演説が貧しい人々に受け、そこからアッピールの手法をウィリーが体得して行くシーンが見せ場になっており、新作もそれをほぼそのままなぞっている。しかし、新作の方が、そのアドリブ演説がどんどんアジプロ的になり、まるでヒトラーの演説のような熱気を帯びて行く。その点では、旧作にあったある種の両義性(ウィリーは単なる「独裁者」ではないこと)が単純化される。
◆『エイプリルの七面鳥』でその力量を見せつけたパトリシア・クラークが演じていることもあって、セイディ・パークという女性の存在と行動が、なかなか意味深なのだが、彼女の演技はここではそれほど活かされてはいないように見える。彼女は、ウィリーの広報担当官的立場にいながら、彼の限界を見据えており、見方によっては、彼女が、タイニー・ダフィーとつるみながらウィリーを追いつめて行くようなところがある。このへんは、旧作は単純だ。しかし、そういう陰謀が隠されていたとしても、その動機が彼女の嫉妬のレベルに単純化されてしまうので、多くの暗殺事件につきものの構造的な陰謀の側面が描かれたことにはならないのだ。
◆旧作は、大恐慌後のアメリカで浮上したある種「共産主義」的な風潮――政府の復興計画「フェデラル・プロジェクト」にもそういう要素があった――を意識している。ウィリーが、公共施設を拡充し、医療費を無料にするというようなやりかたがそれに該当する。つまり、ウィリーの登場と没落は、アメリカにおける「共産革命」(第二次世界大戦後に東欧やアジアで社会主義政権が登場したことに呼応する――だから「フェデラル・プロジェクト」をアメリカ版のソフトな共産主義とみなす論者もいる――の帰趨を体現化しているのである。しかし、新版では、そういう面はほとんど無視されている。
◆話は飛ぶが、九鬼周造は、幼いとき、ときどき母のもとを訪ねて来る岡倉天心にひょっとして彼が自分の父親なのではないかという直感を感じたという。九鬼自身は、そこまではっきり書いてはいないが、この映画で、アンソニー・ホプキンスが演じる判事が幼いジャックと遊ぶシーンをいまのジャック(ジュード・ロウ)が思い起こすシーンを見ながら、ふと九鬼のこの話を思い出した。なお、九鬼自身が岡倉天心について書いた「岡倉覚三氏の思い出」(『をりにふれて』所収)は、長らく絶版になっていたが、いまでは、『京都哲学選書第三十巻 九鬼周造「エッセイ・文学概論」』(燈影舎)で読める。
◆ケイト・ウィンスレットが、マーク・ラファロとジュード・ロウと3人で水辺におり、彼女がいきなり「泳ぎたいわ」と言って、水に入って行くシーンがある。わたしは、ここで、またウィンスレットがヌードになるのではないかと思った。彼女のヌードが見たいからではなくて、彼女は、映画のなかでヌードになるのが好きなのではないかと思わせるシーンに何度か接したからである。
(ソニー試写室/ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント)
2007-03-13_2
●ボルベール〈帰郷〉 (Volver/2006/Pedoro Almodóvar)(ペドロ・アルモドバル)

◆『プレステージ』を見て「満腹」してしまったので、あと1本は過剰かなと思ったが、見たい作品で、しかも同じ試写室で見ることができるので、とどまる。結果は、やはり無理して見てよかった。
◆ペネロペ・クルスはいまではハリウッド俳優だが、その本領を100%発揮できるのはスペイン映画においてだと思う。彼女が「美人」を売り物にするような作品で面白いものはない(たとえば『サハラ』)が、この映画のように、育ちが「下流」で、ある種の修羅場を歩いて来たような女を演じると他の追従を許さない。本作は彼女のこれまでの出演作のなかでもトップクラスに入るだろう。
◆最初のシーンで、おびただしい数の墓石を中高年の女性たちが掃除している。墓をいつもぴかぴかにしておくのがこの村ラ・マンチャ(ドン・キホーテの村だ)の風習だという。男の姿は、墓地の管理人とおぼしき男が2人ぐらいしか見えない。以後の展開でわかるが、この映画では「男」の居場所がほとんどない。出て来てもすぐ殺されてしまったり、ただの行きずり的存在だったりで、話は、幾組かの「母親と娘」を中心にした女たちの目から描かれる。
◆この映画に登場する女たちは、みな、男で苦労している。ライムンダ(ペネロペ・クルス)には15歳の娘パウラ(ヨアンナ・コバ)がいるが、娘は、自分の父親を知らない。いっしょにいるライムンダの男は、パウラに好色な目を向ける。男ってやつはどいつもしょうがない。ライムンダの父親は、火事で死んでしまったが、隣家の女性と不倫をしていたらしい。その女も火事で死んだ。ライムンダの母親もそのときから行方不明なので、火事で死んだとされたが、その後、幽霊になって村に姿をあらわすという噂が流れた。
◆独特の習慣が人々のきずなになっており、幽霊も信じられる村だが、ライムンダの母は、その村で最初のヒッピーだったという。火事で死んだ隣家の女性の娘がアグスティナ(ブランカ・ポルティージョ)で、ライムンダの母を尊敬しており、庭で栽培しているマリワナを常用している。彼女は、火事のときから記憶を失ってしまったアイムンダの叔母のめんどうを見ている。叔母はずっと一人で住んでいる。ライムンダ母娘と、ライムンダの人のよさそうな姉のソーレ(ロラ・ドゥエニャス)ハ、マドリッドに住んでいるが、墓の掃除でラ・マンチャにやってきた。その後すぐに叔母が死に、ふたたびこの村にやってくる。
◆この地方独特なのだろうか、女たちのキスの仕方が独特。頬の両方に交互に唇をつけるだけでなく、そのとき「チュッ」という音を激しく立てるのだ。特に、アグスティナがすごい。彼女は短髪で、レズなのかと思ったら、(おそらく)抗ガン剤の影響でそうなったらしい。アメリカで質の高い治療が受けられるというので、アメリカ旅行とセットになったテレビのクイズへの出演を、テレビの司会をやっている妹から薦められて決心するが、家族の話をする段になってスタジオを去る。
◆この映画では、殺人も、あまり深刻なショックをあたえない。娘が殺した「義父」の死体から流れた血をライムンダが拭き、死体を隠し、やがて捨てに行くシーンはリアルだが、逆にその分おかしみがあるのはなぜだろう? パウラは、自分をレイプしようとした「義父」を軽蔑し、憎んでいるはずいだ。ライムンダも、仕事もせずビールを飲んでテレビを見ている「夫」を罵ってもいた。しかし、ライムンダは、その死体を、彼が好きだった川べりに埋めるのであり、かたわらの樹に「1967-2006」という「墓碑銘」を刻む。これも、どことなくおかしい(ユーモラス)と思うのは、わたしがおかしいからだろうか?
◆ライムンダとはちがってやや内気の姉は、「もぐり」の美容院を開いている。姿をくらましていた母親がまず接触するのが彼女だったのもわからないでもない。死んだか失踪したかのはずだった母親がどうしていまごろ姿を現したかは、映画を見てのお楽しみ。
◆この映画では、さまざまな小道具がうまく使われているが、食も重要な小道具になっている。ライムンダが、隣にある閉鎖されたレストランに「夫」の死体を隠しているとき、たまたま休みなのかと思って立ち寄った映画撮影クルーの男(助監督?)が、クルーのために30人分の昼飯を用意してくれないかと言ってくる。それを引き受けるライムンダのキップがなかなかいい。ただちに食材を買いに行き、たまたま出会った友人たちをうまく動員して、肉やソーセージやデザートまでも短時間に調達して、映画屋の希望を満たす。これがきっかけになって、その後も食事を提供し、撮影の打ち上げパーティまで引き受ける。その席でペネロペ・クルスが聴かせる歌がいい。ちなみに、ペネロペ・クルスは、『ウーマン・オン・トップ』でも料理のうまい女を演じていた。
(ギャガ試写室/ギャガ・コミニュケーションズ)
2007-03-13_1
●プレステージ (The Prestige/2006/Christopher Nolan)(クリストファー・ノーラン)

◆クリストファー・ノーランの新作で大いに期待して見た。それは全く裏切られなかった。エクセレント! 最近見た作品のなかで一番高く評価出来る。このあとに、同じ場所でペドロ・アルモドバルの試写があり、今日は同じ場所で2本見るつもりだったが、終わってから、この作品についての思いが加重し、今日は1本だけにしておこうと思ったくらいだ。というと、以下にその思いが華麗に披露されそうだが、この映画、「ネタバレ無用」のわたしでも、不遜に書いてしまうわけにはいかないことが多すぎて、書き方に迷う。
◆まずは比喩的に。コンピュータのエディターなどにファイルの「移動」という機能があるが、これは、実際に何かを移動させているのではなくて、移動すべき場所に同じものを「複製」し、そのあとで(ほとんど同時に)「消去」しているのである。これが、デジタルの世界における「移動」であり、モノを持ち運ぶことによって「移動」とみなすアナログの世界との根本的なちがいである。つまり、デジタルの世界というものは、「非情」なのであり、同じものが「複製」でき、そこには、「オリジナル」は存在しないという形而上学を前提にしている。
◆押し入れの奥にしまい込んでしまって出すのが億劫なので、「同じもの」を買ってしまうという人がいる。これが可能なのは、ベンヤミンが言った「複製を可能にする技術」が進み、(同時に「オリジナル」信仰が失われ)代替可能なモノが出回るという時代になったからである。そういう時代だから、「・・・枚限定」というようなCDを出すことが逆に意味を持ったりもするわけだが、CD自体は完璧に「複製を可能にする技術」の産物だ。が、では、人間はどうか? クローン羊はすでに存在する。が、意識や感情を持った生きものを「複製」するのは難しい。われわれは、「複製を可能にする技術」に頼らなくても、日々、細胞を複製しながら生きているが、「記憶細胞」がうまく「複製」されなかったり、バグを「複製」したりして、トラブルに巻き込まれている。
◆クローネンバーグの『ザ・フライ』(カート・ニューマンの『蝿男の恐怖』のリメイク)は、人間を電気・電子的な操作で「瞬間移動」ないしは「テレポート」するわけだが、そのためには人間をまずデジタル的に「複製」し、「移動」地点を結ぶ電線のなかに通すわけである。しかし、『ザ・フライ』では、こうした操作に「複製」→「削除」という過程が必ず随伴することは全く描かれなかった。それに対して、『プレステージ』では、まさにそのことがドラマのかなめであり、このことを知っていると、ノーランがこの映画で示した生身の身体と機械的に「複製」された身体との相違に関する洞察の深さが実感できるのである。
◆とはいえ、この映画は、クローネンバーグなどにくらべると、「メカ」頼りではない。出て来るものは、みなこけおどしではなく、実際に起動しうる(しそうな)機械ばかりであり、ドラマの中心は、きわめて「生身の肉体」によって描かれる。時代は、19世紀末のロンドン。まさにチャールズ・ディケンヅが描いたようなドロドロしたうさんくさいリアリティにあふれた街である。映画は、そんな街であの手この手の「マジック」(奇術手品)を披露するマジシャンを登場させる。この時代の雰囲気からすると、「マジシャン」というより「奇術師」と言う方が似合っている。奇術のアイデアから劇場の手配までをコーディネイトしている老奇術師をマイケル・ケイン、その弟子から出発して、ライバルになる2人の奇術師をそれぞれ、クリスチャン・ベールとヒュー・ジャクソンが演じている。ベールが演じる天才的な奇術師アルフレッド・ボーデンと、陰険なアレンジャー的才のあるロバート・アンジャーとは、ちょっとアップルのスティーヴ・ジョブズとマイクロソフトのビル・ゲイツとの関係を思わせる。映画だから、もっと女や殺しがからむのだが。
◆ノーランが奇術をとりあげたのは慧眼だ。というのも、映画は奇術と親類だからである。バスター・キートンの映画などは、奇術そのもののようなものもあったし、特殊撮影はみな奇術だと言えないこともない。この映画には、ニコラ・テスラの電気仕掛けが登場し、それが半端でない重要な役割を演じるが、電気仕掛けは、19世紀の奇術では人気の仕掛けだったらしい。いまでは 「メジュマライズ」mesmerize (催眠術をかける、幻惑する等々)や「メジュマリズム」(催眠術)といく言葉になっているフランツ・アントン・メジュマー(1734-1815)は、その学説においてよりもそのいささか見せ物的な(奇術的)プレゼンにおいて名声を博していた。テスラーの場合も、いまでは、ラジオやテレビの技術、はては、レーザービーム兵器の草分けのような評価を受けているが、彼が生きていた時代には、その際物(キワモノ)性の方が有名だった。
◆このテスラをデイヴィッド・ボウイが演じているのが愉快であるが、いまでは世界標準になっている交流電気が、直流電気を普及させようとしたエジソンの政治力で駆逐されるエピソードなどもちらりと出て来る。実際にどうだったかは知らないが、この映画では彼が、「テレポーティング」のシステムを実験するために要する巨大な電力の使用をカモフラージュするために、コロラド・スプリングの町を電化し、町が寝静まり、電気を使わない時間に使うというやり方をしたということになっている。テスラに「テレポート」の装置を依頼しようとはるばるロンドンからやってくるヒュー・ジャックマンが、まだ電気があまり普及していない時代に、町中電気が晧晧(こうこう)と照り、やっと訪問を許されたテスラの邸宅がいまの時代のように電気の光で輝いているのを見て驚くシーンが印象的だ。
◆ちなみに、テスラと関係のある最近の作品でこの「シネマノート」でとりあげたものとしては、シェーン・カルース『プライマー』と『コーヒー&シガレッツ』がある。
◆さまざまな奇術の技法が出て来る。ピストルから発射した弾をつかむかのように見せる「銃弾つかみ」とか、小鳥を消して、ふたたび取り出して見せる古典的な技など、その種明かしもある。面白いと思ったのは、すでに小鳥を使う奇術でデジタル的な「非情」な「消去」の方法が使われていたことだ。テーブルの上で布をかけられた鳥かごは、バネ仕掛けでクシャンと板状になるようになっているのだが、当然、そのなかの小鳥は押しつぶされる。そして、その「同等品」が隠された場所から取り出されるのである。
◆ジャックマンとベールとを決裂させるのは、まだマイケル・ケインが手品師として舞台をリードし、2人がサクラになって助手にしてジャックマンの妻役(パイパー・ペラーボ)の手と足を縄で縛り、水を満たされたガラスの水槽のなかに空中から落下する「箱抜け」の奇術の事故からだった。ベールの縛った縄が水中で解けなかったのだ。この場合の「消去」は物理的な移動=脱出なのだが、この場合も、すり替えという技法を使うことができる。水中に落ちた女性とそっくりさんを用意し、水中の女性はどこかに退避し、別のところで待機していたそっくりさんが登場すればよい。しかし、デジタルの発想だと、水中の女性は毎回「使い捨て」にしてしまおうというのである。むろん、そのためには、同じ姿の女性をかぎりなく「複製」できなければならない。
◆直接映画と関係のないことばかりを書いているが、映画を見てくれれば、ここで書いていることの意味がわかるだろう。だいたい、この「シネマノート」は、作品を見ていない人にこれから見るための情報を提供する意図で書いているわけではない。むしろ、見た人と経験を共有するために書いている。だから、「ネタバレ」を非難される筋合いはないのだが、とはいえ、見ていない人も読むし、検索エンジンで「データ」として使われたりもするので、「ネタ」の要点だけが、検索項目の見出しに出てしまうというのは避けたいと思うのだ。
◆クリストファー・ノーランは、『メメント』で記憶を、『バットマン ビギンズ』で「変身」をテーマにした。いま、彼の『プレステージ』を見ると、彼の関心が、「複製を可能にする技術」のもとでの身体・肉体(「記憶」の要所としての脳も含む)にあることがいよいよ明らかになった気がする。『メメント』の主人公は、身体的・肉体的な「記憶」を手書きのノートとポラロイドカメラのスチル写真へ転写・複製しようとする。彼が描く「バットマン」は、先天的な特殊能力者ではなく、さもなければ「普通」の人間が、たまたまあるテクノロジーの洗礼を受けてしまったことによってその身体・肉体が変わってしまったという描き方だった。そして、ノーランは、亢進するテクノロジー環境にもかかわらず、「生身」の身体・肉体の一回性を支持するのである。
◆ベールの恋人でやがて妻になるサラを演じるレベッカ・ホールがうまい。その目が実に多くのことを語り、同時に、これはわたしの誤解かもしれないが、あたかもクリスチャン・ベールに恋してしまったのではないかというような目つきをすることがある。この映画には、ジャックマンの助手として登場し、複雑な役割をする女性の役でスカーレット・ヨハンソンが出てくるが、あまり彼女の本領が活かされていないように見える。しかし、最後になって、レベッカ・ホールとスカーレット・ヨハンソンの顔の輪郭と体型がどことなく似ている(おそらくヨハンセンの方をホールに合わせた?)ように感じられるときが何度もあったことが、錯覚ではなかったことに気付くのである。この映画自体が「奇術」なのだ。
◆なお、「プレステージ」というタイトルは、ナレーター役でもあるマイケル・ケインが、奇術には、1に「確認」、2に「展開」、3に「プレステージ」があるという言うところから取られている。「prestige」は、通常、「名声」「威信」という意味だが、語源辞典によると、古くはごまかしやトリックを意味したという。
(ギャガ試写室/ギャガ・コミニュケーションズ)
2007-03-12
●ラブソングができるまで (Music and Lyrics/2007/Marc Lawrence)(マーク・ローレンス)

◆ヒュー・グラントとドリュー・バリモアにはやや特別の思い入れがある。その理由はきわめて単純。グラントは、わたしが親しいメディア・アーティストのハンク・ブルによく似ていて、彼が出演する映画を見ていると、ハンクと会っているような気になること。バリモアの場合は、『E.T.』で家を出た父親を慕ってメソメソしている子役時代からいまの大女優になるまで見てきて、感情移入していること。きわめて「極私的」な理由だ。
◆マーク・ローレンスの「下流」への目線がいい。ヒュー・グラントもドリュー・バリモアも、大スターだが、2人はいつも「下流」への関心が高い俳優たちだ。この映画には、映画のなかでスーパースターという設定のカリスマ女性歌手(ヘイリー・ベネット)が登場する。バリモアは、そういうカリスマ歌手とは世界のちがう、庶民的というより「落ちこぼれ」の女を演じているが、この人は、オーラを消す演技というものが出来ることを証明している。
◆しかし、これは、この映画で長編初デヴューのヘイリー・ベネットの起用が功を奏した面もあるかもしれない。この人、不思議なオーラを発する新人で、バリモアを相手にしても全然動じず、ウソっぽくならずに、え!? この人誰?と思わす演技と歌唱を披露する。ビヨークをもう少し大柄にして、セクシーにしたような外観。次回作が大いに期待される大型新人。
◆80年代ポップスのおふざけから始まるが、押さえるところはきちんと押さえている。たとえば、ヒュー・グラントが、自分のアパートの片隅のちっぽけなテーブルでメロディをつくり、コンピュータに取り込み、多重録音していって、曲を作り、その音をバックにしてドリュー・バリモアといっしょに歌を入れていくシーンは、映画がよくやる技術過程の飛躍を極力抑えている。このやり方で作れるからだ。日常のさりげない描写がしっかりしている。
◆一度スターの経験をしてしまうと、このグラント(役名ではアレックスだが、俳優名で書く)のように、悟り切った感じにはなれない。どこか荒れて、すさんだ表情を見せたりするものだが、彼は、むしろ、えげつない(あきらかに「ユダヤ系」であることを示唆するステレオタイプの演技だが、そこが笑わせる)マネージャー(ブラッド・ギャレット)の指示にしたがい、遊園地や祭りのイヴェントで小遣い銭を稼ぐことに身を殺している。
◆若干過去の屈折をただよわせるのはババリモアで、彼女は、愛した作家(キャンベル・スコット)に裏切られ、自分の文才に疑いを持ってしまった。これもありがちではあるが、「こういうのってあるよね」という感覚で観客を引き込む要素がある。当然、ちょっと登場するキャンベル・スコットの売れ子作家は嫌みな感じで、バリモアが傷ついていることが実感できるようになっている。
◆バリモアの姉で、かつてグラントの舞台に熱狂したファンだったという設定のローンダを演じるクリステン・ジョンストンがなかなかいい。おそらく、暗黙の設定は、ユダヤ系ではないかと思う。家での食事シーンでも、また妹ソフィー(ドリュー・バリモア)にも「ジューイッシュ・ママ」的にふるまう。その押しつけがましさとパワーがすごく、笑わせる。
◆試写の会場では、オープニング・シーンに笑いが起こった。80年代のミュージック・ビデオ・クリップをパロディ化した形で、ヒュー・グラントのスター時代を紹介する。その踊りやミエの切り方が当時の有名バンドを皮肉に参照していて、笑わせるわけだ。
◆ヘイリー・ベネットは、スーパースターという設定だが、仏教に凝っていて、挨拶はすべて手を合わせ、舞台には巨大な大仏像が登場したりする。それらは、大スターが入れ込むオリエント趣味の浅薄さや、スターの高みに登った者には回りが何も言えず、本人はどんどん空想的な世界にはまり込んで行くありがちなパターンが揶揄されていることはたしかだが、そのままずるずる揶揄を続けない踏ん切りのいい演出で、ただのパロディものには陥っていない。
◆仕事のないヒュー・グラントのところに、ヘイリー・ベネットから仕事が舞い込む。彼女は、少女のころグラントのファンで、彼とコラボレイションがしたいと思い、曲を依頼してきたのだった。が、作詞家をアパートに呼んで打ち合わせをしていたとき、たまたま臨時の代理で植木の手入れにやって来たのがドリュー・バリモアで、彼女がちらりと口にした詩文にグラントが惚れ込んでしまったのだった。しかし、彼女の方は、文章を書くということがトラウマになっており、身を入れることができない。しかし、グラントの方は、絶対に彼女だと思う。あとは、書かなくてもわかる成り行きだ。
◆安易なストーリーなのだが、それぞれにねばりのある個性的な役者たちが配置されていて、見ていて厭きないというのが、この映画の感想。グラントが特訓の末、はじめて映画でピアノを弾き、歌を歌うのも、シーンに出来合いとはちがうリアリティをあたえている。歌のシーンでは、ヒューとヘイリー・ベネットが絶唱するシーンが見せ場だが、わたしは、前述の、ドリューとヒューがヒューのアパートで一緒に歌うシーンが一番よかった。
(ワーナー試写室/ワーナー・ブラザース映画配給)
2007-03-07_2
●大帝の剣 (Taitei no ken/2007/Tsutsumi Yukihiko)(堤幸彦)

◆プレスで木俣冬氏が、この映画を「ハチャメチャ」という言葉で形容し、横田順彌を持ちだしていたが、ほめすぎだ。横田順彌的な「ハチャメチャ」とは、「ハチャメチャSF」がはやっていたときに書いたことがあるが(「SFの語源学」)、いわば記号論的な「ずらし」をかぎりなく持っているものであって、この映画のように、そうした「ずらし」がほとんど不可能なダジャレにとどまるものではない。
◆この映画は、予測不可能な「ずらし」を想定しているというよりも、非常にセコイ計算のなかで作られている。つまり、ありもののCG技術と特殊メイクのテクニックを有効に利用しようというわけである。テクニカルなパロディもにぶい。だから、映像の面でも、目を見張るものはない。
◆阿部寛と長谷川京子は、それなりにがんばっているが、ブースト度が低い。宮藤官九郎は、ここでも天才的なセンスを発揮しているが、杉本彩と同様、活かされていない。わたしがこの映画で唯一いいなとおもったのは、遠藤憲一の「あっら、あっら、あっら」というぼやき的なうめき声ぐらいか。これは、何かのパロディ?
(東映試写室/東映)
2007-03-07_1
●あるスキャンダルの覚え書き (Notes on a Scandal/2006/Richard Eyre)(リチャード・エア)

◆レズであるかどうかよりも、一人身で老年を迎える女性の「週末はコインランドリーに行くぐらいしかない」孤独をジュディ・デンチが、見ていて困ってしまうくらい迫真の演技を披露。
◆デンチ(以下、登場人物名は略す)にストーカー的な愛を押しつけられる女性をケイト・ブランシェットが演じていて、両者の風貌の対照性が劇的効果を高める。ありがちではあるが、嫌いなわけではないが、ついていけないというところまで追いつめられたブランシェットが、「あんた、ヴァージニア・ウルフ気取りなの!」と逆襲するシーンは、なかなか見もの。
◆フィリップ・グラスの音楽は嫌いではないが、この映画では、彼の音が出しゃばりすぎて、わずらわしい。キャラクターの感情が高まると、判で押したよいうにグラスの音が画面をすっぽりおおってしまうようなあつかましさを見せる。グラスは映画にかなりコミットしているが、そのなかでは、『めぐりあう時間たち』がよかった。
◆製作はアメリカだが、映画としてはイングシッシュ。だから、アメリカよりもより階級的な要素がドラマの隅々に布石として置かれている。デンチは、おそらくワーキング・クラスの出身だろう。自力でがんばって中学校の教師をつとめ、もうじき定年を迎える。学校ではこわい先生である。そこへ新任の教師としてやってくるのがブランシェット。その姿を見たときから、デンチの心は揺れる。こういう感じって、よくあるでしょう。ブランシェットは、ミドル・クラスの奥さんで、夫(『ラブ・アクチュアリー』のビル・ナイ)は大学で教え、ものを書いているらしい。子供の一人はダウン症で、夫はそのめんどうをよく見る。ブランシェットは、彼の教え子で、「不倫」から再婚に至ったらしい。
◆映画は、デンチが毎日つけている日記の「内的独白」の形式で進む。デンチがブランシェットの家に食事に呼ばれての感想のなかに、ミドル・クラスへの軽蔑の念が出ている。家庭のしつけは自由で、食後、音楽をかけてダンスを踊る。デンチみいやいや加わることになるのだが、この「ファミリー・トラディッション」には耐えられないと彼女は思う。
◆この映画の原題は、ブランシェットが、教え子を愛してしまうということが「あるスキャンダル」であるということと同時に、デンチが彼女の思いを日記に書いているということが一つのスキャンダルであるということを示唆している。どんなに即興的に書いても、書くということには、「意識の罪」が介在する。どこかで相手と世界を冷静に対象化しているからだ。デンチが夕食に呼ばれたとき、ラザーニアは好きかと聞かれ、デンチは大好きと答えるが、本当は好きではない。映画では、「脂っこくてね」、「少しにしてもらおう」という内的独白で表現されるが、つねに裏があるということが、彼女のスキャンダルなのだ。だから、食卓で、彼女が、ラザーニアの食べ残しを付けあわせのレタスの下に隠したとき、子供が見て、あきれた顔をする。子供というのは、「世間良識」の権化だからね。だから、人は、「子供が見ているぞ」と言って、「良識」をただす。
◆人は誰でもうしろめたいことや秘密があるとしても、それを記録に残すことは「悪徳」だと見なされるらしい。「らしい」というのは、わたしには、そうは思えないし、その理由がわからないが、どうやら世間ではそれが「常識」らしいと思われるからだ。その点で、ブランシェットは、どちらかというとあけっぴろげである。が、それは、性格の問題であるというよりも、彼女が育った環境とも関係がある。デンチの場合は、言いたくても言えない環境で育ったはずだ。年齢的にもブランシェットより30ぐらい上の設定で、ものをずばずばいうことがためらわれる時代のなかで育ったことが推察される。
◆ブランシェット(映画のなかの)は、娘時代にポストパンクの「スージー・&・ザ・バンシーズ」に入れ込み、自分もスージーのメイキャップをまねたりしていたらしい。このへんをつっこんで行くと、ブランシェットがなぜまだ15歳の教え子に惹かれていったかがわかる。それは、ワーキング・クラス願望なのだ。スージーは、ナチスのかぎ十字をつけたりしてスキャンダルを起こしたことがあるが、ナチが何であるかをよく知らずにとになく嫌みや反逆を表明するために大胆なことをするというパンク的発想は、ミドルクラスのリベラリストには受ける。まあ、朝日新聞が安全圏の枠内で「反乱」や「造反」に関心を示すようなものだ。
◆この映画でデンチは、ブランシェットの非難は受けるが、社会的な制裁は受けない。ここには、ミドルクラスへのワーキングクラスの復讐のような趣きがないでもない。見晴らしのいい高台のベンチでのモノローグから始まる映画は、同じベンチで歳下の見知らぬ女性に声をかけるシーンで終わる。がんばっているね、という感じだが、これが男の老年という設定だと、特に日本では、早速制裁を加えられるのではないかな?
(FOX試写室/20世紀フォックス)
2007-03-06
●眉山 (Bizan/2007/Inudo Isshin)(犬童一心)

◆宮本信子が最初やけにテンションの高い演技を見せたので、ちょっと気まずい感じに襲われた。『マルタイの女』(1997)以来、10年ぶりの映画出演というのではりきりすぎたのかと思ったら、登場人物のキャラクターがそういうようになっているのだった。病院で注射のへたな看護師に注意するシーン、若い医者(大沢たかお)の言葉じりに文句をつけたあと、謡を口ずさみながら去って行くといったシーンだが、最初、また宮本、無理しちゃって、と思いながら、だんだん慣れてきて、今回はかなりいいんじゃないかという気持ちになったのだった。
◆宮本信子は、出て来る演技に比して、「自己陶酔的」な目をしているような気がするのだが、ある意味で子供っぽいその表情も、62歳になっていい感じになってきた。特に今回は、末期ガンに侵されながら、無理やりシャキッとした態度を見せようとする女を演じており、モルヒネを投与されているという設定なので、そのうるんだ笑いのある目がセクシーですらあった。
◆しかし、それ自体で完結しているドラマに難癖をつけても仕方がないが、宮本が演じている「龍子」という女性は、世代的には、昭和の女というより、明治の女を思わせる。いまどきこういう女っているのかなという感じだ。原作が「さだまさし」だから、自分の母親(明治か大正生まれ)あたりを想定して書いたのではないか? それだとこういうキャラクターも納得できる。
◆医者は告知しなかったが、自分が末期ガンであることをすべて承知している宮本(以下、俳優名で書く)は、娘(松嶋菜々子)にも告げず、献体の手続きまでしている。遺産相続の書類や、娘には死んだと告げた父親の手紙も整理してある。まあ、出来過ぎた人なのだが、わたしなんかの感覚では、こういうのって、全然「立派」だとは思えない。無理すんなよと言いたくなってしまう。むろん、映画はそれでは済まないから、そういう母親の予測と予定をちょっぴり裏切る要素を入れる(出来た母親だから、そういうこともお見通しだったのかもしれないが)。
◆父親が生きていることを知って、松嶋がこっそり訪ねていくシーンがいい。風邪を装って診察を受けるその診療所で、最初カメラはその男の背中を映す。が、その顔が見えると、それが、夏八木勲である。この役者って、妥協の人を演じるのがうまい。若いときはハンサムだったことをただよわせる顔に白髪と(年輪というよりも)老いと疲れをただよわせた感じ――夏八木にぴったりなのだ。松嶋の母は、妻子のある夏八木を愛し、松嶋を生んだ。夏八木は、手紙のなかで、「ささやかながら」自分の病院(映画では「病院」というが、わたしの印象では「診療所」)と献身的な妻を捨てられないと書く。宮本は、それを受け入れて、夏八木の故郷、徳島に幼い娘を連れて移り住む。何でよりにもよって徳島にという気もするが、夏八木への愛と、夏八木といっしょに見た「眉山」、それから阿波踊への愛だというのだが、やや、演出上のアレンジのような気がしないでもない。ちゃきちゃきの「江戸っ子」という設定の宮本が、そんなことで東京を離れるだろうか?
◆こういう問いは、ルール違反になるかもしれないが、ストーリーが、出来事の必然性から組まれているのか、それとも、演出効果の必要から組立たれたのかは、興味深い。クライマックスを阿波踊で盛り上げようという演出では、必要な設定だからだ。
◆松嶋が訪ねて行く父親の診療所は、「文京区本郷5-32-4」という表示になっている。このあたりは、西片の菊坂下に近い、なかなか雰囲気のいいところだ。阿波踊などで盛り上げないで、このへんで撮った方がもっとよかったような気がするが、撮影現場となった徳島市がこの映画に熱い期待をかけていたらしいから、そんなことを言っては酷か。
◆出て行ってしまった父親とか、死んだり、離別した親とか、そういう父や母を子供が慕(した)い、探し求めて会うとかいう話は、テレビでも映画でも小説でも、「感動」を構築する基本設定の一つになっているが、あなたが、実際にそういう状況にあるとしたら、あえて探しだしたりしない方がよいという気がわたしにはする。探しているあいだはいい。しかし、会ってしまったら、失望することの方が多いだろう。この映画では、再会した父を否定的には描いてはいないが、夏八木勲というすぐれた役者がかもしだす雰囲気、彼が役者としてこれまで演じてきたキャラクターの記憶、そういうものがごたまぜになって(そういう見方も映画にはある)、会わない方がよかったのになと思ってしまうのだった。
◆映画のシーンは、阿波踊の祭りの準備の期間と重なっているのかもしれないが、この映画を見ていると、徳島の人って、何かというと阿波踊ばかり踊っているという印象をうける。南米の街角のシーンが映ると、子供たちがみんなサッカーをやっていたり、日本の子供は「かもめ、かもめ」ばかりやっているというのと似ている。
◆東宝の上映設備は非常によいものになった(以前はひどかった)ので、映画自体がそうなのだと思うが、音の採り方が単調だ。音が右と左の固定した場所から聞こえて来る。
(東宝試写室/東宝)
2007-03-02_2
●しゃべれども しゃべれども (Shaberedomo Shaberedomo/2007/Hirayama HIdeyuki)(平山秀幸)

◆気張っていないところがいい。下町だ落語だというと、これが下町でございといった姿勢がでがちだが、平山監督にしてはやや肩の力を抜いて撮っているようにみえる。本当はそんなことはないのかもしれないが、その感じがいい。一応、浅草や隅田川やほおづき市なども出て来るが、「観光百科」にはなっていない。
◆一応名人という設定だが、伊東四朗が演じるわけだから、どこかいんちき臭い。その弟子を演じる国文太一となると、素人の域を出ていない気がするが、実は、そういうキャラクターが設定されているのだということが見ているうちにわかる。落語家が、会社のゲスト講師として社員をまえに講義をするなんてのは、伊東四朗のややくわせもの的な雰囲気が合う。そのカバン持ちで来た国分は、途中で出ていった一人の女(香里奈)を追いかける。それが縁で、知り合うようになるのだが、この女、えらく感じが悪く、言葉の使い方を知らない。孤独に家業のクリーニング屋の配達を黙々とやっているのだが、彼氏と別れたあとであることぐらいしか、訳ありの理由は分からない。この映画は、あまりそういう深入りはしない。
◆あんまり深く突っ込まない(だから「くどい」という言い方がよく使われる)のが東京の下町のルールでもあるかのようなところがあるが、この映画もそんなノリで行く。国分は、両親が早く死んで、祖母(八千草薫)といっしょに住んでいる。色々な思いがあるのだろうが、それには触れないで生きているような気配がある。
◆国分が自宅で開く「話し方教室」というのも、よくわからないが、そこにやってくる元野球選手(松重豊)はわからない人物の筆頭。あまり突っ込まないのが江戸風だとしても、テレビで野球の解説をやりながら、兄の焼き鳥屋で働いているが、店では、その口下手が笑いの的になっている。こういういそうでいない人物が次々と出てきて愉快である。
◆近所の親が国分の教室のことを聞いて連れて来た息子(森永悠希)は、大阪出身ということになっているが、実に口が立つ。子役で年期の入った森永が演るのだからあたりまえだが、国分から借りた桂枝雀のビデオを見て、「枝雀を覚えたで~」と言ってやってくる。その枝雀のまねがすごくうまいのだが、映画では、このシーンはそれだけで終わりになってしまう。プレスによると、森永は、実際に枝雀のビデオを観て、動きや話し方を覚えたとのことだが、それ以外もしゃべりが流暢すぎて、ちょっと浮いてしまうくらい。この子何者?という感じ。これもあまり突っ込まないで観るべし。
◆結局、江戸というのは、地方から痛みを抱えてやってきた人でごったがえしていたから、傷物に触らないというのが、おのずからルールになったようなところがある。江戸弁というのは、しゃきしゃきしているように聞こえるが、そういう形で、突っ込まれるのを封じているようなところがある。
(アスミック・エース試写室/アスミック・エース)
2007-03-02_1
●サンシャイン2057 (Sunshine/2007/Danny Boyle)(ダニー・ボイル)
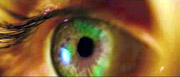
◆「マスコミ試写」は日本が一番早いらしく、試写に行くまえに海外のサイトをさがしても、つっこんだコメントが見当たらなかった。どの程度のものかと思ったが、『ザ・ビーチ』や『28日後・・・』のダニー・ボイルが監督しているので、「マスコミ試写」の初日にかけつけた。映像はいいし、真田広之が英語のせりふでがんばっており、エンタテインメントとしては引きつけるものがある。しかし、太陽が死滅するのを、太陽に核爆弾を打ち込んで再活性化させようという基本のプロットがばかばかしい。エンタテインメントだから仕方がないのかもしれないが、空が曇りつづけるほど太陽が「死にかけて」いたりしたら、地球上は大氷河時代に突入してしまうし、さらに、それが、爆破で空がぱーっと明るくなるようなことが起こったとしたら、(いまでさえ、温暖化で紫外線の当たり具合がわずかに変化しただけで、いろいろ問題が起こっているのに)地球上の生物はばたばたと死んで行くだろう。
◆『不都合な真実』のような映画が関心を呼ぶときに、こういう映画が出来るのも不思議だが、逆に見ると、なぜボイルはこういう映画を撮ったのかに興味を持つ。『ザ・ビーチ』や『28日後・・・』でもそうだったが、彼は、いつも、気を引く題材をとりあげながら、題材そのものへのアプローチの点では極めて一面的ないしは、題材倒れになるきらいがある。むしろ、これまでの作品で一貫しているのは、極限状態のなかでの人間関係である。この映画でも、帰還不能となった宇宙船イカロス2号のなかで8人の乗組員たちがどういう反応をするか、どう生き、どう死ぬかを描く。
◆船長の真田広之は、いかにも「武士」風に行動する。航海士のベネディクト・ウォンは、「中国系」という設定だろうか、操縦ミスを起こし、火災を招いたことで自分を責め、自殺する。状況が切迫してきて自己中心的な行動に出るのは、通信士のハーヴェイ・トロイ。クリフ・カーティスは、精神科医なので、取り乱すわけにはいかないよう。悠々と運命に身をまかせる。ミッシェル・ヨーは、船内の特設ガーデンで植物の世話をしているが、このキャスティングもアジア人というパターンが作用しているのだろうか。
◆この映画では、特別に新しい人間関係というものは発見できない。だから、浮かび上がってくるのは、「地球の運命」を握る使命に対してどうであるかといったことに集約してきて、これでは、ブッシュあたりが喜びそうな話じゃないかという半畳を入れたくなってしまう。
◆物理学的に無理という印象をおぼえるシーンが多いのだが、サスペンスとしては面白い。おまけに、消息不明になったイカロス1号の船長(マーク・ストロング)が、何だかわけのわからない怪物として生き残っていたりして、原理的に無理でも宇宙の果てではそんなこともあってもいいかと思いながら観てしまう。
◆使命に対する疑いやサボタージュの問題がちらりと出て来るが、あまり深くはあつかわれない。映像はいいのだが、仕掛けと発想はえらく古い。
(FOX試写室/20世紀フォックス映画)