|
リンク・転載・引用・剽窃は自由です (コピーライトはもう古い) The idea of copyright is obsolete.
|
| 粉川哲夫の【シネマノート】 |
|
今月気になる作品 G.I.ジョー (海外に出ていて7/23の試写を見れなかった。もったいをつけた試写のやり方などから判断して、2度3度見て細部を詮索したくなるような作品ではないはず) ★★★ HACHI 約束の犬 ココ・シャネル(パリに住む人とこの作品の話をして混乱を起した。「よくもわるくもオドレイ・トトゥの映画」と切って捨てたので気づいたが、その人は、アンヌ・フォンテーン監督の『ココ・アヴァン・シャネル』のことを言い、わたしは、シャーリー・マックレーンが老シャネルを演じる米映画『ココ・シャネル』のことを言っているのだった。まだ見てないが、評判はこちらの方がいい)。 ★★★☆ 縞模様のパジャマの少年 (ガス室に代表されるナチの非情なロジックの暴走に目をつぶっていたドイツ人が、その日常的な無知・不決断のために、そのロジックから皮肉な「仕打ち」を受ける)。 ★★★★ 3時10分、決断のとき (極悪非道な無法者に裁判を受けさせるという西部劇の古典的テーマを描きながら、ひねりと新味を加える。ベール、クロウも悪くないが、脇役がみな一癖ある奴ばかりで雰囲気が出ている)。 ★★★ ナイトミュージアム2 (未来の美術館・博物館はみなこういうヴァーチャル・テクノロジー頼りの方向に進むだろう)。 ★★★★ キャデラック・レコード 音楽でアメリカを変えた人々の物語 (歴史の無理な「再現」であれ、新しい音楽(ロック)の誕生の一齣をこういう形でながめるのは楽しい。オバマ政権誕生とともに、「黒人」の「再復権」の映画が増えている。本作もその一つ)。 ★★★★ 96時間 (リュック・ベッソン製作というから期待しなかったが、アクション映画としてはなかなかの出来。愛娘のためなら敵は誰でも殺しまくる父親というのは、正当化しにくいが、アクションのためと考えれば、どうでもよくなる)。 ★★ ちゃんと伝える (父と息子とのあいだに確執があったかのようにプレスには書かれているが、この程度の葛藤・確執なら、「良好な父子関係」なのではないだろうか?) ★★★★ ホッタラケの島 遥と魔法の鏡 ★★★ ぼくとママの黄色い自転車 (若年認知症に陥り、身を隠した母を、その事実を知らずに追う少年。未知の人々との新鮮な出会いと少しづつ深まる自己認識――なんて硬くは描かないところがいい)。 ★★ 20世紀少年 最終章 ぼくらの旗 (こいつも試写の仕方がもったいぶっているが、まえの2本を見たら、見ないわけにはいかないだろう)。 ★★★★ パティ・スミス:ドリーム・オブ・ライフ (「パンクの女王」以外の彼女の姿と活動の映像、ポリティカルな70年代が詰まっている) ★★★★ クリーン (2004年の作品ながら、まったく古びていない。マギー・チャンがすばらしい)。 |
|
サブウェイ123 激突
さまよう刃
アニエスの浜辺
あなたは私の婿になる
引き出しの中のラブレター
クリーン
あの日、欲望の大地で
20世紀少年―最終章―ぼくらの旗
ホッタラケの島 遥と魔法の鏡
リミッツ・オブ・コントロール
パイレーツ・ロック
母なる証明
わたし出すわ
脳内ニューヨーク
サイドウェイズ
【月間の印象】 ポルトガルの仕事をキャンセルしたので、先月よりは試写に行く余裕が出来た。見てからなるべくその日にノートを書く本来のペースも、少しづつ取り戻しつつある。アメリカでもヨーロッパでも、タランティーノの『Inglourious Basterds』が受けている。部分的な映像を見たかぎりでは、例によって「暴力」描写が凄い。それが、タランティーノ的な「趣味」の新ヴァージョンなのか、あるいは「暴虐な敵への憎悪と復讐」という単純な反ナチパターンを引き継いだものなのかを早く確かめたい。 |
2009-08-28
●サイドウェイズ (Sideways/2009/Cellin Gluck)(チェリン・グラック)

 ◆問題ありでも面白い映画ではあった『サイドウェイ』のリメイクだという本作の予告編を何度も見せられるたびに、「やめてくれよ」という気分になり、試写は見ないつもりだった。が、試写状が何度も来るので、気を取り直し、重い腰をあげた。なかなか面白かった。小日向文世は、ぱっとしなかった(そういう役まわりなんだけど)が、鈴木京香と菊池凜子が、これまでとは違う新鮮な魅力を発揮している。軽薄でいいかげんな野郎を演じる生瀬勝久もなかなかいい。映画は予告ではわかない。
◆問題ありでも面白い映画ではあった『サイドウェイ』のリメイクだという本作の予告編を何度も見せられるたびに、「やめてくれよ」という気分になり、試写は見ないつもりだった。が、試写状が何度も来るので、気を取り直し、重い腰をあげた。なかなか面白かった。小日向文世は、ぱっとしなかった(そういう役まわりなんだけど)が、鈴木京香と菊池凜子が、これまでとは違う新鮮な魅力を発揮している。軽薄でいいかげんな野郎を演じる生瀬勝久もなかなかいい。映画は予告ではわかない。◆元作の『サイドウェイ』以上に、ワインに関しては、いいかげんこのうえない。ワイン好きは見ない方がいい。基本は、銘柄を出すだけにワインを使っているのであり、カベルネ・ソーヴィニヨンとピノ・ノワールとの対比も単なるメタファーでしかない。人間は「カベルネ」派か「ピノ」派かのいずれかに分かれるというようなことが言われるが、ちなみに、ワインのブドウの品種に関し、わたしはカベルネもピノも嫌いなのだ。ただし、わたしのワイン味覚はあてにならない。あるレストランのソムリエに好みをきかれて、カベルネやピノははずしてほしいと言い、「カベルネはあのフルーティーな味が嫌だし、ピノは芋臭い味が嫌なんです」なんて言ったあと、「これを飲んでみてください」と出されたのを飲んだ。なかなかいい味だったので、「これは?」と尋ねると、「いえ、カベルネなんです」との答え。
◆決して「大物」ではないのだが、アメリカ側の出演者がみな手堅い演技をしている。ちょい役でも手を抜いていない。たとえば、ワイナリーのテイスティング・バーでキレてしまった小日向文世が、ワインをがぶ飲みするシーンで、サービスする女性が、驚き、呆れ、怒りを混在させた表情を見せるのだが、その短いシーンの彼女の表情がいい。
◆日系米国人の母を持ち、日本で生まれたという監督のチェリン・グラックは、アメリカ映画が「日本人」を描くときにほとんど必ず陥るパターンに陥っていない。そういうパターンは、日本人自身が感じているものも多いので、それがかなり差別的であっても、笑えてしまうのだが、この映画では、小日向文世と生瀬勝久がどんなに「子供っぽい」ことをしても、差別や諧謔を感じないし、そういうマゾ的な受取方も無用である。予告編では、「日本で一番なさけない俳優(オトコ)二人」という言葉が出てくるが、不思議と、映画を見るとそういう感じがしないのだ。
◆日本人は、海外に行くと、「若く」というより「幼く」見える。それは、いまも変わらない傾向なのだが、近年、状況が変わってきた。アメリカ人が、日本人にいだくような「呆れた」印象を、日本人がある世代の日本人に対していだくという現象が出てきたからである。小日向文世は1954年、生瀬勝久が1960年生まれとのことだが、わたしの印象では、彼らよりもっと後ろの、30台後半から40代前半の世代は、その見掛けや格好とは裏腹に、実に子供っぽい。彼や彼女からすると、小日向と生瀬が演じる世代はまだ「大人」であり、彼らがどんなに「子供」を演じても、わたしには「大人」に見えるくらいだ。
◆なぜこの世代の男たちは、「大人」になれないのだろうか? いわゆる「ピーターパン症候群」の担い手であり、ヒキコモリも少なくない。「親父不在」の世代とも言う。この世代は、家族と顔を突き合わせる「家庭」よりも、テレビやゲームや映画の世界を「ホーム」としてきたような世代である。だから、映画で見た世界にあこがれ、そういう世界を基準にしてものごとを考えがちで、生身の「現実」を忘れる傾向がある。マニュアル志向が強いのもそのためだ。生身の世界で嫌なことがあると、それを避けるために「ヒキコモ」ってしまう。食い物は、ファーストフードや缶コーヒーが「自然」であり、水は水道水ではなく、ボトルの水が安心なのである。この世代は、もっとシャイ度が強く、壊れやすい80年代世代とも違う。大人になれない分、駄々っ子であり、自己主張は強い。そんな歳でもないのに、「老人趣味」のような者もいる。「オタク」世代とも重なっている。こういう連中を「子供」だと言って避けていては仕事にならないので、それを「標準」「あたりまえ」とみなさざるをえない生活をしていると、この映画に登場するような「大人になれない」男たちを見ても、不自然な感じはしないのである。
◆ところで、年齢詐称がないとすれば、鈴木京香は、1968年生まれだという。この映画の出演者のなかで、一番「大人」に見えるのが鈴木なのは、日本の女性がアメリカに行き、本気で働くようになると、みな(日本の同年輩の女性よりも)「大人の女」になるというパターンをとらえているからか?
◆この映画を見て、素質のある俳優は、彼女や彼を異なる言語や文化や地理的環境に置き、それなりの監督や現地スタッフがつくと、それまで見せなかったような新しい才能を発揮するものだと思った。鈴木京香が出る映画はかなり見たが、この映画のなかの鈴木は、これまでの彼女とは全然違う面を出している。菊池凜子も、単なる「海外」向けとは違ったコミカルで軽いキャラクターをつくり出すことに成功している。彼女らは、「ハリウッド出演!」といった力み方をしていないこともいい。こういう、肩の力を抜いた「二流」の日米合作映画をもっと作るべきだろう。
(FOX 試写室)
2009-08-27
●脳内ニューヨーク (Synecdoche, New York/2008/Charlie Kaufman)(チャーリー・カウフマン)

 ◆一枚の紙をかぎりなく折り込んで行くと最後には小さな本のような物体ができる。それを今度は開いて行くと、表面に無数の「襞」(ひだ)のある平面が出来る。ジル・ドゥルーズは、ライプニッツを再解釈して『襞』という卓抜な本を書いたが、この映画は、そういう意味での「襞」(ひだ)で構成されている映画だ。われわれは、折り込むことによって出来上がった「襞」の一つ一つを見せられることになる。全体を広げると、全面に無数の「襞」が見えるが、相互に脈絡はない、というよりも、無限の脈絡が生まれる。なお、原題にある "synecdoche"(シネックドキ) は、辞書的には、「全体をあらわす個/個が全体をあらわしていること/特殊にして全体」といった意味だ。
◆一枚の紙をかぎりなく折り込んで行くと最後には小さな本のような物体ができる。それを今度は開いて行くと、表面に無数の「襞」(ひだ)のある平面が出来る。ジル・ドゥルーズは、ライプニッツを再解釈して『襞』という卓抜な本を書いたが、この映画は、そういう意味での「襞」(ひだ)で構成されている映画だ。われわれは、折り込むことによって出来上がった「襞」の一つ一つを見せられることになる。全体を広げると、全面に無数の「襞」が見えるが、相互に脈絡はない、というよりも、無限の脈絡が生まれる。なお、原題にある "synecdoche"(シネックドキ) は、辞書的には、「全体をあらわす個/個が全体をあらわしていること/特殊にして全体」といった意味だ。◆この映画では、「プロット」とか「筋」とか「ストーリー」といった観念は通用しない。あるのは無数の「襞」である。が、それはあくまでも「襞」であるから、他の「襞」との関係は、きわめて「恣意的」で必然的ではない。その意味で、この映画の楽しみは、「筋」を追う楽しみではなくて、「襞」に注目する楽しみが優先される。
◆むろん、あえて「筋」を探そうとすれば、「筋」らしいものがないわけではない。まず劇作家のケイデン(フィリップ・シーモア・ホフマン)、ミニチュア画を描くアーティストの妻アデル(キャスリーン・キーナー)、その娘オリーブ(サディー・ゴールドシュティン[幼児期]/ロビン・ワイガート[成年期])がいる。個展のためにベルリンに行ったアデルは帰らず、娘はタトゥ・アーティストになり、ケイデンは失望する。劇場で働くヘイゼル(サマンサ・モートン)はケイデンを愛しており、彼も彼女が好きだが、二人の関係は実らない。その間、彼は、マドレーヌ・グラヴィスというセラピスト(ホープ・デイヴィス)のところに通っている。そんな折、マッカーサー・フェロー賞を受賞し大金を得たケイデンは、その費用を投じて巨大な演劇プロジェクトを企画し、自分の人生と自分が住むニューヨークの一角をそのまま舞台化しようとする。が、その役柄と「本人」とが交錯して描かれ、こんな要約で説明のつく「筋書き」では展開しない。ケイデン自身が自分を演じ、その彼を観察している彼(トム・ヌーナン)がいたり、ヘイゼルを演じるタミー(エミリー・ワトソン)は単にヘイゼルを演じているだけではなく、ダイアン・ウィーストが演じる「おばさん」が登場したりして、「筋」を追おうとすれば、何が何だかわからなくなる。
◆こうした「混乱」が意図的なものであることは、映画の冒頭から暗示されている。まず、「7:44」を表示しているケイデンのベッドサイドのクロックラジオのアナウンサーが、「9月22日」(September 22nd)と言っているのが聞こえる。が、朝食のテーブルで彼が開く新聞「The Schenectarian」の一面には「Harold Pinter at 76」の文字が見え、その上に「Ocotber 14, 2005」という日付が見える。その続き(と思われる)シーンで、「Vivian Malone Jones」が死んだという記事を読むが、その上に見える日付は「2005年11月2日」の表示になっている。ちなみにヴィヴィアン・マローン・ジョーンズとは、かつて黒人差別が厳しかった時代にアラバマ大学に初めて入学した2人の黒人の一人で、やがて台頭する公民権運動の象徴的な人物となった。だが、彼女が実際に死んだのは、2005年10月13日であって、それが「11月2日」の新聞に「・・・死んだ(has passed away)」という表現で書かれるのはおかしい。そう、「あたりまえ」の論理では「おかしい」のだ。ついでに挙げると、「10月14日」付けの新聞を見た直後の(と思われる)シーンで、ケイデンは、冷蔵庫からミルクのカートンを取り出し、その賞味期限(「10月20日」とスタンプされている)が切れていると妻に語る。要するに、この映画では、「あたりまえ」の時系列的な時間は意味がないのである。
◆それをケイデンのパラノイアや白昼夢と受け取るのも一つの見方だろう。われわれがスクリーンの上で立ち会う映像の一つ一つが、ケイデンの秒単位で変移する妄想だと考えるのも一つの見方だろう。だが、この映画は、「妄想」というような心理主義的な観念の枠をはるかに飛び越えた認識論の上に立って作られている。とはいえ、セラピストの登場とか、ケイデンが意識していると思わせる孤独や孤立や死への不安や強迫観念がこの映画のモーチーフの一つになっていることも明らかなのだ。
◆先述の冒頭に出てくるラジオから「Union Collage」の「教授」が「秋の詩」について語り、詩文を朗読する。
Whoever has no house now will not build one anymore.これは、字幕には出てはいなかったが、ライナー・マリア・リルケの有名な詩「秋の日」(Herbsttag)の英訳だろう。原詩からの手塚富雄訳のこなれた邦訳でわかるように、えらく寂しい心境の詩だ。ある意味で、この詩は、ケイデンの最初から最後までの心境を表現してあまりある。
Whoever is alone now will remain so for a long time,
will stay up, read, write long letters,
and wander the avenues, up and down,
restlessly, while the leaves are blowing.
いま家をもたない者はもはや家を建てることはありません。◆死への不安の強さは、起き出したケイデンが外の郵便受けを開けると、酸素マスクを着けた末期患者の写真が表紙に載っているパンフレットがあり、「Attending to Your Illness」(あなたの病気をお世話して)という文字が見える。食卓で「10月14日」付けの新聞を見ながら、ケイデンは、「ハロルド・ピンターが死んだよ」とアデルに言い、すぐに「あ、待って、そうじゃない、ノーベル賞を取ったんだ」と言いなおす。「Harold Pinter at 76」という文字を見て、「死んだ」と思ったのは、彼が、死のことを考えてばかりいるからだ。
いま独りぼっちでいる者はいつまでも独りぼっちのままでしょう、
夜は眠りをもたず 本を読み 長い手紙を書くでしょう、
そして並木大路を 落ち着きなく
往ったり来たりするでしょう、樹々の葉の飛び散るなかを。
◆娘のオリーブ(サディー・ゴールドシュティン)の便の色に母親のアデルは神経質だが、ケイデンも便の色を気にする。あるシーンでは、彼の便の色は黒色だ。まるで下血の便だ。洗面所で水道の蛇口をひねろうとしたらその一部がはずれて飛んできてケイデンの額を傷つけるという突発事故が起きるが、この一件で水道屋を呼び、その修理中にトイレに行きたくなったケイデンが、地下にあるアデルのアトリエに降りてきて、「流しで小便させてもらえる?」と言って、小便をする。そのときに映る彼の小便はまさにチョコレート色で、これは、血尿か胆管ガンの患者の小便の色である。ということは、彼は、すでに相当重い病にかかっているのかもしれないということだ。
◆この映画のすぐれたところは、細部を文字化しても「ネタバレ」にはならないという点だ。それは、映画として傑出した作品のすべてに言えることであり、さらには映画にはもともと文字表現による「ネタバレ」などというものはありえないということなのだが、この映画の場合には、その点が明快だ。批評する者にとっては批評冥利につきる。が、そんなことを延々と続けるのもナンだから、このへんでやめよう。いずれにしても、この映画は何度見てもあきないだろう。
◆ベンチに座っているケイデンのところにうれしそうな顔をしたサマンサ・モートンがやってきて、いきなり「(カフカの)『審判』を読んだわよ」と言う。座っていきなりということは、彼がまえに薦めていて、それを読んだという意味だろうか? 『審判』とこの映画との関係も意味深である。
◆映画のいくつかのシーンで、シーンにシンクロした音声や音楽と並行して、ピロピロピロというラジオーアート的なエレクトロニカのサウンドがなり続けている。チャーリー・カウフマン+スパイク・ジョーンズ組の音の使い方は、いつもサウンド・アートの先端を一歩越えるようなところがあり、たとえば、『アダプテーション』の評ですでに指摘したメリル・ストリープがクリス・クーパーと電話でハーモニーをつくりあう「サウンドパフォーマンス」でも歴然としている。「脳内ニューヨーク」の音こそ、「synecdoche」的な「襞」になっている。
◆アデルの作品は、彼女自身、凸レンズのついたメガネを使って描くが、彼女の個展の会場では、観客にメガネを配り、観客はそれで微小サイズの絵を見る。これって、すでに誰かがやっているような気がするが、美術展というものを馬鹿にして(美術展などに行くくらいなら、美味い料理でも食べる方がまし)行かないわたしは知らない。もしまだ誰もやっていなければ、そのうち、日本で真似するやからが出てくるだろう。日本の「美術家」の多くは、「創造」するより「アレンジする」ことに汲々としているから。そういえば、映画が始じまるまえに試写室で読んでいた織田作之助の「二流文学論」(『六白金星・可能性の文学』岩波文庫)に、「『よさ』という言葉が漠然と意味しているもっともらしいものを、手っ取り早く掴むという文化的修学旅行のために、団体切符を買うのが、この国の文化人であった」とあった。
(アスミック・エース試写室)
2009-08-25
●わたし出すわ (Watashi dasuwa/2009/Morita Yoshimitsu)(森田芳光)

 ◆タイトルを初めて見たとき、『カムイ外伝』で体を張った演技をした小雪が主演するのだから、今度は「体を出すわ」という作品なのかと思った。が、『おっぱいバレー』で綾瀬はるかが何も出さなかったように、もっとしとやかなイメージの強い小雪が出すはずはないとも思った。要するにタイトルが思わせぶりだなあと思ったのである。だが、この「出す」は金を出すという意味であった。とにかく、金が必要ということがわかる相手に大金をポーンとくれてやるのである。そういうストーリーを設定した「実験的」な操作は面白いが、その効果は必ずしも映画的に面白いとはいえなかった。
◆タイトルを初めて見たとき、『カムイ外伝』で体を張った演技をした小雪が主演するのだから、今度は「体を出すわ」という作品なのかと思った。が、『おっぱいバレー』で綾瀬はるかが何も出さなかったように、もっとしとやかなイメージの強い小雪が出すはずはないとも思った。要するにタイトルが思わせぶりだなあと思ったのである。だが、この「出す」は金を出すという意味であった。とにかく、金が必要ということがわかる相手に大金をポーンとくれてやるのである。そういうストーリーを設定した「実験的」な操作は面白いが、その効果は必ずしも映画的に面白いとはいえなかった。◆冒頭に、ジョン・ウェスレーの「キリスト者の完全」から、「できるだけ得て、できるだけ蓄え、できるだけ与えるならば、得れば得るほど恵みにおいて成長し、より多くの宝を天に積むことになる」(この引用文は、ネットからの盗用で、映画のなかと同じではない)という言葉が引用される。しかし、この映画の主人公・山吹麻耶(小雪)は、「獲得」/「蓄積」/「付与」という三重構造のうちの「付与」ないしは「贈与」という側面を見せるだけで、彼女が人に無造作に与える大金をどのようにして「獲得」し、「蓄積」したかは明らかではない。まあ、それを想像するのがこの映画の楽しみではあるが、それを追求してもあまり得にならないような気にさせるとことがこの映画の限界かもしれない。
◆企業情報にやたら詳しく、株の相場にも敏感なところをみると、麻耶は、株の操作などで莫大な金を蓄えたのだろうという想像は成り立つ。しかし、小雪が演じているせいか、彼女がいきなり故郷函館のクラスメートたちのところにあらわれて、金に困っているというより、金があれば・・・が出来るなと思っているような相手に「わたし出すわ」と金を与えるのが、あまりリアリティがないのだ。頭では、金が動いたということがわかっても、また、その金が予期せざる出来事を生んだりする意外性を面白いと思いはしても、何かスリルがない。
◆麻耶が故郷の函館にやってきた理由の一つは、病院で頭にBMI(ブレイン・マシーン・インターフェイス)のようなものを装着して眠っている母親を見舞うためらしいのだが、そのことと彼女が無償で金をばらまくこととの関係がよくわからない。母親は、植物人間みたいな状態だが、ときどき、BMIの耳のあたりのLEDがかすか緑色に点滅し、かすかな反応を示す。金はいくらでもあるという設定の麻耶のことだから、母親の病気を治すためには無尽蔵の金をつぎ込んでいるのだろう。それを示唆するのが、このBMIという高価な装置なのかもしれないが、母親の意識が一向に戻りそうにないということは、いくら金を積んでも金では買えないものがあると言いたいのか? 最後の母親の状態に奇跡的な変化が訪れるが、それは、金とは無関係のようだ。
◆かつて、堀江貴文は、「金で買えないものはない」と言って、文字通りの総スカンを食い、社会的生命を奪われてしまった。だが、資本主義の世界では、原理的に、金で買えないものはないのである。買えないものが「ある」としても、それは、まだ「商品」として認知されてい「ない」という意味であって、すべてのものが金に換算できる、つまりすべてのものを「商品」予備軍と考えるのが資本主義というシステムなのである。このあたりの問題との関連では、この映画は、資本主義以前の段階で低迷している。
◆金を持ちつけない人が大金を持ったときの典型的な反応を何人かの登場人物がコミカルに見せる。麻耶とかつてはクラスで美女度のライバルだった魚住サキ(黒谷友香)がその典型だが、特に面白いわけではない。演技としては、市電の運転手の井坂俊哉も、専業主婦の小池栄子も、マラソンランナーの山中崇も、魚学者(?)の小澤征悦も、みな手堅い演技を見せるのだが、とにかくドラマに奥行きがないので、全力投球できない感じ。しかし、一番気の毒なのは、何の役をやらされているのかわけのわからない仲村トオルである。予告編で彼が、「お金は有効に使いましょうね」と言うシーンが使われているが、彼がこの映画で演じることはこれに尽きているのである。仲村を出しながら、もったいないとは思いません? 俳優は有効に使いましょうね。
(アスミック・エース試写室)
2009-08-24
●母なる証明 (Madeo/Mother/2009/Joon-ho Bong)(ポン・ジュノ)

 ◆冒頭、すすき野のなかを歩いていたキム・ヘジャが、こちらを見ながら踊りのような仕草をくりかえすシーンが映る。最初から謎めいている。タイトルが出て、彼女は家のなかで葦のようなもの(漢方の材料か?)をカッターで切っているが、その音がどぎつく録音されている。家の外は通りで、息子とおぼしき青年(ウォンビン)の姿が見える。が、次の瞬間、彼は画面には見えないところから疾走してきた車に撥ね飛ばされる。次々にハッとさせるシーンが続く。予告では、犯罪に巻き込まれた息子のために母親が独力で犯人を捜す・・・という話だということになっているが、そう簡単な話ではない。
◆冒頭、すすき野のなかを歩いていたキム・ヘジャが、こちらを見ながら踊りのような仕草をくりかえすシーンが映る。最初から謎めいている。タイトルが出て、彼女は家のなかで葦のようなもの(漢方の材料か?)をカッターで切っているが、その音がどぎつく録音されている。家の外は通りで、息子とおぼしき青年(ウォンビン)の姿が見える。が、次の瞬間、彼は画面には見えないところから疾走してきた車に撥ね飛ばされる。次々にハッとさせるシーンが続く。予告では、犯罪に巻き込まれた息子のために母親が独力で犯人を捜す・・・という話だということになっているが、そう簡単な話ではない。◆配られたチラシに、詳細を紹介しないように書いてあるので、書きにくいのだが、「子供の心を持ったまま純粋無垢に育った"小鹿のような目をした"青年」は、明らかに、「幼児退行」に陥っており、家では、母と川の字になって「寝る」。「母と寝た」と言って、馬鹿にされたりもする。
◆ある種のミステリー、サスペンス的な要素もある。が、基本は、特殊な母子関係の物語であるし、母親と息子とのあいだに横たわる猛烈な因縁のようなものを強烈な形で映像化している。
◆キム・ヘジャは、1941年10月生まれだというから、今年68歳になるわけだが、貧しい暮らしの母親というイメージの端々から、強烈な色気がただよう。冒頭の「ダンス」の手振りもそうだが、特技とする(という設定の)鍼をつまむ指の仕草、そして最後のシーンで、まわりがハイテンションで盛り上がっている観光バスの座席の片隅で、ぼんやりと座り、いきなりスカートをめくりあげて腿を露出させ、腿の急所に鍼を刺そうとするシーン、年令を越えたエロティシズムがある。
◆この映画は、「母親と息子」といった「と」を描こうとはしていない。母がどんどんエスカレートしていくのにぴったりと寄り添う形で描く。息子も、母との関係が無縁であるわけはないのだが、終始、彼の世界も「自閉的」である。そもそも、この映画の登場人物は、すべて「自閉的」で、いいかげんな「協調」はしない。実は、これこそが、コミュニケーションの基本である。人は、コミュニケーションとは、共通項を持つことであったり、何かを「共有」することだと思っている。が、実際には、人は、他者との関係(つまりコミュニケーション)において、何も「共有」しはしないのだ。みな、その定めにしたがって「直進」し、そのどこかで絡み合いやぶつかり合いが出来、それを「理解」とか「誤解」とか言うのである。
◆この映画では、息子が突き進む「線」(ロジックと言ってもいい、以下同)、母親の「線」、息子が犯人だということになる事件を追う刑事(ユン・ジェムン)たちの「線」は、それぞれに完結しているが、それぞれに違う。われわれは、そのズレに立ち会わされ、人間の複雑さ、単純さに驚くのである。
◆この映画の舞台は、「とある静かな町」で、都心ではないが、この映画が描く登場人物たちの思いや感情は、ありきたりの都市映画が描く「病理」を飛び越え、21世紀的な「病理」を抉り出しているようなところがある。かつてのブーム以後の韓国映画は、そういう面で、他国の映画を凌駕しているとわたしは思うが、それは、韓国の社会がいまかかえている問題とも無関係ではない。
◆殺された娘の友だちで、ケータイを改造するのが得意という女の子が登場する。彼女は、ケータイを改造して、電話がかかると、「ウンコ」のおもちゃのついた棒が回るようにしている。ケータイの改造というのはなかなか難しいのだが、アイデアとしては面白い。
◆機械的な描写が繊細で、母の友人で写真屋をしている女性(チェン・ミソン)は、客の依頼で写真の修整をやる。Photoshop的なツールを使って傷を消したりする過程を、誇張もごまかし(省略)もなく描く。こんなところにも、この映画の基本姿勢が見える。
◆出獄した息子が大きな豆腐を食べるシーンは、ほかの韓国映画にもあった。すぐに思い出すのは、『オアシス』のなかのシーンである。
(映画美学校第1試写室)
2009-08-21
●パイレーツ・ロック (The Boat That Rocked/2009/Richard Curtis)(リチャード・カーティス)

 ◆この映画が公開されたニュースを聞いて、ピンと来た。この映画に登場する海賊放送局・船「ラジオ・ロック」のモデルは、1964年から1968年までイギリスの公海上の船から海賊放送をやった「ラジオ・キャロライン」である。公会では電波を規制する国内法が通用しないから、不法局の烙印を押されずに自由な放送ができるわけだ。海賊放送と自由ラジオの文脈でこの局が果たしたインパクトについて、わたしはかつて『これが「自由ラジオ」だ』(晶文社、1983年刊)などで触れたことがあるが、いまでは、すばらしい文献がある。原崎恵三氏の『海賊放送の遺産』(近代文藝社、1995年刊)である。ここには、この映画でも描かれている、イギリス政府とキャロラインとの攻防が詳細に書かれており、この映画で海賊放送に関心を持った人は、是非読んでほしい貴重な本である。
◆この映画が公開されたニュースを聞いて、ピンと来た。この映画に登場する海賊放送局・船「ラジオ・ロック」のモデルは、1964年から1968年までイギリスの公海上の船から海賊放送をやった「ラジオ・キャロライン」である。公会では電波を規制する国内法が通用しないから、不法局の烙印を押されずに自由な放送ができるわけだ。海賊放送と自由ラジオの文脈でこの局が果たしたインパクトについて、わたしはかつて『これが「自由ラジオ」だ』(晶文社、1983年刊)などで触れたことがあるが、いまでは、すばらしい文献がある。原崎恵三氏の『海賊放送の遺産』(近代文藝社、1995年刊)である。ここには、この映画でも描かれている、イギリス政府とキャロラインとの攻防が詳細に書かれており、この映画で海賊放送に関心を持った人は、是非読んでほしい貴重な本である。◆国内法では不法でも、公海上では合法という抜け穴を逆手に取った「ラジオ・キャロライン」は、実のところ、この映画が誇張するような史上初の海賊放送局ではなく、デンマーク沿岸に船を浮かべて電波を出した「ラジオ・メルキュール」や、スウェーデン沿岸の「ラジオ・シュド」(1959年開局)、同じくスウェーデンの「ラジオ・ノルド」(1961年開局)など、北欧勢の蓄積があり、その流れのなかで登場したのだった。
◆いずれの場合も、中波の長いアンテナを積めるだけの大きさの船が必要なわけだから、アマチュアの個人がやる海賊放送とは違う。ちゃんとしたスポンサーがいて、目的意識を持って開局されたのだった。つまり商業目的だ。当時、イギリスでは、放送はBBCの独占状態にあり、他方で浮上してきたポップカルチャー(リバプールサウンドなどもその一つ)に対応することはできなかった。ポップなものよりも、「格調高いもの」た尊ばれたのである。BBCには、ポプラーミュージックの時間が1日たったの45分間しかなかいという状況にしびれを切らしたレコード会社は、海賊放送で新しいサウンドを流すことを考えた。それは、むろん、政府にとっては容認せざることなので、この映画が描くようなさまざまな弾圧が加えられることになる。まずは、海賊放送局の広告収入を絶つという戦略から、企業の広告規制を強化した。次は、公海上で自由に電波を出せることを禁じる「海上犯罪法」を作ることである。これには、周辺各国の合意が必要なので、成立まで手間取ることになる。映画は、「ラジオ・ロック」が、1966年に開局し、1967年に「海上犯罪法」が成立して、放送ができなくなるまでを描く。
◆「ラジオ・ロック」には、「ラジオ・キャロライン」だけでなく、いくつかの海賊放送局のエピソードが複雑に織り込まれているが、登場人物には、みな、思い当たる実在の人物がいる。アメリカ人のDJ、ザ・カウント(フィリップ・シーモア・ホフマン)は、実際にキャロラインに関わったアメリカ人DJのジョニー・ウォーカーとエンペラー・ロスコとを混ぜ合わせているように見える。イギリスで超有名だったということになっていて、あとから帰国し、キャロラインに加わるDJ、ギャヴィン(リス・エヴァンス)のモデルは、ケニー・エヴェレットかな? 誰かと結婚すれば船に乗りギャビンといっしょにいられるというので、純朴なDJサイモンをだまして偽装結婚をくわだてるエレノア(ジャニューアリー・ジョーンズ)という女が登場するが、このキャビンのモデルは、トニー・ブラックバーンらしい。いや、知ったかぶりはやめよう。いずれにしても、この映画の登場人物たちは、さまざまな実在の人物を重層的に混ぜ合わせていると言った方が正確だろう。とにかく、さまざまなDJスタイルを目の当たりにできるのが楽しい。
◆大臣ドルマンディ(ケネス・ブラナー)とその部下のトゥワット(ジャック・ダベンポート)とがあの手この手で責めてくるのに対抗するラジオ・キャロラインを仕切るのは、ビル・ナイが実に魅力的にカッコよく演じるクエンティだが、このモデルは、ローナン・オライリー (Ronan O'Rahilly)である。ただし、オライリは、やり手ではあったが、ラジオ・キャロラインのころはまだ20代で、ドルマンディのような初老の男ではなかった。おそらく、ラジオ・キャロラインの活動は、若さのパワーとひらめきによって支えれれていたのだろう。外部には彼らの活動をささえる年配者がいたとしても、船内にクエンティンのような人物はいなかったはずだ。が、この映画は、単にラジオ活動だけを描くのではなく、ある種の「アジール」的な解放空間を描こうとしている。そこには、若い人間だけではなく、若い人物の父親的な人物も必要だし、恋人や母親の存在も必要になる。
◆そのへんの要求を一手に引き受けているのが、カール(トム・スターリッジ)である。そもそも、この映画は、彼が母親(エマ・トンプソン)の手引きで「ラジオ・ロック」の船に乗り込むところから始まる。彼には父親がいない。その父探しのドラマもこの映画のもう一つの線である。
◆最初からいるアメリカ人のDJ、ザ・カウントに対して、イギリスで超有名だったということになっているDJ、ギャヴィン(リス・エヴァンス)がアメリカから帰国し、キャロラインのメンバーに加わると、二人の仲は悪化し、やがて子供じみた勇気試しをすることになる。甲板に高くそびえるアンテナのてっぺんによじ登り、海上に飛び降りるのである。このエピソードは、昔、わたしが自由ラジオの方法を模索していたときにベルリンの書店で見つけて買ったえらく長いタイトルの本("Was Sie schon immer über Freie Radios wissen wolten, aber nie zu fragen wagten!")のなかで読んだことがあった。それは、二人で競争したのではなく、あるDJが、いかさまではないことを証明するために塔に登ったという話だった。
◆ここで描かれるのは、ある種の「集団的共同作業」や「連帯」といった60年代的なノスタルジアである。60年代が美化される昨今だが、むろん、60年代がそういう夢の集団性ばかりが支配的だったわけではない。それは、いつの時代にもあるが、60年代は、いまとくらべれば、身体的暴力やセックスのような見えやすい形での自己/他者関係がある程度持続していたということができる。いま、それは、不可視的でヴァーチャルなものになったことは確かで、その分、「孤立」の雰囲気が強いのかもしれない。セックスしたからといって他人との交流が深まったことにはならず(それは昔も同じだったはずだが)、だからそういうフィジカルか関係を避けてしまう。だから、この映画の世界は、そのままではいまの時代に「応用」することはできないのであり、「それっ!海賊放送をやろう!」という感じにはならないのだ。
◆先日、『VOL lexicon』というオールタナティヴ活動のマニュアルのような本が出ているのを本屋で見かけ、ぱらぱらとページをめくったら、「海賊放送」への言及があるのに、ウィキペディアに書いてあるような海外の話ばかりが書かれていて、日本の自由ラジオやミニFMのことには全く触れられていないのだった。日本では、昔から、オールタナティヴを考える者は、「西欧礼賛」をくりかえしてきた。だから、わたしなどは、どうせ「西欧礼賛」なら、その最も先端的なものを「密輸」しようとしてきたのだったが、最近は、向こうにも「密輸」するものが乏しくなったこともあって(というより、インターネットなどの発達で、情報だけは、グローバルになった)、そういう仕事に精を出す人間は少ない。だから、海外のオールタナティヴの先端はさっぱり入ってこない。わたしがこれまで深く関わってきたラジオに関していえば、もう「海賊放送」の時代ではないし、自由ラジオの時代でもない。必要なのは、もっとミクロなレベルに感応するラジオであり、それが、ラジオアートというジャンルでの試みだ。だが、そんなことは、日本ではほとんど関心を持たれてはいない。
◆日本で思い出したが、かの糸井五郎は、1971年にまだオランダ沖で生き残っていた海賊放送船「メボII世号」に乗船し、彼自身も放送をしたのは有名な話だ(『僕のDJグラフィティ』、1985、第三文明社)。
◆この映画では、法による締め付けで追いつめられると同時に、海難事故に遭うという設定になっている。実際のキャロラインは、すぐに2隻で放送するようになっていたが、その一隻の「ラジオ・キャロライン・ノース」は、実際に壊れ、解体された。しかし、この映画では、事故シーンが、まるでタイタニック状態に描かれ、バランスが悪い。こんなに「ドラマチック」に事故を描く必要はないし、そのために、全体が嘘臭くなってしまう。そもそも、船内に水があふれているのに、送信機の電源が健在で、放送を続けているというのは、あまりに空想的だ。が、しかし、この映画は権力の不当な圧力をかわす感性が横溢している点で、元気が出る。
(東宝東和試写室)
2009-08-20
●リミッツ・オブ・コントロール (The Limits of Control/2009/Jim Jarmusch)(ジム・ジャームシュ)

 ◆アルチュール・ランボーの「酔いどれ船」(Le Bateau ivre)の冒頭からの引用で始まる。これも、何かジャームッシュの冗談のような響きがある。
◆アルチュール・ランボーの「酔いどれ船」(Le Bateau ivre)の冒頭からの引用で始まる。これも、何かジャームッシュの冗談のような響きがある。Comme je descendais des Fleuves impassibles,◆主役の「孤独な男」(イザック・ド・バンコレ)は、カッコつけてはいるが、下半身が貧弱で、どっかバランスが崩れている。映画のなかの「タフガイ」を演じているが、抜けている感じにしているのが、ジャームッシュのユーモア。
Je ne me sentis plus guidé par les haleurs :
Des Peaux-Rouges criards les avaient pris pour cibles
Les ayant cloués nus aux poteaux de couleurs.
◆彼の視覚に映る世界は、映画のなかか、夢想の世界で、それを示唆するために、そういうシーンは、わずかにスローに見えるハイスピードで撮られている。
◆クラブで見せるフラメンコ・ダンサー(La Truco)の手の動きと、「孤独な男」の太極拳の手の動きとのあいだに若干共通性が感じられる。
◆ジャームッシュの映画の登場人物らしく、主役の「孤独な男」(イザック・ド・バンコレ)は、いくつかのイデオシンクラシー(わたしの好きな語だが、翻訳不能――ここでは「こだわり」と訳してもいい)がある。一つは、エスプレッソを必ず2杯一緒に注文すること(ウエイターが誤解して「ダブルエスプレッソ」を持って来たりすると、えらく怒り、「two espresos in separate cups」と力説する)、太極拳、朝食は洋ナシだけなどなど。
◆「ギター」(ジョン・ハート)が苦々しく言う「人生は何の価値もない」(La vida non vale nada)という言葉は何度も出てくるが、通りがかるバンの後ろにもその文字が見える。
◆「孤独な男」に連絡を持って来る男「ギター」(ジョン・ハート)は、祖父はボヘミアの出身だが、「ボヘミアン」とは関係がないと言っていたと言い、「ボヘミアン」とアーティストとの関係はいつ始まったのだろうと言いながら、フィンランドの映画にいいのがあったといったことを語る。言うまでもなく、これは、アキ・カウリスマキの「ラヴィ・ド・ボエーム」のことである。最後にデユーク・エイセス「雪の降る町を」が流れるやつ。
◆マシンガンで重装備したガードに囲まれた「要塞」が映り、次の瞬間、「孤独な男」は、そのなかの「自分だけが偉大だと思っている」「アメリカ人」(ビル・マーレイ)の部屋にいる。驚く「アメリカ人」が「どうやって入ったんだ」と訊くと、「想像力でさ」と答える。ガードマンとの格闘シーンも、鍵をはずすスリリングなシーンを全く見せないこの完全犯罪的な映画作法がしゃれている。ジャームッシュは、「アクションなきアクション」を撮りたかったという。
◆「ブロンド」(ティルダ・スウィントン)が言う。「The best films are like dreams you're never really sure you had. 」
◆「孤独な男」は、ピカソの「ゲルニカ」でも有名な Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía が好きらしい。この美術館の作品のまえで時間を過ごすシーンがまえの方と終わりの方にあるが、見える作品は、フアン・グリス(Juan Gris)の「El Violín」、ロベルト・フェルナンデス・バルブエナ(Roberto Fernández Balbuena)の「Desnudo」、アントニオ・ロペス・ガルシア(Antonio López García)の「Madrid Desde Capitàn」などであり、最後に出てくるのキャンバスに布を貼り付けたような作品は、アントニ・タピエス(Antoni Tàpies)の「Gran Sábana」である。この作品は、「人生は何の価値もない」という言葉に対応していることは明らかだが、同時に、それは、「人生はいくらでも色付けできる」という意味でもあり、この映画の各シーンの「意味」を示唆してもいる。
(映画美学校試写室)
2009-08-18
●ホッタラケの島 遥と魔法の鏡 (Hottarake no Shima/Oblivion Island Haruka and the magic mirror/2009/Sato Shinsuke)(佐藤信介)

 ◆人間が「ほったらかした」物を集めて運び、保存する狐とも「妖精」ともつかぬ生き物がいて、ふとしたことから一人の女子高生・遥(声:綾瀬はるか)が彼らの「島」に迷い込む発見と冒険の物語。人間が物を大切にしないといった口ぶりだったので、「リサイクル」や「自然を守れ」路線の映画かと思ったら、そういうのでもなく、けっこう面白かった。タイトルや予告篇から感じられる軽さ(軽薄さ)はなく、なかなかの力作。海外でも売れそう。
◆人間が「ほったらかした」物を集めて運び、保存する狐とも「妖精」ともつかぬ生き物がいて、ふとしたことから一人の女子高生・遥(声:綾瀬はるか)が彼らの「島」に迷い込む発見と冒険の物語。人間が物を大切にしないといった口ぶりだったので、「リサイクル」や「自然を守れ」路線の映画かと思ったら、そういうのでもなく、けっこう面白かった。タイトルや予告篇から感じられる軽さ(軽薄さ)はなく、なかなかの力作。海外でも売れそう。◆ただし、狐(?)の世界に迷い込んでしまい、見破られそうになって逃げまくるといったアクションにかなりウエイトを置いているので、最終的にどう収めるのかと思っていたら、最後には、ちゃんと、それまでないがしろにしてきた父親(声"大森南朋)の愛を理解するところへ収める。死んだ母への思慕が強く、男手ひとつで遥を育ててきた父にはずっとそっけなかった遥だったのだが。
◆遥は、女子高生っぽい格好をしているが、各シーンで短いスカートから露出する腿をさりげなく見せる演出で気を引く。
◆いま日本でも、シングル・ペアレント・ファミリーが少しづつ増えているから、こういう作品は受けるだろう。アメリカから始まったシングル・ペアレント現象は、いまや世界化しているが、この調子で行くと、核家族の時代は終わるし、それにともなって、家族/国家の関係も崩れるから、国家の形態そのものが変わっていくはずである。
(東宝試写室)
2009-08-17
●20世紀少年―最終章―ぼくらの旗 (20seiki-shonen--saishusho--bokurano hata/2009/Tsutsumi Yukihiko)(堤幸彦)

 ◆原作との比較をしたわけではないので、原作の方はわからないが、少なくとも映画版はどれも、わたしには「古すぎる」という印象を真っ先に受けた。「21世紀」ではなくて「20世紀」なのだから当然かもしれないが、もし「20世紀」にこだわるのなら、そのアプローチはノスタルジアにすぎないと思うのだ。折りしも、「1968年」への関心が高まっている。というより、いまや還暦を迎えた「団塊世代」が若き日へのノスタルジアを形にするのが流行りである。それに便乗するかのように、もっと若い世代も「1968年」や全共闘時代にロマンティックなイメージをあたえるようなことをやっている。この映画は、まさにそんな状況にぴったりの映画だ。
◆原作との比較をしたわけではないので、原作の方はわからないが、少なくとも映画版はどれも、わたしには「古すぎる」という印象を真っ先に受けた。「21世紀」ではなくて「20世紀」なのだから当然かもしれないが、もし「20世紀」にこだわるのなら、そのアプローチはノスタルジアにすぎないと思うのだ。折りしも、「1968年」への関心が高まっている。というより、いまや還暦を迎えた「団塊世代」が若き日へのノスタルジアを形にするのが流行りである。それに便乗するかのように、もっと若い世代も「1968年」や全共闘時代にロマンティックなイメージをあたえるようなことをやっている。この映画は、まさにそんな状況にぴったりの映画だ。◆まず、集団志向である。それはこの映画の山場を見れば一目瞭然である。次に、理屈が多すぎる。もっと映像で見せてくれと言いたくなる。「地球を救う」とか「人類を破滅させる」とかやたら大風呂敷。もっと小銭で勝負できないのか? もう権力は、地球とか国家とかのレベルでそのコントロール機能を発揮してはいない。むろん、世界や国家を動かすことにはいささかも興味を失ってはいないが、その手口がもっとミクロで目立たないレベルでしかわからないようなやり方になっている。
◆この映画の要に、小学校時代の経験が大人になっても尾を引くという発想がある。トラウマ理論とも通じる発想だが、これはそろそろ反省の余地がある。そういう形で大人が自分で自覚すべきことをその幼児・少年体験に還元し、現在から逃避する方法としてトラウマ理論は便利この上ない。この映画で、小学生のときに仲間はずれにされたというルサンチマンがその人物の世界の支配と破壊の権力意志を生む。しかし、これは、かつてヒトラーに押し当てられた古い、古い理論だ。ヒトラーは、非常にあつかいやすい範例だったが、いまでは、ヒトラーの「暴虐」も、もっと構造的なものとして見られなかればならないことがわかっている。「ヒトラー」の名のもとにさまざまな人間と組織が動いた結果なのであり、「狂気」の「独裁者」の思うがままに操られていたわけではない。
◆海賊ラジオ局が出てくるが、その雰囲気は、『バニシング・ポイント』なんかを思い出させる古さで、リアリティがない。
◆あまりくさしてばかりいては、見た意味がないから、わたしが一番印象に残ったのは、唐沢寿明のボーカルだったと言っておく。
◆「最後の10分で、すべてがわかります」と企画・脚本の長崎尚志が言うその10分間は、試写では見せてもらえなかった。
(東宝試写室)
2009-08-12
●あの日、欲望の大地で(The Burning Plain/2008/Guillermo Arriaga)(ギジェルモ・アリアガ)

 ◆母娘関係にあるという設定のキム・ベイシンガーとシャリーズ・セロンとのあいだには体質的な類似性があるが、シルビアと名を変えているセロンの娘時代(当時の名はマリアーナ)を演じるジェニファー・ローレンスとセロンとのあいだには体質的にかなりの断絶がある。同様に、若き日のサンティアゴを演じるJ・D・パルドと中年の彼を演じるダニー・ピノとのあいだには全く類似性が感じられない。わざとわからなくしているわけではないところに、この作品のスキが見えてしまう。
◆母娘関係にあるという設定のキム・ベイシンガーとシャリーズ・セロンとのあいだには体質的な類似性があるが、シルビアと名を変えているセロンの娘時代(当時の名はマリアーナ)を演じるジェニファー・ローレンスとセロンとのあいだには体質的にかなりの断絶がある。同様に、若き日のサンティアゴを演じるJ・D・パルドと中年の彼を演じるダニー・ピノとのあいだには全く類似性が感じられない。わざとわからなくしているわけではないところに、この作品のスキが見えてしまう。◆記憶を交錯させながら描いているこの映画の流れを無粋に整理してみると――かつて、母親のジーナ(キムベイシンガー)が近所(メキシコの国境沿いのニューメキシコ)のメキシコ人、ニック(ヨアヒム・デ・アルメイダ)と浮気しているのを敵意の目で見ている娘、マリアーナ(ジェニファー・ローレンス)がいる。娘心の敵意と偶然が重なったある行為によって、ジーナとニックは死ぬ。その死は、世間では心中とみなされたらしい。いずれにしても、ニックの残された妻は、夫を殺した女としてジーナを憎む。ジーナの夫(ブレット・カレン)も、ニックを憎んでいる。そこにありがちな皮肉が起こる。ニックの遺児のサンディアゴ(J・D・パルド)をマリアーナが愛してしまうのだ。彼女の父親(ブレット・カレン)は怒り、二人はメキシコに駆け落ちをする。その後、彼女はサンディアゴの子を身ごもるが、幼いときに夫と子供を捨てて、名前をシルビアと変えて、アメリカにもどったらしい。映画の現在は、中年になったシルビアが、ポートランドのレストランのマネージャーとして暮らしているという設定である。
◆シルビアは、やり手のマネージャーで、客の受けもいいが、自分を痛みつけるかのようにすぐに男と寝、自傷行為にも及ぶ。10代の経験と記憶、子供を捨てたことがトラウマになっているというわけだ。トラウマというのは、それを持っている側からすれば他人から加えられた被害だが、外から見ると、甘えである。自分のやったことに責任が持てないのを、他人や偶然事のせいにすることである。しかし、責任が持てない、責任を遂行できないというのは、弱さではあるが、人は誰でもが強いわけではない。逆に、強さというのは、非人間性のあらわれでもあり、「強き者」がヒーローにあがめ立てられるに劣らず、「弱き者」はそれだけ人を惹きつけたりもする。悪循環だが、そのために、無責任な者は、問題をどんどん増やして行き、自分でも自己嫌悪に陥る。自傷行為は、そういう自分を罰する行為であり、準自殺的な行為なのだ。無責任人間は、実際には決して、植木等的な「スーダラ」人生を送ることは出来ないのであり、内に内に自責の念をつのらせていく。シルビアはまさにそんな女であり、それを乗り越えるドラマがこの映画で描かれる。一つのきっかけは、彼女が捨てた子供との再会である。彼の元夫のサンディアゴ(ダニー・ピノ)は、種の散布の仕事をしているが、操縦する飛行機が墜落して、重症を負う。そして、友人のカルロス(ホセ・マリア・ヤスピク)に、娘の母親を探してほしいと頼む。カルロスは、ポートランドに住み、シルビアと名を変えている彼女を探し出す。
◆ここにはいくつかの「家庭の危機」のパターンが描かれている。まず、ジーナは、セックス関係がうまくいかなくなった夫を離れて、ニックに近づく。これはよくありがちのパターン。そういう状態を見て育った娘マリアンーナは、母と同じようにメキシコ人の男(しかもニックの息子)を愛するが、持続しない。なぜ彼女が彼と子供を捨てたのかは描かれないが、不安定な夫婦関係を見て育った子供が、安定した夫婦関係を持てないというのも、一つのパターンである。いつもそうだとはかぎらないが、そういうパターンは、なんとなく納得させる面を持つからだ。もう一つのパターンは、子供と親(とりわけ母親と子供)との関係の分かち難さというパターンである。この点で、この映画は、もう一つのパターンを描くことを忘れていない。それは、浮気の最中に、火につつまれてあっさり死んでしまうジーナとニックである。彼らは、基本的に、自分のやっていることに悩んだり、自分をいじめたりはしないタイプなのではないかと思う。浮気した結果、彼女と彼の家族がどういう影響を受けるかはほとんど考えず、自分たちの閉ざされた世界に閉じこもり、そのまま昇天してしまうわけだから。
◆こう見てくると、この映画は、責任のパターンの映画であるとも言える。無責任の親がいる。責任と無責任とのあいだを揺れ動く娘・女がいる。では、どのようにして、シルビアは、責任意識に目覚め、責任を果たすのか? それを、テッサ・イアが見事に演じる子供マリアに収斂させるのは、一つのパターンなのだが、親が子供に対して責任を取らざるを得ないのは、親子が血を分けた関係にあるからであるよりも、たとえばこの映画で父親が重症を負い、男手一つで育てた娘を庇護する者がいなくなったとき、その母親しか、扶養義務を負う者はいないからである。
◆親子関係を血縁関係としてではなく、国家組織が個々人に押し付けている制度的な枠組みのなかで不可抗力的に生じる関係として見た方がいいとわたしは思う。近代国家とは、親子関係を血縁という観念のもとで縛りつける制度であり、あたかも血のつながりが最も密度の高い関係であるかのように思い込ませる制度である。だから、この映画でもそうだし、『クリーン』でもそうだったが、<親子の愛情は否定しがたい>から、親が子供を庇護したり、逆に子供が親のめんどうをみたりするのではなく、そういう制度のなかに埋め込まれているから、それしかないという風に考えた方がいいのだと思う。そして、もしそうだとすれば、「いたしかたなく」面倒をみる関係のなかに、どの程度近代国家的な親子関係を越えるものがあらわれているかどうかを見ることが重要になる。が、この映画は、結局のところ、シルビアの「母性愛」のめざめのようなロジックに身をゆだねて終わっている。せっかくジャリーズ・セロンに屈折のあるキャラクターを演じさせておきながら、これではもったいない気がする。
(映画美学校第1試写室)
2009-08-11
●クリーン(Clean/2004/Olivier Assayas)(オリヴィエ・アサイヤス)

 ◆わたしは、この作品を随分まえに見ている。一見してマギー・チャンの魅力に惚れた。それまでのマギーとは別の側面をこういう形で出すとは思わなかった。義理の父親役のニック・ノルティもいい。この映画では誰もみせかけの演技をしていない。
◆わたしは、この作品を随分まえに見ている。一見してマギー・チャンの魅力に惚れた。それまでのマギーとは別の側面をこういう形で出すとは思わなかった。義理の父親役のニック・ノルティもいい。この映画では誰もみせかけの演技をしていない。◆日本では、いま、酒井法子の覚醒剤事件など、芸能人のドラッグ騒ぎに事欠かないが、その基本は、国家の法に触れたという犯罪としての問題に終始している。ドラッグは最初から「悪」だということになっていて、ドラッグを売ったり買ったりした者は、国法を犯したから即「悪人」ということになり、酒井なら酒井がドラッグについてどう考えているのかは全く伝わってこない。最初から「悪事」と決められているから、マスコミへの反応は謝罪か沈黙しかなく、なぜ自分がドラッグにはまったのかということの釈明をする機会は与えられない。
◆「日本では」と言ったが、D・C・A・ヒルマンの『麻薬の文化史』(森夏樹訳、青土社)によると、ヒルマンは、ギリシャ・ラテンの文学との関連で麻薬を博士論文のテーマにして、教授から猛反対を食ったという。彼は書いている――「西欧現代の地歩を築いた父祖たちた、正真正銘の麻薬使用者だった・・。現に彼らは麻薬を栽培し、それを売っていたし、とりわけ重要なのは彼らがそれを使用していたことだ。現代の麻薬撲滅運動でさえ古代人の目には、けっして民主的な運動として映らなかっただろう。古代社会は、・・・麻薬を使用した者を監獄へぶち込むことさえしなかっただろう。だいたい古典期の人々は節制を徳目のひとつなどにしていない。・・・そして、そんな麻薬を生活の一部として受け入れた世界から、芸術や文学、科学や哲学が飛び出てきたのである」。ただし、ヒルマンは、このことに加えて、つぎのことを指摘するのも忘れてはいない。すなわち、「古代における麻薬の需要や向精神薬の流行を理解するためには、2000年ほど前に営まれた、古代人の生活の厳しい現実を知ることが必要だろう」と。逆にいえば、いま、日本でドラッグ・ユーザー(その大半が社会のエリートたちばかりだとしても)が急増している背景には、社会的なストレスの亢進(毎年3万人を越える世界第二の自殺大国である)という問題が隠れており、それを緩和する政策が進められないかぎり、ドラッグ問題は一向に解決しはしないのだ。そして、そのストレス「緩和」が、密売組織を温存させることになる。
◆ドラッグの規制には、根本的な矛盾がある。それは、ドラッグの配布・使用が犯罪であるといっても、それは、傷害や窃盗や殺人が犯罪であるのとは、かなり異なる面を持っていることだ。これらの場合には、必ず「被害者」がいるが、ドラッグの場合の「被害者」は、多くの場合、可能的な「被害者」であって、その被害が特定されたことによって逮捕されるわけではなく、配布・使用・所持の事実によって犯罪とみなされるのである。ドラッグ犯罪の被害者は、ドラッグの使用者ではない。オーバードースで死に至ることもあるが、使用者も犯罪者とみなされるのだから、彼ないしは彼女はその「犯罪」の被害者ということにはならない。ある意味で、ドラッグ犯罪の被害者は、その家族や社会的な影響、国法を破った、世を騒がせたということによる世間の人々一般が可能的「被害者」となる。罰則というものは、まず被害者が特定されて初めて想定可能になるのべきだとすれば、「被害」の度合いにまず注目する必要があるが、ドラッグの場合には、それはほとんど顧慮されない。
◆エミリー(マギー・チャン)の夫のリー(ジャイムズ・ジョンストン)は、かつてはロックのスター的な存在だったが、スランプ状態に陥っている。周囲は、エミリーにその責任があるといった中傷を暗に流している。いつのころからか、二人は、ヘロインに耽溺していたが、ある晩リーは、エミリーにヘロインを買わせに行かせたあと、彼女に当たり、キツい言葉を吐く。車で飛び出したエミリーは、ドッグに車を停めて、ヘロインを打つ。他方、モーテルに残ったリーは、やけくそになって過剰な量のヘロインを打つ。このあたりはさりげなくしか描写されないが、翌朝モーテルにもどったエミリーは、警察がリーの死体を運び出す場面に直面する。
◆ここで、重要なのは、この映画が、ヘロインの使用を法律が罰するか否かとは関係なく、ドラッグによってもたらされてしまった被害者=夫リーに対してどのような責任をとるかというモラル問題を描いている点だ。映画のなかで、彼女は捕らえられ、やがて保釈で出る。が、彼女にとっての苦しみは、彼女がヘロインの使用という犯罪を犯したことではなくて、夫を死なせてしまったこと、子供から父親を奪ってしまったこというである。彼女が、その語の本来の意味での「forgiveness」(許し)をどう得るかがこの映画の一貫したテーマであり、それは、日本のタレントたちが、テレビや新聞のまえで「二度とこんなことはいたしません」と謝罪するようなこととは全くレベルが異なるのだ。
◆エミリーとリーには子供がいたが、二人は通常の意味でのよき「親」ではなかった。二人は彼を育てず、リーの両親アルブレヒト(ニック・ノルティ)とローズマリー(マーサ・ヘンリー)がその子のめんどうをみている。だが、ローズマリーはガンにかかり、アルブレヒトが彼女の面倒を見なければならなくなったこともあって、アルブレヒトは、子供を実の母親に返したいと思うようになり、エミリーと子供を再会させる努力を始める。
◆「forgiveness」には、相手からもらう「許し」という意味と同時に、相手に与える「寛容さ」という意味がある。ノルティが実にすばらしい演技を見せるアルブレヒトは、まさに「寛容」の人であり、世間では、夫を死に追いやった「悪妻」とみなされているエミリーにきわめて「理性的」な寛容さを見せる。危機のときこそ、必要なのは「理性的」な判断である。彼は、自分の息子のリーの弱さも知っている。だから、エミリーの苦労もわかる。その点、ローズマリーは、嫁に対して批判的であるが、それも次第に折れて行く。
◆感動的なシーンは、再会した息子とエミリーとの対話である。彼は、「あんたは、ぼくのパパを殺した人だ」と言う。それは、祖母のローズマリーの影響なのだが、それに対して、エミリーは諄々と(まさに「理性的に」)説明をする。「殺してはいない」という答えに、息子は究極の問いを問う、「じゃあ、どうしてドラッグをやったの?」これに対して、エミリーは言う、「ドラッグというのは、たいていの人が考えるよりもっと複雑なの」。彼女はドラッグが与えてくれるものを否定しない。が、「どうしてドラッグを必要とするかというと、つらいことがあり、ドラッグ以外には、ほかにどう生きたらいいかわからないからなのよ」。
◆この映画は、2004年の映画であり、ドラッグに関するいまの状況は少し変わってきているかもしれない。この映画は、ヴァンクーヴァーから始まり、ロンドン(エミリーとリーが仕事場としていた)とパリ(エミリーがしばらく滞在し、中国料理の店で働く)に場面が移るが、リーが死ぬのは、ヴァンクーヴァーである。ヴァンクーヴァーは、ドラッグでは悪名高い場所だ。一説によると、アヘン戦争の時代に中国に向けてアヘンが出荷された港がヴァンクーヴァーだったという。その名残かどうかは知らないが、ヴァンクーヴァーのチャイナタウンに近いへイスティング・ストリート(Hasting Street)は、路上でドラッグなら何でもありのところで、ジャンキーたちの悲惨な光景を目の当たりにすることもできる。こういう場所を見ると、ドラッグと組織犯罪との関係を考えないわけにはいかなくなり、冒頭で引用した古代ギリシャやラテンの社会でのドラッグ状況とは、全くコンテキストが違うと言わざるをえなくなる。結局、すべてが利潤獲得の素材になる近代化のなかで、ドラッグも組織的な利潤獲得の道具になり、その使用は、精神の解放や創造とは無縁の単なる超「美食」的な消費行為に成り下がるのである。
2009-08-10
●引き出しの中のラブレター (Hikidashinonakano Rabureta/2009/Sanjo Shinichi)(三城真一)

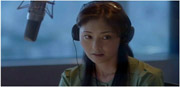 ◆わたしは、この映画に登場する日本人ほど「シャイ」で、思うことをストレートに言わない人々がいま一般的だとは思わない。が、その一方で、たしかにはっきり言いたくても言えない社会的・文化的・環境的条件は強まっており、だからこそ、敬語としては美しくともなんともない「・・させていただく」とかいうような卑屈にへりくだった表現ばかりが使われるのだろうという思いもある。
◆わたしは、この映画に登場する日本人ほど「シャイ」で、思うことをストレートに言わない人々がいま一般的だとは思わない。が、その一方で、たしかにはっきり言いたくても言えない社会的・文化的・環境的条件は強まっており、だからこそ、敬語としては美しくともなんともない「・・させていただく」とかいうような卑屈にへりくだった表現ばかりが使われるのだろうという思いもある。◆俯瞰で映される東京、高層のビルが立ち並び、通りにはシャレたブティックやカフェが立ち並ぶ。30年まえにくらべれば、「日本」の都市とは思えないほど「西欧化」した東京。しかし、そのなかに住む日本人は、30年まえとは比較にならないほど「壊れやすく」、人に言えない悩みや思いを心のなかに無理やりしまい込んで生きている。この映画が映す東京の気配は、そんなところだ。
◆実際にそうであるかどうかはどうでもいい。この映画は、そんな気配のなかで生きる個々人が、ラジオというメディアによって結ばれる「リモートラブ」のストーリーだからである。そう、リモートラブ(これはわたしの造語だが)。愛情を感じているのに、面と向かうと言い出せないし、表情や身ぶりとして表現できない――ケータイも、ネットも、そういう個々人を結びつける「リモートラブ」の小道具として機能し、普及しつつある。
◆この映画で、ラジオパーソナリティをつとめる真生(常盤貴子)は、編成会議に提案して、「心の中の引き出しにしまって」いる「大切な想い」を投書し、それを読み上げる番組を始める。反対もあったが、社長(伊東四朗)の賛成と命名(それが本作のタイトル)によって実現する。それによって、それまで途絶していた男と女、親と子などなどが再会を果たす。
◆常盤の番組が成功するのは、投稿者の名を明かさない、つまり匿名のメッセージを放送したからだった。本名を出さないという形式は、知っている人だけが知っている、当事者や自分だけが知っているという「共犯関係」を生み出す。全国放送でありながら、全国の人々を一まとめにしてしまうのではなく、点と点とを結ぶ。他のリスナーは、その点と点との熱い関係を想像することによって感動を深める。と同時に、自分もその匿名の個人に同化することもできる。それは、勝手な同化であり、自由な同化であって、強制されたものではない。
◆リーモートラブとは、ある一定の距離とへだたりを愛するコミュニケーションである。そもそも、日本や韓国の「おじぎ」は、そうした距離の文化に属する。ハグやキッスの文化とは大いに異なる。
◆この映画では、いく組みもの関係が最初、ばらばらに描かれる。いわゆる「グランドホテル方式」である。そこには、とりわけ親子の確執で疎遠になっている親子、親子の確執が影響して疎遠になっている恋人たちがいる。そうした関係の一方が、常盤のラジオ番組の呼びかけで、おずおずと手紙を書く。それは、自分と相手の名を明記した手紙ではないが、それを代読されたときには、誰が書いたのかが特定の人にだけはわかる。リモートではあるが、愛情を生むリモートさ。
◆かつて別れた妻への罪責感から心を閉ざしている漁師を演じる仲代達矢は、さすが別格の演技。本上まなみは、大人の女を破綻なく演じて印象深い。終わりそうでなかなか終わらないしまりのなさもあるが、この映画のテーマには、終わりがないのだから、それもいたしかたがないか? 途中で、この映画がJ-WAVEとのタイアップ映画であることがわかった。ならば、公開中、映画館とスタジオとがシームレスにつながってしまうようなイヴェントを組むのもいいかもしれない。
◆わたしも、大学で「距離の文化」の深さを日々感じている。意見を求めても答える者がほとんどいない――マイクを回せば体のいい答えはするが、本音は言わない――ので、あるときから、小さな紙に5分もあれば書ける短い感想を書いて出してもらうことにした。名前を書くので、最初は、口頭で言うのよりはやや本音に近いかなという程度の感想だったが、次の週に、ユニークだったり、苦情を言っているいるものを選んで、(名前を伏せて)感想の部分だけを書画カメラで大スクリーンに映して、公開することにした。すると、次の週から、面白いものや忌憚のない文句の感想がグンと増え始めた。おそらく、これが、実名入りだったらそうはならなかっただろう。匿名であること、しかし、本文はそのままであること、この「距離」が、疎遠ではなく、接近の効果を発揮するのだ。この映画の場合、「本文」を常盤が代読するため、そうした「距離」は、もう少し広がる。男の文章も、老婆の文章も、常盤が読むわけだから、その「距離」的抽象度は高まる。が、それは、そこで組み合わされている関係を疎遠にはしない。むしろ、そのオリジナルな関係だけではない、いわばその関係に「便乗」する新しい関係(カップリング)を生みもする。
(松竹試写室)
2009-08-07
●あなたは私の婿になる (The Proposal/2009/Anne Fletcher)(アン・フレッチャー)

 ◆ロマンティック・コメディの定型を踏む作品だが、せりふのうまさと気を引くプロットを積み上げ、ハートウォーミングな仕上がりになっている。
◆ロマンティック・コメディの定型を踏む作品だが、せりふのうまさと気を引くプロットを積み上げ、ハートウォーミングな仕上がりになっている。◆サンドラ・ブロックが演じる編集長マーガーレットは、(おそらくユダヤ系の)タフ・ウーマンで、『プラダを着た悪魔』でメリル・ストリープが演じた編集長を真似ているかのように仕事の成功と自分のことしか考えない嫌味な女だ。それが映画の導入部で描かれる。むろん、これは、ロマンティック・コメディのパターンで、それが段々くずれていくところが見せ場である。
◆アメリカでは、個人の持つパワーが絶大で、その点ではパワーのある者は仕事がしやすい。そういう仕組みのなかからはあのブッシュのような大変な不作も現れるので、危険と可能性とが同居している。が、そういうマーガレットにも弱点がある。それは、国籍がカナダで、すでに就労ビザが切れているということである。そのため彼女は、何らかの方法でビザを更新するか、グリーンカード(永住権)を取らなければ、不法就労で国外退去の危機にあることがわかる。鼻っぱしの強い彼女は、そのことを知ってか知らぬか、無視していて、上司から言われて初めてそれに気づいた(かのように見える)。出版社としては、ビザのない外国人を雇うわけにはいかない。上司も部下も、彼女の実力は認めながら、とりわけ部下はその独善的なやり方にうんざりしていたので、彼女の退陣を内々喜ぶ。
◆マーガレットには、忠実な秘書がいる。ライアン・レイノルズ(ちなみに、この人、顔がG・W・ブッシュに似てますね)が演じるアンドリュー・パクストンである。彼は、マーガレットの出勤にまにあうように「シナモン入り豆乳ラテラGサイズ砂糖なし」を買うが、万が一のため2つ買うという気配り男。マーガレットは、自分の危機を上司から知らされてとき、彼を利用することがひらめく。彼と結婚し、アメリカの市民権を取ること。どうせすぐ離婚すればいいのよ、と。命令に従順なアンドリューは、しかたがなくそれを引き受ける。自分の原稿を出版すること、使い走りの秘書ではなく、編集者にすることを条件に。しかし、偽装結婚が多いアメリカでは、当局は甘くない。移民管理事務所の係官(デニス・オヘア)は疑心の目で見、来週厳密な面接をするということになる。
◆ドラマは、その面接の「来週」までの終末に起こる出来事を描く。設定は数日間だが、いろいろなことが起こるので、見終わって、まるで1ヶ月ぐらいたったのではないかと思ってしまう。しかし、そのドラマは飽きさせない。場所が、導入部のマンハッタンから、アラスカのシトカに移ることもある。アンドリューの故郷に住む祖母アニー(ベティ・ホワイト)の90歳の誕生日のために、彼は故郷に帰ることになっており、結婚するとなると、祖母や両親にマーガレットをお披露目しなけらばならないからだ。(今後、アラスカを舞台にした映画がけっこう作られるのではないだろうか?この映画を見て、そんな予感がした)。
◆この映画は、(よくあるパターンであるとしても)セントラルパーク沿いの高級マンションに住み田舎を馬鹿にしている都会派の女・マーガレットが、ファミリーの味や田舎のよさを再発見するドラマでもある。カナダのどこの出身かわからぬが、16歳で親を失い、家族的なものとは無縁のまま独力でいまの地位を築いた。ファミリーなんて糞くらえと思っている。その意味で、マンハッタンとシトカの対比は、うまい選択だ。都会派を都市的なものが何もない「大自然」の放り出すという手もあるが、この映画では、田舎町の若干都会的なものも残しながらの対比である。アンドリューの父親ジョー・パクストン(クレイグ・T・ネルソン)は、この島の地主で、この島の店舗などはほとんどパクストン家の支配下にある。「パクストン」と名のついた店が多い。豪邸に住み、経済的な不自由はない。アンドリューは、小説家志望の息子に反対する父に反抗して、ニューヨークに出てきた。彼も、家族的なものや故郷の田舎には確執がある。父親は、いまでも、故郷に帰り、「パクストン王国」を継いでもらいたいと思っている。だから、顔を合わすと、喧嘩がたえず、母親(メアリー・スティーンバージェン)はあいだに立って苦労している。
◆アン・フレッチャーの演出は、細かいところで手を抜いていない。たとえば、マーガレットが、仕事でネットを使わなければとあせり、アンドリューが町の雑貨屋に連れて行く。そこには、有料のネット端末があるのだが、ブラウザを立ち上げ、接続を開始すると、「シャー・ピー」という音がする。「何?!これ?!」と彼女は言うが、おそらく、この意味がわからない観客も多いかもしれない。これは、一時代まえには当たり前だった「電話モデム」の音なのだ。この店では、まだネットを電話モデムでつないでいたのである。スピードは、「シャー・ピー」だと、せいぜい9,600bpsぐらいか(38,600bpsだと「ギャー」という音になる)。ちなみに、いまのネットのスピードは、ADSLでも12Mbpsは出るから、この町のネット端末はマンハッタンあたりの千分の一以下だということになる。
◆アメリカ映画でファミリーが出てくれば、壊れかけたそれが修復に向かうというパターンが多い。少なくともロマンティック・コメディではそうなるのが普通。この映画でも、そのパターンは踏襲されており、その中核にいるのが、ベティ・ホワイトが演じるアンドリューの祖母アニーである。アラスカ・カナダ地方の原住民の血を引くという設定の女性で、ファミリーをしっかりと包容する。原住民の血を引くという感じは全くしないが、ユーモアのある魅力的なおばあちゃんを演じており、この映画の最も強力な助演的パワーになっている。
◆アンドリューとマーガレットのあいだには愛情はないという設定だから、アンドリューの実家に泊まっても、同じベッドには寝ない。が、両親の手前、仲むつまじい関係をつくろわなければならない。そのつくろいの一つひとつが笑わせるわけだが、このぎくしゃくした関係は、必ずしも、こういう特殊な関係の男女のあいだにかぎったわけではなく、もう男なんか信じないという思いに至っている熟年の女、女には関心がないわけではないが、当面仕事が一番だと思っている男、女を恐がっている男、将来への不安があり、結婚などしたいとは思わない(本来ならば適齢期の)の男等々の今日的な男女の意識をちょっとひねった形で描いているとも言える。そういう男女は、その意味で、このドラマのような「アキシデント」を待望している。というか、何かの「アキシデント」がなければ、結婚など決意できないというのが、いまの30~40代の男女の傾向(「不幸」とは言わない)かもしれない。
(ウォルトディズニースタジオ試写室)
2009-08-05
●アニエスの浜辺 (Les plages d'Agnès/2008/Agnès Varda)(アニエス・ヴァルダ)

 ◆この映画を見ると、アニエスは、映画監督というよりも、真性の「メディア・アーティスト」(つまり80年代にいっとき流行したうわべだけの「メディア・アート」とは異なる)、あるいは、もっと広義の「パフォーマンス・アーティスト」とみなした方がよいという考えに達する。冒頭、海辺にいくつも鏡を置き、そこに映った映像をカメラに映し込むパフォーマンスを見せる。スタッフの紹介も鏡の操作で済ませてしまう。スゥイッチャーやあとからのデジタル処理でではなく、リアルタイムで映像を合成したり編集してしまうわけで、これはまぎれもないメディア・パフォーマンスである。また、砂の上に写真を並べる「インスタレーション」もメディア・アートである。さらに、時代を振り返るシーンで、カメラを動かすのではなく、彼女が後ろに後退りするのも面白い。
◆この映画を見ると、アニエスは、映画監督というよりも、真性の「メディア・アーティスト」(つまり80年代にいっとき流行したうわべだけの「メディア・アート」とは異なる)、あるいは、もっと広義の「パフォーマンス・アーティスト」とみなした方がよいという考えに達する。冒頭、海辺にいくつも鏡を置き、そこに映った映像をカメラに映し込むパフォーマンスを見せる。スタッフの紹介も鏡の操作で済ませてしまう。スゥイッチャーやあとからのデジタル処理でではなく、リアルタイムで映像を合成したり編集してしまうわけで、これはまぎれもないメディア・パフォーマンスである。また、砂の上に写真を並べる「インスタレーション」もメディア・アートである。さらに、時代を振り返るシーンで、カメラを動かすのではなく、彼女が後ろに後退りするのも面白い。◆ヌーベルバーグのなかでも異彩を放つあのクリス・マルケスが、猫を描いた動く看板の後ろに身を隠し、さらに声をヴォイス・チェインジャーで変質させて、アニエスにインタヴューするのも、マルケスのパフォーマー的な資質を感じさせて、面白い。まあ、ヌーベルバーグの人たちは、みな、パフォーマンスが好きだったが。
◆今年80歳を越えた(1928年5月生まれ)アニエスが、ベルギーで生まれたときから、その後の半生をふりかえる。写真を学び、写真家として出発した彼女が、フォークナーの小説『野生の棕櫚』の時間構造にインスパイアーされて撮った自主映画『ラ・ポワント・クールト』(1954)から始めて、長編映画『5時から7時までのクレオ』(1961)で成功をおさめ、以後、映画のなかに独自の世界を築いていく。ヌーヴェルバーグの作家たちとの交流、クリス・マルケスとゴダールが仕切った『ベトナムから遠く離れて』のような作品とのシームレスなつながり。以後、フェミニズムとのコミットメントもあるが、だからといってイデオロギッシュな「政治映画」は撮らない彼女の柔軟さは、夫・ジャック・ドゥミの影響でもあったはずだ。彼は、アルジェリア戦争への強烈な批判をメロドラマの形で撮った『シェルブールの雨傘』のように、政治をエンターテインメントのなかにそっとしのばせ、観客が映画を楽しみながら政治感覚をひそかにインプットされて家に持ち帰るような作品を作れる人だった。
◆ジャック・ドゥミは、1990年10月に59歳でこの世を去るが、アニエスはこの映画のなかでも、その死を悲しんでいる。わたしは、この映画で初めて彼がエイズで死んだことを知った。が、映画は、彼がどうしてエイズにかかったかについては明かしてはいない。
◆この作品を見て、アニエスの作品を全部見てみたい気になった。わたしは、1963年6月22日に新宿のアート・シアターで『5時から7時までのクレオ』を見て、アニエス・ヴァルダという女性監督の存在を知った。この映画は実に新鮮だった。当時買った黒と白のコントラストの強い映画パンフレットのNR.12の後ろに万年筆でその日付が書いてある。しかし、この映画にも引用されているその後の代表作、『ダゲール街の人々』や『歌う女・歌わない女』、『冬の旅』などはちゃんと見る機会がなかった。だから、その後、久しぶりにVHSビデオで『アニエスv.によるジェーンb.』(1987)を見たとき、かつてジャック・ドゥミなどといっしょに映っているのを見たことがあるアニエスが、「美人」顔から「オバサン」顔になっているのに衝撃を受けたのだった。が、今回の独特のドキュメンタリーを見て、アニエスは、若いときには、あの「美人」顔にもかかわらずパワフルな女性であったのであり、彼女がやがてブレヒト劇の「肝っ玉母さん」のような感じになるのは、むしろ必然的なことなのだということがわかった。
(松竹試写室)
2009-08-04
●さまよう刃 (Samayou Yaiba/2009/Masuko Shouichi)(益子昌一)

 ◆映画として重厚に出来ている。出演者たちもみな手を抜いていない。だから、映画としてはファーストクラス。が、この映画が原作の小説(東野圭吾)から引き継いだテーマは、一見もっともに見えて、最初から「傾向的」である。つまり、「未成年犯罪に極刑も」といった主張を映像的に支援している傾向である。
◆映画として重厚に出来ている。出演者たちもみな手を抜いていない。だから、映画としてはファーストクラス。が、この映画が原作の小説(東野圭吾)から引き継いだテーマは、一見もっともに見えて、最初から「傾向的」である。つまり、「未成年犯罪に極刑も」といった主張を映像的に支援している傾向である。◆「妻を亡くし、中学生の一人娘を大切に育ててきたが、その娘・絵摩が無残に殺される」とプレスにあるように、最初からどうみても、この父親(寺尾聡)には、犯人たちに復讐心を燃やしてしかるべき理由があるように設定されている。その時点で、犯人たちは、「獣」同然の存在におとしめられ、寺尾に復讐されて当然というロジックが成立する。注射を打たれ、強姦され、ショックで死んでしまった少女、残されたビデオに写った若者たちの姿、車を貸した仲間の若者の密告を通じて犯人を知り、その一人を殺す寺尾、こうしたプロセスを追いかける二人の刑事(竹野内豊・伊東四朗)は、次第に寺尾に対して同情的になる。現在の法律では、未成年の犯罪に対する刑罰は軽い。人を殺しても死刑にはならない。
◆犯人がこれでもかこれでもかという残忍なことをして、被害者やその家族が反撃したり、復讐したりするドラマは、いくらでもある。その場合、犯人の犯行がひどければひどいほど、それへの反撃や復讐は(少なくとも心理的には)正当化される。その過程で、法の番人である警察は、逡巡を見せるとしても、それは、反撃や復讐の正当化のどぎつさを和らげるためのものでしかない。観客は、絶対に反撃や復讐に声援を送る。ただし、この映画は、単純にそんなパターンを踏んでいるわけではない。寺尾は、犯人の一人に対しては単純な復讐を遂行するが、もう一人の犯人には(そちらの方がおそらくもっと悪質だと思えるにもかかわらず)そうはしない。法を守るべき警察のタテマエも生かした、屈折した終わり方をする。だから、この映画の結末は後味がよくはない。
◆この種の終幕は、「観客に考えさせる」終わり方のように見えるかもしれないが、わたしはちがうと思う。アクションとドラマをめりはりよく描くタイプの映画(この作品もそうだ)という形式が、そもそも、「考えさせる」ということとは同居しずらいということは知っておくべきだろう。たしかに、犯人は「無慈悲」だった。少なくとも、われわれに提示される映像では、そうとしか見えない。が、彼らが人間であり、それぞれの生き方をしているとすれば、彼らを「けだもの」と断定して済ませるわけにはいかない。そういう人間を育ててきたのは、同じわれわれが住む社会であり、同じ空気だからである。
◆法制度というものは、基本的に拒絶と排除の機能にたけていて、許容と理解は得意ではない。法の番人は、許容と理解から身を遠ざけなければ、その役割を果たせない。だから、法制度からはずれた者、つまりは犯罪人は、その法制度が施行されている社会から隔離されるか、抹殺されるし、法の番人はそういう方向で反社会的人間に対応する。
◆しかし、法制度というものは、資源や権利の共有を効率化する便宜であって、その社会を構成する個々人の特異性やイデオシンクラシーを尊重することは、その本性上できなものなのだ。もし、そうした効率化を考えなければ、社会の枠組みを少なくとも「犯罪」の種類だけ構築すべきだし、「犯罪者」は、処罰されるのではなく、それぞれの異なる枠組みのなかに移住させられるべきだろう。刑務所は、隔離の施設であるが、その画一性は、「犯罪者」を一色に同化させる装置ではあっても、決してその特異性をまっとうさせる解放装置ではない。
◆おそらく、順序は逆なのだろう。社会が画一化と同化を求めるから、それに逆らい、それに反逆する者を生み出す。法の番人は、そうした者たちを処罰することによって排除したり隔離したり抹殺したりするが、それでは、何ら根本的な解決にはならない。
◆犯罪が終わることがないのは、社会の「多様化」とはうらはらに、法制度の多様化は一向に進まないどころか、法というものそのものが、多様化とは裏腹のものであるからだ。だから、歴史的には、都市はつねにその内部にさまざなな「暗部」、「ゲットー」、「アンタッチャブル」なクラスターや小世界を作ってきた。それらの間には孤立があるが、その個々の内部にはそのなかでだけ通用する「自由」がある。たがいに干渉せず、結果的にたがいを尊重しながら共存する、という形式だ。それは、いまでも可能だが、現実には、むしろ画一化、ゲットーの破壊に向かっている。
(東映第1試写室)
2009-08-03
●サブウェイ123 激突 (The Taking of Pelham 1 2 3/2009/Tony Scott)(トニー・スコット)

 ◆わたしにとってはなつかしの『サブウェイ・パニック』(The Taking of Pelham One Two Three /1974/Joseph Sargent)を、現代に置き換えた「リメイク」である。ニューヨークの地下鉄も都市も、1970年代とはずい分違っているとしても、ニューヨークという都市へのアプローチが、ジョゼフ・サージェントとトニー・スコットとでは根本的に違う。旧作では、英語がわからないスパニッシュの女性やユダヤ系の老人(かつてイーディッシュ演劇の名優だったマイケル・ゴーリンが演じている)などを登場させ、この都市の人種的な多様性をちらりと表したり、生活感覚がむんむんと伝わる描き方をしていた。
◆わたしにとってはなつかしの『サブウェイ・パニック』(The Taking of Pelham One Two Three /1974/Joseph Sargent)を、現代に置き換えた「リメイク」である。ニューヨークの地下鉄も都市も、1970年代とはずい分違っているとしても、ニューヨークという都市へのアプローチが、ジョゼフ・サージェントとトニー・スコットとでは根本的に違う。旧作では、英語がわからないスパニッシュの女性やユダヤ系の老人(かつてイーディッシュ演劇の名優だったマイケル・ゴーリンが演じている)などを登場させ、この都市の人種的な多様性をちらりと表したり、生活感覚がむんむんと伝わる描き方をしていた。◆スコット版は、サスペンスにウェイトを置き、警察が現金を移送するシーンを派手派手に描く。ただし、デジタル処理を多用し、しかもそのスタイルが少し古めの「ミュージックビデオ」風なので、カー・クラッシュのシーンなどスリルが出ていない。カメラは実際に回したのかもしれないが、デジタルの嵌め込み操作でも作れそうな(結果的にであれ「安手」に見えてしまう)仕上がりになっている。
◆乗客の個性は、ほとんど無視され、乗客で印象に残るのは、ひそかに車内からビデオチャットの映像を送り続ける青年だけである。その場合も、主役はこの青年の個性ではなく、彼のコンピュータ画面であって、この青年が何者なのかという人間的興味は希薄である。なるほどその分、主犯の「ライダー」(ジョン・トラボルタ)、彼と無線で交渉をするMTA (The Metropolitan Transit Authority )の地下鉄配車係「ガーバー」(デンゼル・ワシントン)、NYPDの警部補カモネッティ(ジョン・タトゥーロ)、ニューヨーク市長(ジェイムズ・ガンドルフィニー)、ギャング仲間の「レイモス」(ルイス・ガスマン)等の登場人物は、癖の強い俳優によってその個性が強く印象づけられる。しかし、映画のなかの「無名」の人はほとんど無視されている。
◆登場人物の個性という点では、ジョン・トラボルタが、ふだんとは別人のような「悪」と「狂気」の個性を見事に演じている。彼の「危険な」手下を演じるVictor Gojcaj(発音不明)は、トニー・スコット監督が発掘した新人とのことだが、映画初出演とは思えない「悪党」の面構えを見せ、将来有望である。
◆まえにも書いたが、オバマ政権以来、アフリカン・アメリカンや「黒人」系の登場人物――従って俳優もそれにならう――が映画のなかでも増えているが、この映画でジョン・トラボルタは、顔をやや浅黒くメイキャップし、明らかに「白人」とは違った「有色」系の登場人物になっている。旧作では、ガーバーは、ウォルター・マッソーが演じ、地下鉄ジャッカーたちは「白人」ばかりだった。
◆今回、MTAは、映画の撮影に協力的だったとのことだが、旧作のときには、最初、本物の地下鉄駅での撮影も禁じられ、MTAは、すべての協力を拒否した。最終的に、当時の市長のジョン・V・リンゼイが割って入り、ブルックリンのトンネル内などの使用が許可されたが、製作側は、施設使用料と「反ハイジャック対策」の保険料をMTAに支払わなければならなかったという。ちなみに、1972年にミュンヘン空港で「アラブ・ゲリラ」による乱射事件があり、公共機関のハイジャックは最大の関心事になっていた。だから、『サブウェイ・パニック』も作られ、ヒットしたのである。
◆旧作以上に今回は、MTA、市、警察などの官僚主義への批判が強く表現されている。旧作でも、市長への風当たりは強かった(面白いことに登場する映画のなかの市長――リー・ウォレスが演じている――の顔は、当時の市長のリンゼイによりも、当時の市政のナンバー2で、1978年から市長になるエド・コッチに似ている)が、新作の市長も、不倫騒動で辞職寸前の状態にあり、自宅に引きこもっている。
◆新作では、犯人たちはみんな銃撃されて死ぬが、旧作では犯人たちの死は多様だった。(もう書いてしまっていいと思うが)主犯のブルー(ロバート・ショウ)は、線路と並行に走っている「サードレール」に足をかけて、みずから「感電死」する。そのまえのセリフがいい。地下鉄公安局警部補(新作では警部補ではない)のガーバー(ウォールター・マッソウ)(ちなみに新作の「ガーバー」のファーストネームが「ウォールター」なのは、マッソーへのオマージュらしい)に、「この州ではまだ死刑(電気椅子)はあるのかね?」と訊く。追いつめられて、先を見越したのだ。
◆この映画では、銃が派手に乱射され、血や脳漿が飛び散る。これは、旧作では抑えられており、撃たれる場合も、ただ死ぬのではなく、それなりの理由があった。ブルーに逆らってばかりいた仲間は、銃殺されるが、ブルーは、英国の軍人で傭兵としてアフリカなどにも行っているという設定で、命令に背く者は許さないという軍規に従っていたわけだ。
◆旧作ではのうのうと生き残り、自宅で札束とベッドの上で戯れている男がいる。名優マーチン・バルサムが演じる男グリーンで、彼は犯行まえにカゼを引き、ハイジャックした地下鉄のなかでもクシャミを繰り返す。その音は構内電話での交渉のとき、ガーバーは気づいている。その最後のシーンで、グリーンのアパートに、ガーバー警部補らが任意の訊問にやってくる。何とか切り抜けけ、ようやくガーバーらが去ったとたんに、大きなくしゃみをしてしまうグリーン。映画は、「ん?!」という顔でもう一度ドアを開くガーバーのアップ(この顔は喜劇役者としてのウォールター・マッソウの顔)で終わる。このへんのユーモアは、新作には全くない。
◆旧作には、日本の地下鉄関係者がグランド・セントラル駅のコントロール・ルームを見学に来るという設定のシーンがあり、例によってカメラを首から下げ、いつもぺこぺこ頭を下げ、英語で話しかけられるとさっぱりわからないという、差別的な「日本人」像がえがかれていた。新作では、そういう日本人は出てはこないが、時代の変化だと思わせるくだりがある。ガーバー(デンゼル・ワシントン)は、地下鉄車輌の選択権をもっている管理職についていたが、日本の車輌会社から賄賂をもらったという嫌疑をかけられて、配車係りに左遷されたのだった。そのくだりに関連するせりふのなかで、日本の車輌は、技術的に世界一だという意味のことが言われる。かつて、外国に行って写真ばかり撮っている「日本人」が馬鹿にされたが、いまでは、どこへ行っても、非日本人が、デジカメで写真ばかり撮っている。時代は変わる。
(ソニー試写室)