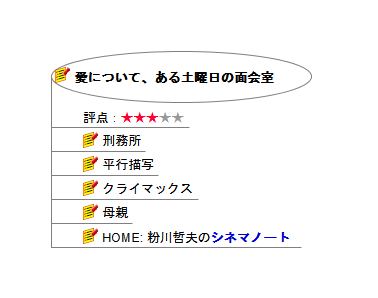◆映画は、マルセイユの郊外にある刑務所の前庭のシーンから始まる。明らかに狂っている女が何かを探し、髪をふり乱して叫び、泣き出す。「助けてください」となんども言うが、まわりの人々は相手にしない。ここに映る人々は、受刑者に面会するために来た家族や近親者たちだ。最期にわかるが、このシーンにこの映画の主要な登場人物たちの姿がある。
◆日本の刑務所の面会とちがい、面会する組が同じフロアーで同時に会う。前庭に集団で集まり、一定時間にゲイトが開いて、面会する家族や近親者がなかに入る。ゲイトで持ち物と身体の検査があるが、かなり甘い。これまた一定時間に全員の面会が開始され、この映画の場合は、30分で一斉に終わる。クライマックスは、その30分間に起きることである。
◆面会の際に獄中者と面会者との間に仕切りがないので、抱擁しあったり、手を取り合ったりする姿がある。こういう光景は、日本ではありえない。日本にも、出所まぎわになった者に対して〝家族面会室〟が提供されるが、体に触れることは禁じられる。これは、管理の厳しさと取ることもできるが、むしろ、日本の身体文化との関連で考えたほうがよいと思う。刑務所とは、その国々の〝国風文化〟をあらわにする。日本の〝国風〟は、〝べたべたすること〟をよしとしないのだ。逆に、フランスでハグや握手を禁じたら、人権というものを全く認めないことを意味し、暴動になるだろう。むろん、国家や国風はいつも、個々人がすでに実践していることに遅れて機能するから、いまの日本の〝国風〟が現実にあっていないのは驚きではない。
◆この映画の面会風景を見て、フランスの監獄が日本のそれより〝自由〟であると考えるのは、現実を見誤っている。国家が作るものに自由はないし、そもそも自由という観念は外的な拘束のありなしから考えるかぎり、意味をなさない。アントニオ・ネグリは、<私は監獄と残りの人生との間にそれほどの基本的な違いがあるとは思っていない>と言い、<生が自由ではないのと同じように――少なくとも労働者の生では――、監獄は自由の欠如ではない>と書く(「監獄と生」、『未来への帰還』、杉村昌昭訳、インパクト出版会)。
◆面会室の内部を動くカメラは、母親と息子、恋人同士といったさまざまな組み合わせを映し出すが、ちらりと聞こえるセリフは、「どうしてこんなことをしたの」とか、「もう俺のことは忘れてくれ(面会なんかに来ないでくれ)」といったもので、これらは、カップルや家族などの小単位を含む<社会>でかわされる象徴的な表現である。
◆日本の刑務所の面会様式が、他の面会者と切り離す方法をとっているのは、日本国家が日本に住む個々人(国民ひとりひとり)をどうあつかおうとしているかと無関係ではない。日本国家は、この映画の面会者たちのような<不特定多数>の集合(これがデモクラシーの基礎であり、西欧の街の広場で日々目撃できるものである)を禁じているのである。

◆前庭のシーン以後、3組の物語が並行的に描かれる。その人物たちは、グランドオペラ風やアンサンブル・プレイ風に最期に一同に会するわけではない。一応、刑務所の面会室にやってくるが、たがいに関係しあうわけではない。その意味では、ここでは、3つの物語が同時的に展開するのを見るということになる。
◆(1)ステファン(レダ・カテブ)は、母親と金のことでもめている。いっしょに住んでいるエルザ(ディナーラ・ドルカーロワ)と三つ巴で喧嘩をしている。「あたしの子宮をeBayで売りなさいよ」というエルザのセリフからすると、この母親はがめついのか、息子に働きがないことを呪っているのかようわからないが、とにかく彼女には貸した金があるらしい。彼は、病院の血液をバイクで運搬する仕事をしているが、バイト的な仕事らしい。原因は母親だけではないようだが、ステフェンとエルザの関係もぎくしゃくしている。そんなとき、彼女が地下鉄駅で襲われたが、ちょっとヤクザ風の男ピーエール(マルク・バルベ)に助けられて、病院にいるという知らせが入る。この男、ステフェンの顔を見ると、自分の親友に似ていると言い、奇妙な仕事を頼んでくる。その親友はいま刑務所にいるのだが、面会のときにすり替わってくれないかというのだ。その謝礼は保証するし、1年もすれば出すようにするという。まともには信じられない話だが、ステファンは金のために興味を示す。
◆(2)アルジェリア人のゾラは、息子が殺され、パリから空輸される遺体に面会するために警察にやってくる。安置された遺体に向かう母親の姿は痛々しい。彼女は、息子を殺した同性の相手が彼の元恋人であったことを知り、その彼に会おうとする。パリにその姉セリーム(デルフィーヌ・シュイヨー)が住み、不動産屋を営んでいることをつかみ、パリに行く。セリーヌに近づき、子供のベビーシッターとして雇われ、それが・・・するプロセスは、これだけで一本の映画になりそうな重みとドラマ性をはらんでいる。このことは他の話にも言えることだ。
◆(3)16歳のロール(ポーリン・エチエンヌ)は、バスのなかで知り合ったロシア系の青年アレクサンドル(ヴァンサン・ロティエ)に連れられて〝サンパピエ〟(不法移民/サン・パピエ sans-papiers→ヴィザを持っていない人々)の居住区に案内され、つかのまの二人で〝スクウォッティング〟生活を楽しむ。が、不法占拠と不法移民を許さない警察の急襲を受け、逃げ出す。フランスでは〝サンパピエ〟の運動は以前からあるが、アレクサンドルはそういう活動家らしい。やがて、ロールは、彼が逮捕されたことを知る。
◆この3つの物語が、おしゃれな編集でシームレスに切り替わりながら展開するのだが、(2)と(3)の比較的時代性の強い物語に比して、(1)が、定職を得ることの難しさを問題にしながらも、獄中者とすり替わるというサスペンシヴな話に向かうために、こちらが(2)と(3)を圧して、全体がサスペンスになってしまうきらいがある。
◆しかし、この映画の基本には、サスペンスで終わってしまうわけにはいかない問題がある。その一つは、格差や貧困であり、母親の存在論的な問題だ。ステファンは、ピエールに鍛えられて〝男〟になる。それがいいとは(わたしは)思わないが、〝男〟にならなければ(女も)仕事にありつけないのが現実である。ゾラは、息子に対して〝母親〟として失敗したという思いがある。ロールは、たぶん、母親に対しても現実に対しても、他とは異なる姿勢を持っているのだろう。だから、この映画は、ステファンよりも、ロールを中心にしたほうがよかった。
◆ロールは、16歳なので、単独では収監されているアレクサンドルと面会することができない。そこで、彼女は、たまたま知り合ったアントワーヌ(ジュリアン・リュカ)に介添えを頼む。面会はつねに3人で会うことになるが、この3者のあいだに微妙な感情が生まれるところも、もっと展開できるだろう。いまの社会は、男と女であれ同性同士であれ、親と子であれ、二者関係というものの難しさをあらわにしている。では、三者関係はどうなのか? こういう方向をもっと深めるならば、見応えのあるものになるだろう。

◆クライマックスは、刑務所の30分の面会時間のなかで起こる出来事だが、ステファンがジョゼフとすり替わるドラマがサスペンス調なので、この部分に焦点が当たってしまう。これは、ドラマを盛り上げるという意味では効果的だが、せっかく最期まで多元性を維持しながら持って来たトーンを崩してしまう。この点を除けば、この映画の評価は5星中4星はあたえることができた。
◆映画がインプットした可能性は、このサスペンスよりもはるかに大きい。ゾラが、自分の息子を殺したフランソワ(ミシェル・エルペルディング Michaäl Erpelding)と面会するシーンで、それと知らずに会った彼が、やがて動揺を抑えて話し始めることとか、ロール、アレクサンドル、アントワーヌとの三者のあいだで、それまで傍観者のつもりでいたアントワーヌのなかで起こるように見える変化とか、また、成り代わりを果たしたステファンがそれからどうなるのかとか、いろいろな思いと想像が残る。

◆この映画には、父親が不在である。それは、脚本・監督のレア・フェネールの選択であり、現実把握の結果である。彼女は、暗黙に、現代を<父親なき>社会ととらえているように見える。問題は、それにもかかわらず、<父親や男にされる>ことだ。ステファンの母親は、まるで<男>である。彼の恋人エルザを助ける(このへんはからくりくさい――つまりステファンに成り代わりの仕事をさせるためにこの事故を仕組んだとも考えられる)ピエールという男は、<男のなかの男>である。ゾラには老いた母親がいるが、その関係は抑圧的ではない。ゾラはイスラム系の文化に属している。ロールとアレクサンドルとの関係は、次第にアレクサンドルが嫉妬深くなるにつれて、ごく普通の<男>と女の関係に堕ちて行くが、その間にいるアントワーヌの姿勢が微妙で、意味ありげである。

HOME: 粉川哲夫のシネマノート
■粉川哲夫のシネマノート