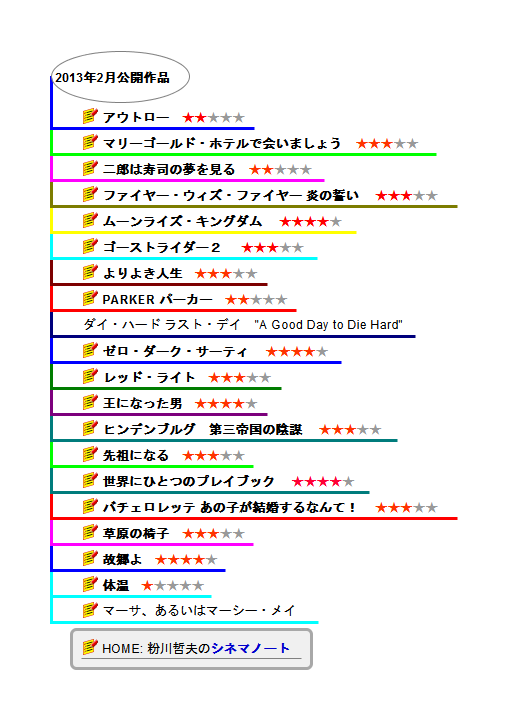アウトロー ★★★★★
■Jack Reacher/2012/Christopher McQuarrie(クリストファー・マッカリー)
◆トム・クルーズに関しては、『コラテラル』の殺し屋の感じで行けばいいのではないかと期待したが、脚本が脆弱だった。トム・クルーズの本領を活かしていない。
◆この種の作品にはつきものの女性役のロザムンド・パイクがミスキャスト。そもそも顔がこのドラマ向きではない。そのうえ、これも脚本の弱さだが、彼女が、点数かせぎの裁判しかしない地方検事(リチャード・ジェンキンス)に反発する弁護士という設定も月並みだ。
◆通行する5人を暗殺した狙撃事件が起こり、犯人として逮捕された男ジェームズ・バー(ジョセフ・シコラ)は、突きつけられた証拠に、とても正攻法では釈放されることはないと観念して要求したのが、「ジャック・リーチャーを呼んでくれ」というセリフだった。このへんの捻りは悪くない。が、もっと簡単に救世主を呼ぶほうほうはあったはずだという思いが残る。自分が手ごわいやり方ではめられたと悟ったとき、戦友のジャック・リーチャーを最後の綱にするのは論理的にはわかるが、サスペンスのために案出されたプロットという感じがするからだ。これは、マッカリーの前作の『誘拐犯』での過剰に使われる銃撃シーンのあつかいにも通じる。
◆久しぶりにロバート・デュヴァルを見ることが出来、それなりの演技を楽しめるが、ジャックとの出会いから共闘のプロセスは型にはまっている。予想外に凄腕の老人とオールマイティのジャックとが冷酷なワルを相手に闘うというパターンは、型にはまりすぎている。これも、責任は脚本にあるとしておこう。
◆ワルの凄味を見せるということが最初から予告しているように登場するのが本来は監督業のヴェルナー・ヘルツオークだが、これも見かけほどではない。
◆後半で重要なカギをにぎる刑事役のデヴィッド・オイェロウォは、最初からせりふがおぼつかない。日本の場合だと〝新劇〟系の教育を受けた俳優がよくやる〝他人事〟のような発声法である。俳優の演技は発声法は、監督に責任がある。
◆長編の監督としては前作の『誘拐犯』(The Way of the Gun/2000)だけのマッカリーだが、この作品に関し、ロジャー・イーバートは、"a wildly ambitious, heedlessly overplotted post-Tarantino bloodfest--the kind of movie that needs its own doggie bag."と評した。「ドギーバッグが必要な映画」とは言いえて妙だ。見たその場では堪能しきれない作品という意味だが、持ちかえったとしても、食べるかどうかはわからないから、つまりは食べれば消化不良になるので、とりあえず持ち帰りたくなるような料理のようだというわけ。ただし、今回の『アウトロー』は、持ち帰る気にもなれず、なんか損をした気持ちにさせた。
"

マリーゴールド・ホテルで会いましょう ★★★★★
■The Best Exotic Marigold Hotel/2011/John Madden(ジョン・マッデン)
◆老後をどう暮らすかについて、西欧社会は日本より大分以前から意識が高かったと思うが、近年、このテーマの作品が目につくのはなぜだろう? この作品では、それぞれに訳ありの老人たちがインドにやってくる。夫を亡くしたばかりのイブリン(ジュディ・デンチ)、価値観のちがうダグラス(ビル・ナイ)とジーン(ペネロープ・ウィルトン)の夫婦、元判事でゲイのグレアム(トム・ウィルキンソン)、いい歳になっても新しいパートナーへの夢を捨てきれないマッジ(セリア・イムリー)、もうちょっと純粋なロマンティストのノーマン(ロナルド・ピックアップ)、股関節疾患で車椅子のミュリエル(マギー・スミス)。
◆人生をやりなおそうという西洋人にとって、インドは期待をふくらませる場所。が、インドはそう甘くはない。親から引き継いだホテルの経営に苦労している青年(『スラムドッグ$ミリオネア』のデブ・パテル)が西欧の高齢者が来てみたくなるようなウェブサイトを作る。ユートピア的夢をいだいてはるばるイギリスからやってきたのがこの7人だ。出演者たちは、それぞれに偏屈な老人のパターンを演じ、笑わせ、泣かせ、しんみりさせる。
◆夢をある程度満たす者、適応できずに帰る者、永住の決意をする者等々、結果をさまざまだが、老後という修羅場には、マギー・スミスが演じたような一見利己的で妥協のない老人のほうが強いのかと思う。
◆ディテールのしっかりした映像と軽快なテンポ、たくみに構成されたプロットで飽きない2時間である。たしかに老後をいかにすごすかということが主要なテーマになってはいるが、ここで描かれるのは、彼や彼女らにかぎらず、デブ・パテルが演じる青年と恋人との関係をもふくむさまざまな愛の微妙なメロドラマである。別れあり、再会あり、死ありの一定の時間がたったあと、あらたな組み合わせの余韻を残しながら終わる。
◆挿入される音楽と音の演出は、ドラマ以上に華麗であり、多様性に満ち、すばらしい。

二郎は寿司の夢を見る ★★★★★
■Jiro Dreams of Sushi/2011/David Gelb(デイヴィド・ゲルプ)
◆食べ物に興味のある者なら、〝すきやばし次郎〟を知らない者はいまい。鮨道では別格の人である。だから、この人(小野二郎)が映像になるというと、大いに期待が高まる。どんな映し方をしても小野二郎は小野二郎であり、それなりの説得力を持つはずだ。このドキュメンタリーは、しっかりと撮っている。いちゃもんをつける気はない。しかし、音楽に問題がある。これから小野二郎の握りの秘密が公開されるというシーンの音楽が、チャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲なのだ。これでは、二郎の握りが月並みなメロに流れてしまう。
◆他にマックス・リヒター、モーツアルトなどが使われ、フィリップ・グラスはかなり聴かされる。しかし、小野二郎の鮨は、フィリップ・グラスじゃないでしょう。
◆料理評論家としての山本益博の功績を否定するつもりはないが、最初からこの人がガイド役で出てくると、若干警戒心が出てしまう。この人は、料理評論を商売にしている人である。彼がこれまで文字でやってきたときにはせこいと言わざるをえない演出は覚悟しなければならない。
◆ただし、すきやばし次郎の寿司が抜群なのは、特上のネタの確保と処理が抜群だからだ。寿司屋の質は大体ネタの供給で決まる。この映画は、寿司職人の指先に特別の秘密があるような見せ方をしている。これは、事実ではない。彼らがいかにして特上のネタを安定供給できるようになったかを見せなければ、すきやばし次郎の秘密には迫れない。これでは、彼が生きているあいだに〝伝説〟のおすそわけを得るために店に駆けつけたいというミーハーを増やすだけだ。もろん、それは山本益博のねらいでもある。
◆こんな映画を見るよりも、里見真三(文章)、丸山洋平(写真)の『すきやばし次郎 旬を握る』(文藝春秋社)を読んだようがいい。いまでは、文庫本でも読める。

ファイヤー・ウィズ・ファイヤー 炎の誓い ★★★★★
■Fire with Fire/2012/David Barrett(デイヴィッド・バレット)
◆コンビニで非情な殺人を目撃してしまった消防士ジェレミー(ジョシュ・デュアメル)は、以後、その悪党たちに追われることになる。親子を非情に殺すネオナチ的な悪党を演じるヴィンセント・ドノフリオは、悪の演技として『ロボコップ』のクルトウッド・スミスに匹敵する。
◆殺人者たちは、ジェレミーの証言を阻止するために彼を消そうとするが、彼は反撃にでる。その際、どんな手で行くかは、彼が消防士であるということと、「ファイヤー・ウィズ・ファイヤー」(an eye for an eye, a tooth for a toothを思わせる「火には火で」)が最初から暗示している。だから、先が読めてしまうのだが、ジェレミーを証人として守ろうとする刑事役のブルース・ウィリスの渋い演技もあるので、失敗作にはなっていない。

ゴーストライダー2 ★★★★★
■Ghost Rider: Spirit of Vengeance/2011/Mark Neveldine+Brian Taylor(マーク・ネヴェルダイン+ブライアン・テイラー)
◆準備中
◆ヴィオランテ・プラチドがなかなかいい。

レッド・ライト ★★★★★
■Red Lights/2012/Rodrigo Cortés(ロドリゴ・コルテス)
◆不可解なシークエンスがいくつかあるが、それも観客に考えさせるということならそれでもいいだろう。(1)トム・バックリー(キリアン・マーフィー)はトイレで殺し屋に襲われ、流しが割れるほどたたきつけられ、頭をさんざん殴られるが、死なない。(2)最後のほうになって、重要な秘密を解くのが、いきなり(授業のシーンではちらりと出ていた)登場し、コンピューターや映像機器を駆使した調査をする。(3)サイモン・シルバー(ロバート・デ・ニーロ)の〝超能力〟がインチキであることを暴いた末に、今度はトムが同じような能力を持っているらしいことを示唆するが、なんか説得力がない。
◆念力で劇場内が揺れ出し、場内の照明器具などが落下したり、コントロールルームのガラスが割れたりというシーンは、基本のテーマが〝超能力〟のインチキさを暴くことにあるので、たとえそれが誰かの超能力によるものだとしても、相対化されてしまい、説得力がない。
◆〝超能力〟を調査する機器が見えるが、コンピュータを使いながら、リール式のテープレコーダーを使う理由はどこにあるのか? 映画では、いまだに小さな機械では絵映りがしないというわけか、オープンリールのテープレコーダーを見せることがよくある。

世界にひとつのプレイブック ★★★★★
■Silver Linings Playbook/2012/David O. Russell(デイヴィド・O・ラッセル)
◆ジェニファー・ローレンスが、『ハンガー・ゲーム』や『ボディ・ハント』ではまだ残っている〝小娘〟的な雰囲気を完全に振り払い、レベルが一段階うえのキャラクターを見事に演じているのが凄い。単に体当たり的な力づくではなく、〝双極性障害〟の女を演じる。

体温 ★★★★★
■Taion/2011/Takaomio Ogata(緒方貴臣)
◆ラブドールを愛する男(石崎チャベ太郎)が、ラブドールそっくりの顔の女(桜木凛)に出会うという設定はいいのだが、クレイグ・ギレスピー監督/ライアン・ゴズリング主演の『ラースと、その彼女』、是枝裕和監督の『空気人形』といった作品がすでに表現したことをまったく咀嚼していないのは嘆かわしい。この映画の結末は、これらの2作にに先行するロバート・パリジの『ラブ・オブジェクツ』(Love Object/2003/Robert Parigi)と同様、ヴァーチャルな身体と生身の身体との不幸な混交であり、いまやヴァーチャルな性的身体がかぎりなく増殖する環境の時代には、あまりに古すぎるドラマである。

HOME: 粉川哲夫のシネマノート
■粉川哲夫のシネマノート