| ★今月のおすすめ(公開順): シリアナ ブロークバック・マウンテン かもめ食堂 ステップ!ステップ!ステップ! ククーシュカ ラップランドの妖精 |
| ファイヤーウォール 君とボクの虹色の世界 僕の大事なコレクション ナイロビの蜂 間宮兄弟 戦場のアリア 親密すぎるうちあけ話 ジャケット STAY ステイ プルートで朝食を フーリガン ココシリ 嫌われ松子の一生 雪に願うこと インサイド・マン ロシアン・ドールズ ディセント |
2006-03-29_2
●ディセント (The Descent/2005/Neil Marshall)(ニール・マーシャル)

◆この映画は、第8回ブリティッシュ・インディペンデント映画賞の最優秀監督賞と最優秀映画技術賞、スウェーデンの第11回ファンタスティックk・フィルムフェスティヴァルの最優秀作品賞を受賞し、さらにいくつかの賞に輝いているという。英語で読めるメイジャーな映画評も好評であり、IMDbの User Raiting でも7.5/10 をつけている。が、わたしが見たかぎりでは、どこがそんなにすぐれた作品かが全くわからないのであった。むしろ、IMDbで、「金かえせ!!!」(I want a refund!!!)とか「(DVDを)借りるな ― ひどい」(Do not rent - Dire) などと書いているレヴューの方に賛同してしまうのである。IMDbには、そういう糞味噌の批評もかなりある。プロっぽいレヴューでは概して「好評」で、アマチュアの批評では散々という感じもする。わたしのようなホラーものの素人にはわからない奥深さがあるのだろうか?
◆登場するのは、主として6人の女性。川下りとか洞穴探険とか、冒険に入れ込んでいる仲間同士。映画は、ゴムボートで3人が川下りをしているシーンから始まる。乗っているのは、母親と娘2人かと思ったら、岸に着いたのを見ると、3人とも大人の女なのだった。岸で迎えるのは、その一人サラ(シャウナ・マクドナルド)の夫(オリバー・ミルバーン)とまだ幼い娘(モリー・カイル)。そのとき、この夫が何か変な、うかない態度をしているのが気になったが、その点での展開はなく、そのまま次のシーンに飛ぶ。が、場面が変わって、夫が運転し、サラと娘が乗っている車は、あっという間に衝突事故を起こし、2人は死んでしまう。何なのだと思っていると、1年後という設定になり、女ばかりがサラの家に集まる。ここは、何かレズ軍団が勢ぞろいしたかのようで面白い。はあ?、女だけで探険隊を組んでいるなんてのがあるのかぁという感じ。
◆どうやら、家族を一瞬にして失ってしまったサラを探険仲間が慰めるため、洞窟探険をしようというらしい。それを仕切るのは、自信過剰でやや無鉄砲な感じをただよわせるジュノ(ナタリー・メンドーサ)。で、手慣れた身ぶりで女たちは、洞窟に入るが、小さな地震が起こり、入口をふさがれる。実は、この洞窟、ジュノが言っていたのとは、ちがい、全く地図に載っていない未踏の洞窟だった。ジュノは、それを知っていて、新洞制覇の手柄を立てるために、他の仲間には黙っていたのだった。パニックが広がるが、とにかく、出口を探さなければならない。奥に進むと、クレバスの向こう側に出口がありそう。このクレバスをトラバースするシーンはなかなかいい。
◆映像は、全体にそう悪くない。が、俳優が安い。テレビには出ていても、映画の経験はあまりない俳優が多い。面白いのは、サラ役のシャウナ・マクドナルドが、マレーシア生まれ、ジュノ役のナタリー・メンドーサが香港、レベッカ役のサスキア・マルダーがオランダ(日本のプレスではニュージーランド)、サム役のマイアンナ・バリングがスウェーデン、ノーラ・ジェーヌ・ヌーンがアイルランド、ベス役のアレックス・リードだけがUK生まれというように、実に多様な出身別の俳優によって構成されている。が、そのせいか、その多様性が、いったいこの女性集団は、どのように生まれたのかという気持ちを起こさせるくらい、不思議な感じがする。探険でつながっているといっても、これだけタフな女たちは、そうざらにはいない。ま、細かいことはどうでもいいという映画なのである。
◆配給会社の御達しで、最後のシーンについては明かさないでほしいとのことだが、ネットで読むことのできる英文のレヴューでは大部分がはっきり書いているし、トレイラーにはその姿(→
 )がばっちり映っているので、わたしも書くことにする。要するに、怪物に出会うのだ。その設定は、同じ監督の前作『ドッグ・ソルジャー』(Dog Soldiers/2002)に似ている。が、このシーンも、映像的には、しっかりと撮られていて、ただのこけおどしではないリアリティがある。そのへんで楽しむしかないのかな。
)がばっちり映っているので、わたしも書くことにする。要するに、怪物に出会うのだ。その設定は、同じ監督の前作『ドッグ・ソルジャー』(Dog Soldiers/2002)に似ている。が、このシーンも、映像的には、しっかりと撮られていて、ただのこけおどしではないリアリティがある。そのへんで楽しむしかないのかな。◆サラの夫は、実は、このグループのジュノ(だったか?)と出来ていたらしいことがちらりと示唆される。それが、冒頭のシーンの夫のうかない顔に結びつくのだろうが、それは、ジュノに対するサラの不信感と怨みをエスカレートさせる程度の意味しか持たないのか、それとも、もっと意味があるのかは、はっきりしない。
◆6人の女を狭い空間に閉じ込め、怪獣(どうもみんなオスらしい)に襲わせるというのは、どこか、「繋縛もの」に通じる何かがありそう。この映画が好きな人は、無意識裏でそんな感覚を働かせているのではないかな?
(スペースFS汐留/エイベックス・エンタテインメント)
2006-03-29_1
●ロシアン・ドールズ (Les Poupées russes/2005/Cédric Klapisch)(セドリック・クラピッシュ)

◆無数のスネイルがジグゾーのようにならぶ画面から一つのスネイルへズームインされるスタイルで始まる画面はおしゃれ。パリ/ロンドン間を走る新幹線のなかでロマン・デリスが PowerBookで仕事をしようとするが、バッテリー切れになる。あわててPowerBookをかかえてトイレに走り、コンセントから電源を取る。これから始まる物語が、彼自身によってPowerBookで書き始められているということが示唆される。まあ、よくあるスタイルではある。この映画では、無数のスネイルの使い方とか、「リアル」な場面に、複数のロマン・デリスを登場させるとか、映像上の工夫が見られる。が、それらは、それほど斬新なわけではない。ポジティヴな言い方をすれば、それらが気にならない。
◆2001年のヒット作『スパニシュ・アパートメント』の続編という形になっている。パリの大学生のグザヴィエ(ロマン・デリス)は、「エラスムス・プログラム」奨学金を取得して、バルセロナに留学した。そこで、同じ奨学金でヨーロッパの各地から来た同年配の若者と共同生活をしたことが、彼にとって忘れ難い経験となった。留学中、離れ離れとなっていた恋人のマルティーネ(オドレイ・トトゥ)とは、最後にはまたよりがもどりそうな感じもあったが、それから5年後の時代に設定されたこの映画では、マルティーネは、グザヴィエとは別の男を愛し、子供をもうけたらしい。が、その男は、いまでは、出て行ってしまい、二人は親友として付き合っている。
◆ストーリをいちいち追ってもしかたがないので、結論にはいる。要するにこの映画は、固定したパートナーを見つけられない、あるいは、少なくともこれまで見つけなかったグザヴィエの心の揺れを描く。彼の心が揺れ動いたのは、一つは、年老いた祖父(ピエール・ジェラルド)が、しきりに、「いつフィアンセに会わせてくれるんだい?」と言うこともあった。祖父が生きているうちにそうしてやりたい。あせった彼は、ある日、友人のイザベラ(セシル・ド・フランス)に頼んで、婚約者のふりをしていっしょに祖父を訪ねてもらう。彼女は、レズビアンで、ふだんはハイヒールなどはいていない。その彼女が、ワンピースを着て、転びそうなおぼつかないハイヒールの足で歩き、祖父のまえでグザビエとむつまじいふりをするが、ついつい荒っぽい言葉が出てしまうシーンが面白い。
◆このシーンで思ったが、フランス人でも、老人ともなると、生涯に伴侶は一人的な結婚観をいだいているのだろうか? グザヴィエの祖父がこの映画のいまで70歳代とすると、1930年代の生まれだ。ドゥルーズやガタリフーコーの世代だが、彼らは、家庭に関しては結構ラディカルな世代だった。まあ、彼らは「普通」の人たちではなかったが。いずれにしても、映画である一定のことが強調される場合は、映画のコンテンツとの関係よりも、映画が直面している「いま」との関係が介在していることが多い。つまり、いま、フランスでは、好きならいっしょになり、嫌になったら別れるといったカップリングのパターンが、修正されつつあるのではないかということだ。これは、ポストフォーディズムの多くの国で見れらる現象だ。
◆映画は半分夢の実現のようなところがあるからでもあるが、男が魅力的な女に会うと、すぐにベッドインしてしまう。そして、その場合、相手に魅力を感じてすぐセックス関係に入ったあと、そのまま持続的な関係になるのがパターンだ。たとえその関係が崩れるとしても、セックスをした結果、がっかりし、そのままつきあうのをやめてしまうような例は少ないのである。なぜだろうか? 現実には、こちらの方が多いような気がするのだが。この映画のグザビエも例外ではない。彼は、この映画のなかで、最低3人の女と寝るが、少なくとも、彼女らとのセックスには満足し、相手も同じようだ。
◆ヴァルセロの仲間にウェンディ(ケリー・ライリー)という女性がいたが、その弟ウィリアム(ケヴィン・ビショップ)は、ロシア人のバレリーナに恋をし、結婚することになる。彼は、一人の女性を「一筋に愛する」男の雛形であり、ふらふらしているグザヴィエのアンチテーゼとして設定されている。ウィリアムの結婚式に、彼の両親が来るが、二人はすでに離婚しており、息子の結婚式のためだけに同席した。つまり、この世代では、すでに長くない結婚のパターンが始まったいたわけだ。式と披露宴での両親のぎくしゃくしたシーンは、こういう関係へのさりげない批判が感じられる。ということは、前述したように、ウィリアムの結婚は、「新しい」のである。
◆グザヴィエというのは、70年代後半生まれ世代の典型なのだろう。こう一般化するのはナンだが、映画が一般化して描いているのだから、そういう言い方が許されるだろう。フランスの場合は、ポストMay 68 世代である。1968年の5月革命の余波が消えた時代に生まれ、70年代後半から80年代の資本の多元化の「恩恵」を受け、反抗を知らずに育った世代だ。フランスでは社会主義政権が成立したが、それは、情報と文化を取り込んだ新資本主義への出発だった。これは、フェミニズムの影響やマルチカルチャリズム、ベルリンの壁の崩壊などの影響で、女性や、東欧出身者の場合は若干違うのだが、パリジャンのグザヴィエの場合は、あまり状況から決定的な影響を受けなかったのではないか? だから、かえって、ヴァルセロナでの経験のような外国体験が意味を持つ。
◆この映画でも、女性たちはみなマイ・ウェイだ。グザヴィエがいまは友人としてのいい関係を保っているマルティーネ(オドレイ・トトゥ)は、環境問題に関心を持ち、子供をグザヴィエに預けて集会に行き、なかなか帰ってこない。グザヴィエは、彼女の誕生日のプレゼントを買いにいったKOOKAIで早速セネガル人の店員をくどく。彼女は、すぐに彼と寝る。彼女は、その後、彼に恋人がいると思い、さっと引く。じめじめしない。レズのイザベラ(セシル・ド・フランス)も、あっさり昔の相手をふり、新しい恋人を作る。つまり、男がいくら「終生のパートナー」志向になっても、女の方は、そうはなっていないのである。この映画は、そういう点を強調してはいないが、グザヴイエは、その顔の通り、いつもどこかズレているようだ。その分、女性は助けたいという気になるのかも。
(角川ヘラルド試写室/角川ヘラルド映画)
2006-03-28
●インサイド・マン (Inside Man/2006/Spike Lee) (スパイク・リー)

◆冒頭から、ズンズンという低音の響きとヒンズー語の歌詞の音楽が盛大に鳴る。これは、マニ・ラトナムのインド映画『ディル・セ~心から~』(Dil Se../1998/Mani Ratnam)のテーマソング(A・R・ラーマン)の一つ「チャイヤ・チャイヤ・チャイヤ」(Chaiyya Chaiyya Chaiyya)だ。この曲は、映画の終わりにも流れる。スパイク・リーがこのソングを使ったのは一つの目くばせである。
◆ハリウッド資本の映画が、娯楽装置としての機能を果たしながら、同時に政治的アクティヴィズムとの関係を維持し続けることが出来るかというチャレンジを、スパイク・リーは、決して忘れない。ドラマとしては、この映画は、若干普通とはちがう銀行強盗の全プロセスを描く。そのドラマはは、サスペンスとしても楽しめる。この映画が終わって外に出たら、前を歩く人が、「これから始まるっていうところで終わっちゃいましたね」と言っているのが聞こえたが、わたしはそうは思わなかった。話は、ちゃんと完結している。重要なのは、あなたが「銀行強盗」をするとき、あるいは何らかの形で警察と対峙するようなことになるときには必ず役立つであろう斬新ないくつかのノウハウをこの映画が教えてくれる点だ。そしてまた、この映画は、銀行強盗が、かならずしも金品の強奪のためだけでなくなされることもあるし、その「必要」があるときがあるということを示唆する。
◆銀行の金庫には、現金だけではなくて、いまの時代にはますます、さまざなな情報が格納されている。そのなかには、世間から(できれば)永久に隠蔽する必要からそこに隠されているものもある。そういうものを暴くことも、ある種の反権力活動であろう。この映画では、ダルトン・ラッセル(クライブ・オーウェン)をリーダーとするグループが襲った銀行の取締役会長アーサー・ケイス(クリストファー・プラマー)があるものを隠している。ニューヨーク市警の刑事キース・フライジャーと事件担当の警部ジョン・ダリウス(ウィレム・デフォー)は、当面、ただの銀行強盗だと思うが、アーサー・ケイスは、自分の銀行が襲われたとき、危機を直感する。そこで、彼が連絡をとるのが、凄腕の弁護士マドリン・ホワイト(ジョディ・フォスター)。フォスターが(けっこうノリノリで)演じる感じの悪い女弁護士は、市長に要求を出せば何でも通るような力を持っているという設定。あるシーンで、キース・フライジャーが、名刺を要求すると、「言っておくけど、あなたには、わたしの弁護士料は払えないわよ」と平然とした顔で言う。
◆さりげないショットのなかで、いまのアメリカでは、「イスラム系」の人間がいかに猜疑の目で見れらるかも描く。解放された人質の一人が、犯人の仲間ではないかと疑われ、警官になぐられるが、その顔を見た警官が、「アラブ人だな」と差別と警戒の目を向けると、その男は、「アラブ人じゃない。シーク人だ」と言う。シーク人は頭にターバンを巻いているが、彼は、ターバンをはずさせられたことに憤る。ところで、シーク人はインドにもいる。その人物は、インド系だったのかもしれない。そうすると、冒頭の「チェンヤ チェンヤ チェンヤ」との関係が気になってくる。
◆銀行に多数の人質をとってたてこもるというような事件が起きると、一個中隊くらいの警察が動員されるが、その指令基地となるのが、盗聴や監視装置を搭載したバン。そこにジョン・ダリウスが鎮座するのだが、犯人たちの動静をさぐる盗聴器から国籍不明の言葉が流れてくる。そこで、その声をバンの外に拡声器で流し、この言葉が何語かわかる者をさがす。その音を聞きつけてやってきた男の話では、アルバニア語だという。それは、アルバニアの反体制活動家の演説の録音なのだった。
◆絶対にお薦めの一作。
◆【追記/2008-02-16】「helpline」氏のブログに、以下のような(わたしには文章的にかなり意味不明の)コメント( http://d.hatena.ne.jp/helpline/20080211/p1 )があったので、無断で引用しておく――「粉川氏のエッセイは、なんかおかしいですね。粉川氏は、アメリカの「イスラム系」(と括弧でくくられたカテゴリ)にはインド人も含まれるから『ディル・セ/心から』を引用したのだと「インド人」にアクセントを置いてるんですけど(「シーク人はインドにもいる。その人物は、インド系だったのかもしれない。そうすると、冒頭の「チェンヤ チェンヤチェンヤ」との関係が気になってくる」)、『ディル・セ/心から』は、インド政府(ヒンドゥー教徒)がムスリムを弾圧していることを背景とする映画なのだから、「権力者によるムスリムの弾圧」という文脈を念頭において引用されているという解釈でいいのでは? アメリカ人が「イスラム系」という括りでムスリムもインド人も一緒くたにして差別している状況があるとしても、だからといって、『ディル・セ/心から』のヒンドゥー教徒とムスリムの対立という文脈を無視するのはどうなんだろう?(間違ってたら、ご指摘よろしくお願いします)
◆ここでは、わたしは、<『ディル・セ/心から』のヒンドゥー教徒とムスリムの対立という文脈を無視する>というより、そのことには触れていないので、上で「なんかおかしい」と言われても、困ってしまう。わたしは、アメリカにおける近年の差別状況を言っただけである。ただし、<『ディル・セ/心から』のヒンドゥー教徒とムスリムの対立という文脈>ということでいま考えると、スパイク・リーが「チェンヤ チェンヤチェンヤ」を使っているのは、そういう文脈を意識していたのかもしれない。<「粉川氏のエッセイは、なんかおかしいですね」>というところをもう少しわたしの文章の文脈にそって言ってくれれば、対応することができるかもしれない。
(UIP試写室/UIP映画)
2006-03-27
●雪に願うこと (Yuki ni negaukoto/2005/Negishi Kichitaro) (根岸吉太郎)

◆力のある役者をそろえたが、映画は凡庸である。せりふが「・・・た」「・・・た」と書き言葉になっていて、それを暗記し、口に出す役者がかわいそうになる。なんで、こんなせりふをはかなければならないのかという意識が役者たちにもあったはずである。佐藤浩市は、かなりの程度そういうせりふの単調さを回避している。ただし、それは、彼が演じる人物が、感情的に起伏が多く、せりふの抑揚の激しさでごまかせるからである。小澤征悦は、怒りの役で、同様に回避。が、草笛光子は、ほとんど活かされていないで、気の毒。
◆北海道の帯広。そのばんえい競馬場に伊勢谷友介の姿がある。彼は、競馬にかけ、あり金をすってしまったらしい。常連らしい山崎努は、もうけた金をこれ見よがしに勘定し、伊勢谷に話しかける。大声で声援を送り続けたあげくという設定だが、わたしは、山崎の声がかすれがちで、喉頭ガンにでもかかったのかという余計な心配をする。どうなの?
◆本当は訪ねたくなかった兄・威夫(佐藤浩市)のもとに転がり込んだ学(伊勢谷友介)を兄がやけにじゃけんにあつかうのが、不可解だったが、やがて、その事情がわかってくる。彼は、東京で貿易会社をたちあげ、薬のネット販売でいっときはもうけたが、消費者に死亡者が出て、薬事法違反に問われ、倒産寸前。会社設立に金を出した妻からも見放され、仲間(小澤征悦)は、彼の無責任を難詰する。
◆学は、ある意味での「ルーザー」だが、今様の「身勝手さ」を最初から設定されているキャラクター。貧しい生い立ちを隠して金持ちの家の娘と結婚するために「母親が死んだことにしてほしい」と兄に頼み、兄が怒り、以後ほとんど絶縁状態になっていた。いまさらおめおめと故郷にもどれる筋合いではない。ヴェンチャービジネスで一旦は成功するが、ネットで失敗するというのもいかにも今様。その意味では、学を伊勢谷友介が演じるのは、悪くないはず。が、それが全然活かされない。それも無理はない。「いまの30代」をこういうパターンでとらえるのが、すでにズレているのだ。
◆しかも、その一方に競争馬としては成績があがらず、廃馬になりそうな馬「ウンリュー」を置き、この馬と学との「交流」を通じて、彼が癒され、馬の方も周囲の期待に答えるという筋書きは、あまりに見えすいている。わたしなんか、馬であれ運動選手であれ、彼や彼女らが勝つことに自分を同化することなどできないので、こういう作劇には特に感動できない。
◆わたしは、この映画で見る「ばんえい競馬」にスリルを感じることが出来なかった。おそらく、映画ではただただスローに見える競技も、現場で見れば、スリルがあるのだろう。ひずめのがっちりした1トンを越す競争馬が数百キロのソリを引くのだから。しかし、映像からは、そうした迫力は伝わって来ない。やたら、馬の白い鼻息が盛大に広がるワンパターンの映像をくりかえし、わたしのような「ばんえい競馬」の素人を驚かすことができない。
◆もし、世代論的にいまの30代(大体1970年代前半期に生まれた世代)を問題にするのなら、彼や彼女らのどこかにある「労働の拒否」という発想を押さえなければならないのではないか? 彼や彼女らは、日本のバブル経済のなかで、働かないで済めばそれに越したことがないという「労働の拒否」の文化を暗黙のうちに身につけた。これは、いまだと批判の対象になるが、1970年代のイタリアで、「労働の拒否」が労働運動の重要なテーマにまでなったことを忘れてはならない。それは、強制される「労働」から創造的な労働としての「遊び」へというマルクスが本来考えていた発想を引き継いでいた。日本では、せいぜい「時短闘争」のような形でしか、「労働の拒否」をめざす労働運動はついに出現せず、「労働の拒否」の文化は、自覚されないまま「フリーター」のなかに身を隠した。
◆現実には、いま、アイデア一つ思いついて巨額の金を得たり、金融や情報の操作で富を気づくことがあたりまえになり、そういうことを「本業」とする階級が生まれているにもかかわらず、より多くの人が「働かないでいられるのなら、それにこしたことがない」ということは是認されるどころか、悪とみなされるようになってしまった。いま高まっている「フリーター」批判は、「労働の拒否」を単なるぐうたらで無責任な生き方として単純化し、その能動的な側面を葬り去るものである。「働かない」ということは、ぐうたらで、寄生虫になることとはかぎらない。強制された仕事をいやいややることを拒否し、もっと自発的なことをやるということだ。
◆学が起業したサプリメント販売の会社は、この映画では、「虚業」と見なされている。そのいっぽう、大地にしがみつき、生き物と苦闘する厨舎は、「実業」だ。しかし、こういう単純な図式ではダメなのではないか? 学には、故郷があるが、多くの「ルーザー」たちに帰るべき故郷はない。
◆この映画の作りなら、テレビでよかったのではないか? この映画で、威夫が責任者になっている厨舎のスタッフ(山本浩司)と学が浴槽につかっていると、やはりスタッフの湯原(出口哲也)の姿が脱衣所で見え、次の瞬間いきなり浴槽に入ってくる。これは、実にテレビ的だと思う。偏見丸出しで言うと、テレビの入浴シーンというのは、だいたいがいいかげんだ。瑣末なことかもしれないが、普通、銭湯的な共同風呂では、風呂に入るまえに尻や局部を洗う。だが、テレビの場合は、脱衣場で服を脱ぐシーンがあり、前を桶などで押さえ(これは、表現規制の問題)、そのまま浴槽に直進し、入ってしまう。おいおいケツはどうした、と言いたくなるが、だいたいこういう感じだ。おそらく、この分では、それが映像の外でも普通になってしまうかもしれない。え、銭湯でケツを洗わないのが普通だって? 最近、銭湯に行っていないから、知らなかった。
(メディアボックス試写室/ビターズ・エンド)
2006-03-22_2
●嫌われ松子の一生 (Kiraware Matsuko no Issho/Memories of Matsuko/2006/Nakajima Tetsuya)(中島哲也)
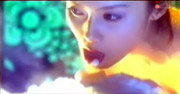
◆ひらめきのある天才肌の映画という印象を持ったが、長く山にキャンプした末に出会った山女をに惚れるような印象かもしれない。が、いずれにしても、テンポとタッチとユーモア感覚が新鮮であり、また、甥が叔母・松子の人生の足跡をたどるという記憶のドラマの持つ魅力があますところなく表現されていたと思う。
◆『電車男』や『疾走』にくらべれば、中谷美紀が最高の適役であったかどうかはわからない。比較をすれば、適役度としては、『力道山』のレベルだが、中谷は、例によって与えられた枠のなかで最高の演技をしている。中谷が演じる松子のまえに現われては消える数々の男たちを、宮藤官九郎(小説家)、武田真次治(ヒモ)、荒川良々(床屋)、伊勢谷友介(元教え子でヤクザになる)等々のクセのある俳優たちが楽しみながら(?)アンサンブルプレイを演じている。女たちも生き生きしている。わたしは、松子がソープ嬢をしていたときの同僚を演じたBonnie Pinkにいたく惚れた。
◆松子は、幼いとき、シンデレラ的な人生を夢みる少女だったが、病弱の妹(長じた役を市川実日子が演じる)ばかりかわいがる父(柄本明)の関心を得るために唇を突然突き出すのが癖になってしまう。緊張するとその身ぶりが無意識に出てしまう。それがたたって、小学校の音楽教員の職を失う。以後は、まさに絵に描いたような「転落」の人生。小説家志望の男の虐待にあけくれる毎日と劇的な別れ、その友人との不倫と破局、ソープ嬢になり、店のトップにまで上りつめるが、ヒモを殺して、刑務所入り。殺人を犯して逃亡生活をしていたとき優しくしてくれた床屋は、8年後に出所したときには、別の女と絵に描いたような「しあわせ」な家庭を築いていた。以後、荒川沿いにある安アパートで「引きこもり」と「ホームレス」的(変な表現ですが)な生活を続け、最後は、河川敷で夜遊びする子供たちに撲殺される。すべてが、スポーツ紙や週刊誌のページに登場する「絵に描いたような」パターン的出来事の羅列なのだが、それが、コミックスをポップアートに機能転換してしまったリキテンシュタインの絵のように実に新鮮なのだ。
◆その点で、松子を最後までサポートしようとするヤクザの姉御的雰囲気の元親友を演じる黒沢あすかが、若干浮いて見えたのは、彼女が「普通」のヤクザ映画に出てくる「姉御」のままだったからだろう。それを一段ポップ化する操作が彼女の演技と演出にはなかった。
◆パートごとに字幕をつけたり、音楽を多彩に変える手際も見事。刑務所のシーンでBonnie Pinkが歌うソングは、マドンナの「アメリカン・ライフ」の放映中止になったビデオクリップ的。まあ、とにかく楽しめる。
◆ここで、「人生ってもんは・・・」というような論を展開するのは野暮の骨頂。むしろこの映画から「人生」的なものを語るとすれば、一度会ったかも知れないが、記憶にない叔母に興味を持ち、調べはじめる甥(暎太)の行動だろう。その発端は、松子が残したアパートの一室にびっしつつまったジャンクのような遺品を甥が手にし、その持ち主に興味を持った「アーキヴィスト」(archivist)的な関心と情熱だ。これは、『僕の大事なコレクション』の主人公の関心と一脈通じるものがある。そして、わたしに言わせれば、いまの時代の「愛」というものは、そういう歴史的・アーカイヴ的想像力によって可能なのであり、とりわけいま、「愛」のそうした転換が起きている。
(東宝試写室/東宝)
2006-03-22_1
●ココシリ (Kekexile/2004/Chuan Lu)(ルー・チューアン)

◆タイトルになっている「ココシリ」というのは、中国青海省チベット高原の高山地帯のことだという。ここに棲息するチベットカモシカは、1970年代には100万頭いたが、乱獲する密猟者のために90年代には1万頭に激変し、1993年、それを憂う有志たちが、自腹でパトロール隊を組織し、命をかけて密猟者と闘った。このことが中国のメディアで取り上げられ、それがきっかけになって、1997年に初めて、ココシリ国家級自然保護区管理局が出来、カモシカの保護が軌道にのるようになる。映画は、そのパトーロール隊員が密猟者に殺されるという事件からこの活動に興味をいだいたいてはるばるやって来た中国人の記者ガイ(チャン・レイ)を設定し、彼が厳しく、危険なパトロールに参加するという形態で、彼の目からすべてが描かれる。いわば、活動しながら記録する「メディア・アクティヴィズム」の記録のような映画である。
◆しかし、そのスタイルは、密猟を見張っている監視員が密猟者に殺され、その殺人者を追う、リータイ(ディオ・ブジエが力演)の一隊との闘いをドラマチックに描くもので、「実話」であるという但し書きがなければ、犯罪サスペンスに見える。それは、ドキュドラマにしては、出演者がみな独特の個性にめぐまれており、また、酸素の薄いココシリ高原での危険を冒したロケといやがうえにも映像に奥行きをもたらす環境のためでもある。おそらく、民族的なものもあるのだろう、久しく会っていない隊員同士が再会したときに身ぶりは、「ハグ」どころではなく、たがいに飛びつき合うのである。食料品や資材を調達に行った隊員が、砂地の「あり地獄」のようなものに飲まれるシーンもすごい。空をびっしり埋めつくしているかのように光る星の光景も実に映画的だ。
◆ボランティア活動であるがゆえに、隊員が密猟者との闘いで負傷したとき、その隊員を入院させるための費用を得るために、密猟者から没取したカモシカの毛皮を密売者に売らなければならない屈折とか、命をかけて闘わなければならないために、家族にとっては、旅立つ男立ちとの別れが最後の別れになるかもしれないという不安、生活のために密猟をせざるをえない者たちと、それを食い物にしているマフィア的な中核集団の確信犯的な冷酷さなど、実際にあったであろう事実を活写しているはずのシーンもあるが、観客としては、非常に出来のよいサスペンスを見ているという印象をぬぐい去ることができない。それは、別に欠陥ではないが、若干、考えさせるものを残す。
◆鳥葬のシーンがある。死体をナタでばらし、禿げ鷹が食べ易いサイズにする。その一方で、密猟者たちがカモシカの皮を剥ぐシーン、パトロール隊が食料の肉をさばくシーン。これらを見ていると、生き物の肉体と自然との一体感を感じる。その意味では、パトロール隊が自分たちの身体を張って密猟者と闘うのは、密猟が、[生→死→ばらし→鳥が食う]という自然のサイクルのバランスを崩すからだろう。たしかに、高原にちらばるおびただしいカモシカの骨は、カモシカの肉が禿げ鷹や他の動物たちの腹を肥やしたであろうことを示唆しはするが、それは、動物たちにとっては「過食」であり、自然なことではない。そして、そうした密猟から生じる利益の大半はマフィア的な組織のトップに独占され、密猟者の手にはわずかしか行き渡らない――これも自然の原理に反する。それは、資本主義の原理としれは「自然」であるとしても。
(ソニー試写室ブルー/ソニー・ピクチャーズ・エンタテインメント)
2006-03-17
●フーリガン (Hooligans/2005/Lexi Alexander)(レクシー・アレキサンダー)

◆わたしは、スポーツには興味がないし、ルールのある集団にくみするのも嫌いだから、フーリガンのように、身体をはって他の派閥と闘うなどということの意味も理由もわからない。となると、わたしは、この映画を評価する資格がないということになるが、映画や文学で描かれる戦争や人の死が「現場」のそれらとは異なるように、フーリガンも、映画に描かれることによって、別の次元を獲得する。フリーガンは、映画というわたしでもわかる「参照体系」(referential system) のなかに引き込まれ、映画のコンテキストのなかでの判断や分析が可能になる。
◆このことは、映画と「現実」とは違うといったようなことではない。「ナマの現実」などというものはなく、映画ではなくても、ただ視線を向けるというような知覚行為のなかでも、あなたやわたしは、(仮に認識論的違反をして)「ナマの現実」と言っておくものを「別の」「参照体系」に移して認識しているのである。と偉そうなことを書いたが、ここで使われている引用符は、引用とは無関係で、みなわたしの独断だ。わたしの文章では、「 」は文字を太字にする代わりにもつかわれる。人も動物も、「もの自体」を自分の住み慣れた「水」に移してから認識するのであり、だから、フーリガンも、映画というわたしが住み慣れた水のなかに持ってこられると、何かを語ることができるということだ。しかし、それは、ある意味で勝手な意見であり、客観性などというものは全くない。
◆だが、この映画を見て、ここで描かれるフーリガンに魅力を感じたかというと、全くそうではなかった。アホやなあという印象しかおぼえなかったということは最初に言っておこう。わたしは、アメリカからやってきてたまたまフーリガンに入ってしまうこの映画の主人公マット(イライジャ・ウッド)には同化できない。ピート(チャーリー・ハナム)が率いるフーリガンのメンバーは、徒党を組んで歩きながら「ユナイテッド!」(団結した)と声を合わせて叫ぶ。最初、集団で殴りあうなどということをやったことのなかったマットも、最後には、このスローガンを愛するようになる。が、わたしに言わせれば、「ユナイテッド」は、「アメリカ合衆国」(United States)も「国連」(United Nations)も、そして同名の飛行機会社も落ち目であって、「ユナイト」の時代は終わりつつある。というのも、「ユナイト」には、uni (単一の)という含意があり、「複数多数性」へ向かおうとしている(だから「マルチチュード」だ)今日、こんなすローガンを唱えても、どうにもならないからである。とはいえ、この映画は、「ユナイト」志向の集団性(かつてサルトルが「融溶集団」と呼んだもの)を単純に肯定しているわけではない。むしろ、それを余すとこなく描きながら、その限界と宿命を示唆してもいる。
◆マットがピートのフリーガン・ファーム(フーリガンのグループの単位を「ファーム」というらしい)に惹かれた理由は、割りあい月並みだ。彼は、ハーバード大学でジャーナリズムを専攻し、「パパラッチ時代のジャーナリストの役割」という論文を書いて卒業間近だったのに寮の同室の学生の罪をかぶって退学処分になる。部屋からその学生のドラッグが見つかったのだが、富豪ヴァンホール家の御曹司とかいうその学生は、自分はエリートの道を歩まなければならないからして罪をかぶってくれと1万ドルを渡して頼んだのだった。マットは、その金を最終的に受け取らないのだから、なぜそんな役割を負ってしまったのか、理解に苦しむ。ドラマの筋立てとしては、ありがちだが、考えてみると、よくわからない。ハーヴァードあたりに行くと、そういう不可解なことがあたりまえなのだろうか?
◆マットがそれからロンドンに来る理由もあまりはっきりしない。とにかく、彼は、イギリス人と結婚している姉のシャノン(クレア・フォーラニ)を頼ってロンドンに来る。バンク・ストリートの地下鉄駅で彼を待っているシャノンは、見るからにスウィートな女性。その感じは、キャラクターがそうなっているからであると同時に、それを演じるクレア・フォーラニの性向とも関係があるのではないか? シャノンという女性は、著名ジャーナリストの父親とうまくいかなくて、母の死後、アメリカを捨ててロンドンに来たらしい。どちらかというとタフガイ的な感じの夫スティーヴ(マーク・ウォーレーン)に愛されて家庭を守っているという感じの女性。つまりアメリカの典型的な女性よりも「従属的」で、その分「スウィート」なのだ。あとで知ったが、俳優クレアの父親はイタリア人だとういう。そのイタリアン的部分が、シャノンの「スゥイート」な部分の表現に大いに役立っているように思う。家庭でも組織でも、「ユニティ」度が強くなればなるほど、そのなかで従属的な位置にいる人間は、不自由や理不尽な要求をじっと堪え忍ばなければならない。その非従属性から生まれる情感や美や色気というものがあるが、シャノンは、そういう要素を、美しいがどこかに悲しさを秘めた表情のなかに隠し持っている。
◆この映画は、キャスティングが抜群にすぐれている。シャノン/クレア・フォラーニもそうだが、フーリガンのリーダー、ピートを演じるチャーリー・ハナムの場合もそうだ。「この役を受けるまで、サッカーの試合には言ったこともないし、テレビで観たことすらなかった」というハナムだが、フリーガンのためには命を落とすことも辞さないような信念、聡明さと粗暴さ、街のチンピラかパンク風でありながら小学校の教師であるというアンバランス・・・単純そうで複雑なピートという人物を実にリアルな存在感で演じている。『コールド・マウンテン』で悪党の三下みたいな役を演じていたときのハナムにもその片鱗があらわれていたのだろうが、大いなる飛躍である。
◆キャスティングの妙では、グループの「ユダ」役を演じることになるレオ・グレゴリーも、ハードな組織には必ずいる抑圧と偏見のかたまりのようなキャラクターをリアルに演じている。自動車修理工場を経営しながらチャーリーたちとは敵対するフーリガン・ファームのリーダーをしているトミーを演じるジェフ・ベルも、なかなかいい。わたしはこのトミーの風貌を見て、わたしの友人のジェイムズ・スティーヴンスを思い出した。彼は、非暴力の人だが、90年代のロンドンでネットとミニFMのフリースペース「バック・スペイス」を開き、ロンドンのネットアートや電子的なアンダーグラウンド・カルチャーのリーダー的存在だった。「バック・スペイス」の場所は、いま、スターバックスに接収され、彼は拠点をグリニッチの港湾地区に移した。そこでの対話がアップされているので、聴いてみると面白い。彼も、この映画のなかのフリーガンたちと同じように「サッカー」ではなく、「ソッカー」と発音するはずである。
◆この映画を見ながら思ったのは、民主主義とか平等とかいうが、競争という原理が存在するかぎり、フリーガンのような「ユニティ」集団はなくならないし、警察や軍隊は存在し続け、殺し合いもとまらないだろうということだ。当然、強者と弱者の差、男が女を支配すること、人種や党派やさまざなレッテルでセクトを作る閉鎖性と排外主義はなくならない。だが、この映画は、そうした「ユニティ」集団や「ユニティ」社会を礼賛しているのではなく、それを存在論的に問い、その「宿命」を問うてもいる。はたして、それは「宿命」なのか、と。
◆わたしは、よく知らないので仮設的に問うてみる。スポーツは、競争原理で動いている。スポーツがあるかぎり競争はある。競争があるかぎり、戦争もある。が、支配者は、戦争はするが、自分の命をかけては闘わない。支配者は一兵卒にはならない。スポーツは戦争ではなく、戦争の代償でもある。が、支配者はスポーツのスポンサーにはなるが、その競争の第一線に出ることはほとんどない。スポーツにも権力的な階級制があるが、その階層は、社会の底辺に開かれている。あなたが抜群の運動神経の持ち主ならば、世界的な運動選手の地位に上りつめる可能性があたえられる。いいかえれば、スポーツは、非権力者が権力者の顔をしないで権力に馴染み、その一部が権力機構の一員として選別されるための装置である。権力が存在するかぎりスポーツは存在する。よって、権力にさからう者は、スポーツを素直に受け入れることはできない。スポーツ会場での観衆の歓声と熱気は、権力の礼賛に比例しているように思えてならない。
(映画美学校第2試写室/ワイズポリシー)
2006-03-16
●プルートで朝食を (Breakfast on Pluto/2005/Neil Jordan)(ニール・ジョーダン)

◆ニール・ジョーダンに瞠目したのは、『モナリザ 』(Mona Lisa/1986)でだった。その折、けっこう入れ込んだ映画評を『キネマ旬報』に書いたが、近年の『ことの終わり』も『ギャンブル・プレイ』もあまりぱっとしなかったので、今回こそはと思って見た。う~ん、前述の2作よりはいいが、『モナリザ 』にはおよばない。いや、こういう言い方をすると、作家の方は、「おまえ、何にもわかっちゃいねぇな」と言いたくなるだろう。作家にとっては、最新作が一番いいはずなのだ。むろん、若さの勢いというのはあり、初期の作品からどんどん後退してしまう作家もいる。(それにしても、リュック・ベッソンの凋落ぶりは何でだろう? ビジネス家としてはますます成功なのだろうが、作品は、初期の『最後の戦い』や『サブウェイ』を越えられない)。おそらく、ニール・ジョーダンの場合、故郷のアイルランドへのこだわりがあり、それが、(アイルランドを頭でしか知らない)わたしなどには、ピンとこないのだろう。『モナリザ』は、アイルランドを舞台とはしていなかったので、「一般受け」したのだ。
◆しかし、前言をひるがえすようだが、ジョーダンの映画の問題(わたしにとっての)は、アイルランドと彼とのイディオシンクラティックな関係にあるのではないように思う。この映画が描くアイルランドのシーンは、映画としても生き生きとしている。そのカソリック的背景の屈折の描写は、悪くない。が、舞台はすぐにロンドンに移る。ロンドンのシーンもそう悪くはない。じゃあ、何なんだと言えば、わたしが問題にしたいのは、このアイルランド出身の主人公の、1960年代から今日までの「遍歴」を、時代時代の音楽をまぶしながらビルドゥングスロマン風に描くときの時代認識の軽さである。60年代のドラッグカルチャーとフリー・ライフ、70年代のIRAやグラム・ロック等々、時代を「象徴」する風俗が呈示されるが、すべてが百科事典の「教養的」描写にとどまっている。そんな「象徴」サービスなどしなくても、時代の変化は描けたであろうし、その方が、主人公が活かされることになったのではないか?
◆神父リーアム(リーアム・ニーソン)とメイドのエイリー(エヴァ・バーシッスル)とのあいだの隠し子として生まれたらしいパトリック・ "キトゥン" ・ブレイデンは、教会の近くの家で養子として育てられるが、幼いときから女性になることを夢み、トランスヴェスティズムにのめり込む。ゲイというより「おかま」になる道を進んだわけである。元来保守的なアイルランドでは、世界中で「フリー」が流行になりはじめた60年代の後半でも、タブーであり、キトゥンは、ロンドンに脱出する。
◆このへんは、ちょっと『タブー』に似ているが、この映画には、『タブー』のような毒がない。むしろ、軽く、「明るく」がこの映画の売りで、その点では、キトゥンを演じるキリアン・マーフィーは、最高の演技をしている。特定の時代のアイルランドという限定がありながら、キトゥンが学校で神父の教師を誘惑しても、ハレンチな作文を書いて懲罰を受けても、笑って見ていられるようなスタイルがこの映画の基本にあり、そのへんが、この映画の評価の分かれ目にもなる。
◆ある意味で、キトゥンには、トリックスターや道化の要素が入っている。ところでいまどき「トリックスター」などという言葉を使うと、いまではゲームの名前にもなって一人歩きしているので、わたしがこの語を使う真意が通じないかもしれないので、若干解説をしておく。この語は、英語辞書的意味では「詐欺師」や「ペテン師」を意味するが、1960年代前後に、文化人類学や(のちに「カルチャラル・スタディーズ」と呼ばれるようになる)諸々の文化論で特別な意味を付与され、よく使われた。日本では、山口昌男氏がそのタームの普及に熱心だった(『本の神話学』や『道化の民俗学』を参照)が、要するに、さまざまな境界線を容易に飛び越え、異文化や異なる世界を「媒介」してしまう主体のことである。文化の変化には、そういう「トリックスター」(「文化英雄」とも訳された)の存在がかならずあり、逆に、時代が硬直しているときには、めぼしい「トリックスター」があらわれないのである。また、たとえ現われても、すぐに抹殺されてしまうのだ。そういえば、堀江貴文は「トリックスター」のはずだったが、それを許せない時代だったので、隠蔽されてしまった。
◆閉塞した日本の状況を考えたら、ふと、アイルランドへの想像力が起こった。アイルランドにこだわるニール・ジョーダンとしては、この映画で、アイルランドの保守的な世界に一匹の「トリックスター」を解き放ってみるというねらいがあったのかもしれない。そういえば、冒頭、大きな赤い帽子をかぶったキトゥンが、乳母車にやや色の濃い皮膚の幼児を乗せて「おかま」身ぶりで歩く姿は、いかにも「トリックスター」的でいい。このシーンは、「現代」で、ここから60年代にバックし、ふたたび「現代」に返る。子供のころから、一貫して「トリックスター」だったキトゥンは、成長して、母探しの旅に出るが、この母探しも、「徳光&安住の感動再会 "逢いたい!" スペッシャル」のような涙路線ではなく、最初からむしろ「お笑い」路線に設定されている。彼(ないしは彼女)が探す「母」は、最初から「異化」されている。というのも、キトゥンは、自分の母が、女優のミッツィ・ゲイナーそっくりの女性と信じ込んでいるという設定だからである。最初の方の3人称表現ですでにその「実母」の姿を見てしまっているわれわれ観客としては、キトゥンの母探しを「涙ながらに」見ることはできない。
◆しかし、どのみち「異化」されているとはいえ、彼(ないしは彼女)が、その旅のさなかで見せる「男」たちとの出会いは、けっこういい感じに描かれていた。ヒッチハイクしたワゴン車のなかで、バンドリーダーのビリー・ハチェット(ギャヴィン・フライデー)に出会い、愛がめばえる。これが、キトゥンにとって、音楽世界への入口になるが、むしろ、彼(ないしは彼女)は、「ビリー・ハチェット&モホークス」バンドのなかに異質なものを持ち込むことになる。トリックスターは、こうして、二つの世界を「媒介」し、既存の世界を変革することもあるが、多くの場合は、既存の世界から追放される。ただ、既存の世界にトリックスターが闖入したことによって、既存世界の、普段は見えない要素があらわになる。ビリーとの出会い以後、IRAの話が出てくるまでのくだりは、まさに、キトゥンのトリックスター的機能が躍如する。
◆手品師バーティ・ヴォーン(スティーヴン・レイ)との出会いは、まさに、キトゥンがバーティの舞台を手伝い、道化/トリックスターとしてふるまうという点で、最も「しあわせ」な時期だったかもしれない。が、トリックスターは、持続する「しあわせ」のなかで生きることはできない。この場合は、キトゥンをバーティから引き離すのが、幼友達のチャーリー(ルース・ネッガ)という黒人女性であるところが面白い。チャーリとは10代からのつきあいで、彼女が同じ仲間のアーウィンとカップルになってからも、ずっと友情をたもってきた。そういうチャーリーにとっては、キトゥンが「道化」にさせられているのは、見るに忍びなかったのだ。
◆道化やトリックスターは、いつも、自分が異世界との媒介役をするように運命づけられていることを知らない。だから、ときには、彼や彼女らは、既存の世界から利用されたり、その犠牲になったりしているように見えることもある。アーティスト志望であるが、「普通の人」であるチャーリーには、キトゥンがそういう役回りをさせられていると映った。これは、両方の世界を見てきた観客にとっては、残念に思える。キトゥンは、どのみち、「普通」の世界には生きられないのだ。スティーヴン・レイは、このへんの屈折をなかなか微妙に表現していた。
◆では、キトゥンは、トリックスターとして、何を変えたのだろうか? チャーリーの彼氏のアーウィン(ローレンス・キンラン)は、IRAに入って、仲間に殺される。チャーリーは、彼の子供を身ごもっている。そんなとき、ロンドンのピープブース(覗窓)で働くキトゥンのもとへ、「父親」があらわれる。このシーンは、教会の懺悔室を裏返した形になっていて、面白い。そして、最終的にこの「父親」は、自分の「息子」への責任を果たし、アイルランドの保守的な社会では許されない共同生活を始めて、教会を焼かれることになる。しかし、教会という保守の牙城のテーブルが、つかのまであれ、「プルートでの朝食」つまり「冥王星」(pluto)=既存社会の果て、極限にある理念的現実での朝食が実現したことにはかわりがない。
◆映画とは関係ないが、ロンドンには Pluto Pressという出版社があり、1960年代末から今日にいらるまで、「革新」的な書籍を出してきた。わたしは、ここから出た John Downing: The Media Machine (1980)を著者からもらい、一読して深い影響を受けた。この本との出会いがなかったら、自由ラジオへのわたしの関わり方は変わっていたと思う。その意味で、"pluto"という語は、わたしには、「冥王星」よりも、Pluto Pressを真っ先に思い起こさせる。
◆この映画では、チャプターのあいだで小鳥が登場し、短いコメントを入れる。つまり、この映画の全般的視点は、小鳥なのだ。
◆アイルランドでも、朝食は、一日の食事のうちで重要な位置をしめる。最初の方で、ニーアム神父が、牛乳、トースト、卵、ベーコンの朝食をうまそうに食べるシーンが見える。だから、問題は、その朝食をどこで(既存の社会環境のなかでか、それとも理念的な――たとえつかのまの――場でか)食べるかが問題なのだ。
(東京国際フォーラムD1/エレファント・ピクチャー)
2006-03-15
●STAY ステイ (Stay/2005/Marc Forster)(マーク・フォースター)

◆配給会社の要請で、「エンディングについては触れないよう」にということなので、中国のことわざを紹介する。それは、「一炊の夢」とか「邯鄲の枕」というやつだ。知ってますよね。唐の時代に、道士の呂翁(りょうおう)が、邯鄲の宿で廬生という少年に会う。少年は、呂翁から枕をもらって眠る。すると、さまざまな人生経験をした夢を見る。が、目が覚めたら、宿の人がたいていた黄梁(こうりょう)の飯がまだ炊き上がらないつかのまの時間だった。この場合、少年は夢のなかで栄達をはかり、そこから、「一炊の夢」とは、人生の栄華のはかなさを言うが、この映画の場合は、栄華とは関係ない。複雑そうで、話は簡単。人は死ぬまえに一生の記憶が走馬灯のように展開するという、本当か嘘かわからない「通念」も動員している。
◆しかし、考えてみると、映画というのは、「一炊の夢」であり、「走馬灯」の幻影なのではないか? 問題は、その見せ方なのだから、「エンディング」に触れようが、触れまいが、大して関係ないのではないか? 今日、寿命は予測可能になり、ガンなどにかかれば、大体予測通りに死期を迎えるから、「エンディング」がわかったらドラマ=「人生」がつまらないといった観念は捨てるべきだろう。むしろ、「エンディング」を、そのドラマを見る(人生を生きる)以前に明確に認識し、そのうえでどう見るか(生きるか)を考えるというのが今様なのではないか? つまり結果がわかっているかどうかよりも、プロセスが問題なのであり、そして映画の場合には、そのプロセスが「夢」であるか「現実」であるかはどうでもよいということが加わるのである。「ネタばれ」禁止主義の人にはあえてこのように挑戦しておく。
◆こう書いてふと気づいたが、「ステイ」(stay) というタイトルは、「とどまる」、「延期」するという意味だが、何に「とどまり」、何を「延期」するかといえば、それは、プロセスをなのだ。ある出来事(それが「エンディング」で示される)が起き、そのプロセスを映画の時間に「延期」し、その時間のなかに「とどまる」体験を観客にさせるのが、この映画なのだ。
◆「エンディング」は書かないでというので、冒頭の方のシーンを明かしておくと、高速のトンネルの中のような場所で車が燃えている。衝突事故か、自爆テロか? そのかたわらに男(ライアン・ゴズリング)が座り込んでいるが、しばらくすると、立ち上がり、亡霊のように歩き出す。すると、ゴズリングの顔が「融解」し、ユアン・マクレガーの顔になって、ブルックリン・ブリッジを渡り、マンハッタンのオフィスに来る。この「融解」が何を意味するのかは、(「エンディング」に触れることができないとすると)映画を見て、自分で考えてくださいと言うしかない。
◆この映画では、本屋のドアが開くシーンがバスのドアが開くシーンへ「融解」するとかいう風に、フレームに窓外の風景が映っており、カメラが(ノーカットであるかのように)そのままズームすると、別の時空に飛び移っているといったトリックが多用されている。それは、なかなかスタイリッシュで、魅力的だ。そういうカットを見ることが、この映画の楽しみでもある。「ネタばれ」の責任を回避するためにプレスから引用する。「例えば、サム[ユアン・マクレガー]とヘンリー[ライアン・ゴズリング]がコロンビア大学に新しく建造された、ガラス張りのモダンな建物を歩いているワン・カットのシーンの中で、突然ふたりはブロードウェイ195番地[旧WTCに近いBroadwayとDey streetの角]にある19世紀後半のフランス風建造物であるATT社の大きなイオニア式円柱の間に移動する」([ ]内はわたしの追加)。
◆プロセスということで言うと、この映画の「モラル」は、意外と古い。精神科医のサムは、元患者で恋人だったライラ(ナオミ・ワッツ)に負い目を感じている。ヘンリーは、両親に負い目を感じている。ヘンリーは、サムの患者になり、21歳で自殺することを予告する。サムは、それをとめようとするが、両人を媒介するのが、ボブ・ホスキンスが演じる盲目のレオン博士である。ヘンリーは、この人を「父」と思いこんだりもする。レオン博士がソニー・ロリンズのLPを持っているのは、何を意味するのか?
◆ナオミ・ワッツは、ずっとよかったのに、『ザ・リング2』で安売りをしたが、『キング・コング』で回復、そして、今回は、さらによくなった。当然この映画は、ナオミ・ワッツが出ている『マルホランド・ドライブ』や『21グラム』を意識している。さらに、『リチャード・ニクソン暗殺を企てた男』とも、一脈通じるものがある。
(フォックス試写室/20世紀フォックス映画)
2006-03-10
●ジャケット (Jacket/2005/John Maybury)(ジョン・メイブリー)

◆タイトルの「ジャッケット」は、日本語では「上着」の意味だが、原題は、最初から「拘禁服」(拘束衣)を指す。精神病院で暴れる患者に着せる服のことである。これは、英語圏ではすぐにわかるだろうが、日本語で「ジャケット」と言われて、すぐに「拘禁服」のことだとわかる人はそう多くはないだろう。映画のなかで、湾岸戦争の帰還兵のジャック・スタークス(エイドリアン・ブロディ)が着せられる拘禁服のことを「jacket」と繰り返し言うので、映画をみているとすぐわかるわけだが、英語圏の人は、エイドリアン・ブロディが台にベルトで拘禁されている宣伝写真を見て、タイトルとの関係がすぐわかる。それをわかって映画館におもむくのと、映画を見て、ああと気づくのとでは、映画を見る姿勢が全然ちがってくるだろう。
◆最初、湾岸戦争を批判するようなニュアンスを含んだ映画かと思ったが、見終わって、これはただの「タイムトラベル」映画じゃないかという、失望感に襲われたが、ブロディもキーラ・ナイトレイも悪くないのと、絵柄がいいので、見て損はしないだろう。が、この手法とテーマなら、エイドリアン・ラインの『ジェイコブス・ラダー』(Jacob's Ladder/1990/Adrian Lyne)ぐらいまで行けたのではないか? こちらは、似たようなテーマをあつかいながら、ベトナム戦争にかり出された兵士の戦場での危機的な意識と帰還しても残る悪夢とを、錯綜した時間のなかで描き出し、インスパイアー度の高い作品だった。
◆ついでに書いておくが、『ジェイコブス・ラダー』というタイトルも、日本では、すぐには意味がわからない。「ジェイコブズ・ラダー」(「ス」でなく「ズ」)と表記してくれれば、少しわかるかもしれない。「ヤコブの梯子なら、もっとわかりやすい。英語なら、「ジェイコブ」(Jacob)とは、日本で「ヤコブ」と言っている、聖書でおなじみの名前である。主人公ジェイコブ・シンガーの名前は、聖書の「ヤコブ」にかけてあるのだ。そして、「ヤコブの梯子」といえば、「創世記」に出てくる、ヤコブが夢で見た天国から一条の光のよう下りてくる「梯子」のことであることもわかる。そのうえで、この「梯子」(ラダー)と、政府が兵士にあたえるために開発した幻覚剤との名がかけあわされていることを知れば、その皮肉が際立ってくる。
◆『ジャケット』のジャックは、1991年の湾岸戦争で重傷を負い、1年後にヴァーモントに帰還する。殺風景な原野のかたわらにある道路で1台のエンコした車に出会う。車にはアル中らしい母親とその娘がいる。彼は、その娘ジャッキーに戦地から持ち帰った「認識票」をあげる。それから、彼は、通りがかりの車に乗せてもらい、カナダへ行こうとする。が、その車は、やがて、パトカーに検問される。気づくと、車の男と警官が地面に倒れており、ジャックは、警察に連行される。裁判ののち、彼は、病院送りとなり、ベッカー医師(クリス・クリストファーソン)の「治療」というより人体実験を受けることになる。それは、毎日、拘禁服を着せられ、ロッカーのような「カプセル」状の「ベット」に収納される。
◆この「ロッカー」は、ジャックの時間のスウィッチャーの機能を果たしており、そのなかで時間が15年スウィングする。が、このへんは、あいまいにされており、彼をめぐって15年の幅をもって展開する時間が、単にこの閉ざされた「子宮」的空間のなかにいるときの幻想であるのか、それとも、逆転した時間なのか、それとも、時間というものがいつもそういう飛躍のなかを動いているという時間論にもとづいた表現なのかは、きわめてあいまいである。そういう確固とした時間論にもとづいて作られてはいないように見えるが、それがこの映画の核心ではないので、そういう「弱さ」はあまり気にならない。
◆しかし、最初の惹きつけ方にくらべて、見ているうちに失望してくるのは、この映画が前提としている「常識的」な道徳感である。人は、親を見習って育つ、「子供時代に「しあわせ」なら、「まともな」大人になれるだろう――といった観念がこの映画の基本にある。アル中の母親を持った娘は、15年後、母親と似たような女になるだろう。もし、それ以前に、母親が反省し、「まとも」な生活を送るならば、娘の人生も変わるだろう・・・・。たしかにそういう確率は高いかもしれない。しかし、誰でもが考えがちな(その実、かならずしもそうではない――むしろ、そう考えることによって、そういう不安をぬぐい去ろうとしているにすぎない)観念を映画がなぞっても、面白味はない。
(松竹試写室/松竹)
2006-03-08
●親密すぎるうちあけ話 (Confidences trop intimes/2004/Patrice Leconte)(パトリス・ルコント)

◆「常識的」には、精神科医の診療室と税理士のオフィスとをまちがえた女(サンドリーヌ・ボネール)と、その女性に惹かれ、まちがいを知りながら言わずに「精神科医」を演じ続ける男(ファブリス・ルキーニ)との「大人」のコメディといった風情。しかし、映るシーンは、最初から最後まで意味ありげ。それが「ふり」(プリテンション)ではないところがルコント。だから、深読みすれば、いくらでも意味を付加できる。
◆最初、歩いている女の足が映るが、それが何を意味するかは、あなたの映画的記憶次第だ。足から入る映画というのがあり、話は飛ぶが、日本の国策映画『非常時日本』にもよく歩いている足のシーンが出てきた。歩いている足は、「常識的」には、アンナを演じるサンドリーヌ・ボネールの足のはずだが、そうでなくてもいい。さしあたり「常識的」に見ておくと、アンナは、パリの街を歩いてとあるビルのなかに入る。このビルの6階にあるモニエという精神科医の診察室を夕方の6時に訪ねるアポイントメントをしている。(「6階」の「6時」というのも暗示的だ)。
◆同じデザインのドアーが並ぶ廊下で、部屋がわからなくなった彼女は、とあるドア(管理人?)をたたき(開いていたか?)、「ドクター・モニエ」の部屋番号を訊く。アンナは、教えられた通りにそのドアをノックするのだが、それを教えた初老の女が、ずっと意味ありげに彼女のことを見ている態度がわたしにはやけに気になった。その女性の姿は、アンナが部屋のことを尋ねる以前から画面に映っている。彼女は、テレビで古い映画かテレビドラマを見ているのだが、そのなかで、女が夫(?)に、自分は彼よりも「ジョゼフ神父」により正直な告白をするとかいうようなことを言っている。アンナが、税理士のウィリアムのドアを叩いたのは、その初老の女がそう教えたからであり、彼女がそうするのをずっと見ているわけだから、その女がわざと間違った部屋を教えたという推定もできる。そういう風に見て行くと、この映画は、「常識的」な見方から大いにはずれてくる。つまり、この映画は、ある種の「陰謀理論」で見ることもできるのである。
◆「常識的」には、ウィリアムの部屋には、フロイト派のセラピストが使うのに似たソファがあり、テーブルには、「(精神)分析」と読める「Analyse」という文字が見える雑誌が置いてある。本当は、「Analyse Finacielle」なのだが、「Finacielle」の部分に何かがのっていて、アンナには「Analyse」の部分しか見えない。しかし、このシーンは、アンナの目にそう映ったかのように見せておいて、観客を「常識的」な線に導くためのものであるかもしれない。「常識的」には、ウィリアムは、彼女が部屋を間違えたのを知りながら、精神科医のふりをしているように進むが、実は、そのことをアンナ自身が知っていてウィリアムと「芝居」を楽しんだのかもしれない。管理人(?)の女が、彼女の姿をじっと見ていたのも、彼女が教えたのとは違う部屋のドアをノックしたので、不可解な目で見ていたのかもしれない。
◆ウィリアムのオフィスは、アパルトマンの一室で、奥には秘書の部屋と居間や台所がある。それは、親から引き継いだアパルトマンで、彼はそこで育ち、父親の死後、仕事を引き継いだらしい。仕事が終わっても、孤独にレコードを聴いたりするくらい。おもちゃのコレクションもある。窓から向いのホテルのなかが見え、男女が愛しあっているのが見える。秘書をしているマダム・ミュロンは、父親の彼女だったらしい。エレーヌ・シュルジェールが演じる60過ぎの女性からは、そんな雰囲気が伝わってこないでもない。
◆アンナは、夫マルク(ジルベール・メルキ)とうまくいっていないで悩み、精神科医を訪ねたという設定。その夫がウィリアムとの関係を嫉妬し、彼のまえに現われるが、このくだり、必ずしも「現実」と受け取らなくてもいい。同じ階に診療室を持つドクター・モニエ(ミッシェル・デュショソーワ)とウィリアムが昼食をするシーンで、アンナの言説の虚実が話題になる。このあたりを発展させて、ウィルアムは、実は、ドクター・モニエの患者で、すべてが彼の「妄想」だという解釈も不可能ではない。
◆最後は、パリから、太陽がいっぱいの南仏にアンナが移住し、もともとやっていたバレーを子供たちに教えているという風にとれる展開をする。ウィリアムから電話が入る。彼女を探してパリから彼も移住することにしたのだ。すでにオフィースを借り、荷物も届いている。このあたりも、「常識的」なストーリを単純になぞることもできるが、時間を逆転してみることも可能だし、また、「パリ」か「南仏」かのどちらかを空想の括弧のなかに入れて、すべてを再構成することもできる。その意味で、この映画は、何を書いても「ネタばれ」にはならない。
(スペースFS汐留試写室/ワイズポリシー)
2006-03-07
●戦場のアリア (Joyeux Noël/2005/Christian Carion)(クリチャン・カリオン)

◆第一次世界大戦のとき、フランス北部のデルソーにフランスとイギリスの連合軍とドイツ軍がたがいに塹壕を作って戦っていた。なにせ、この時代は、空爆もあるが、勝敗を決するのは敵と味方が激突する地上戦だ。中世とあまり変わりがない。第二次世界大戦の方が死者の数は多いが、対決して一方は必ず死ななければならないという恐怖の度合いはこちらの方が高い。映画は、その最前線でクリスマス・イヴに起こった実話をもとにしたいる。ドイツ軍の塹壕に多数のクリスマスツリーが送られ、それを兵士が塹壕の外に飾ったのをきっかけに、スコットランドの兵士がバグ・パイプを吹き、そして、フランス兵が歌い、やがて、ドイツ軍のなかにいたテノール歌手のニコラウス(ベン・フュルマン)と、特例を使って夫に会いに来た彼の妻で著名なソプラノ歌手アナ(ダイアン・クルーガー)が歌いはじめる。そして、敵と味方の対立をこえた「クリスマス休戦」が実現する。
◆こういう話は、うそでも解放感があるが、わたしは、若干違和感を持った。すんなりと解放感が胸を突き抜けず、ときおり不快感がこみあげてきた。それは、キリスト教の問題と関係がある。クリスマスだから当然なのかもしれないが、歌われる歌がすべて「聖歌」なのだ。これは、異教徒にとっては気になる。なるほど、戦争をやめることは、なにはともあれ、すばらしい。兵士たちが、戦争のばかばかしさ(それは誰でも知っているが、それを否定することができない条件のなかにいる)に対していっときでも行動を起こしたのはすばらしい。しかし、それらは、キリスト教の「連帯」にすぎないような気たした。
◆しかし、その「連帯」は、イギリス軍でもフランス軍でも、またドイツ軍でも問題になり、イギリス軍に召集されたパーマー司祭(ゲイリー・ルイス)は、司教から司祭の職を解かれる。ドイツ軍のホルストマイヤー中尉(ダニエル・ブリュール)は、粗末な貨車で別の戦地に配置転換となる。その貨車の横腹には「タンネンベルク」の文字が見える。タンネンベルクは、ヒンデンブルクがロシアを「殲滅」した地ではあるが、熾烈な戦いが行なわれ、「大勝」とはいえ、ドイツ軍に1万5千人以上の死者が出ている。
◆夢の「クリスマス休戦」という事態に慌てた司教は、その主要な当事者であったパーマー司祭を解任し、若い兵士のまえで、戦地で死ぬことが神の意思であるかのように「聖戦」を説く。パーマー司祭は、自分にとっては、戦場で祈ることこそがつとめであるとし、司教に反発し、十字架を捨てる。このあたりは、(最近は相当トーンダウンしているが)アメリカのブッシュが事実上の「聖戦」を遂行していることと考えあわせると、面白い。いつの時代も、宗教は国家と結びついて殺人(「敵」の抹殺)や戦死を正当化してきた。
◆だから、うしろからこの映画を見ると、キリスト教にも二つの流れがあることがわかるのだが、わたしに言わせれば、宗教が国家と一体になったときだけがまずいのではなくて、そもそも宗教にはいずれも「殉死」の思想が潜在し、死ぬことを美化し、聖化する機能がある。この映画の「クリスマス休戦」の出来事は、「事実にもとづいている」とうたってあるように、実際にそうだったのだろう。が、このとき、もし、キリスト教徒とイスラム教徒とがいっしょだったら、こういうことが起きただろうか?
◆ところで、この映画のなかで、 ダニエル・ブリュールが演じるホルストマイヤー中尉は、ユダヤ人で、自分にはクリスマスは関係ないと言うシーンがある。が、ユダヤ教はキリスト教の「親宗教」であって、キリスト教とイスラム教との関係とは比較にならない。
◆宗教のあるかぎり戦争はあり、命令する者と従属する者との階級差があるかぎり、戦争はつづく。
◆ダイアン・クルーガーのソプラノとベンノ・フュルマンのテナーは、いずれも本人自身が歌っているのではなく、ナタリー・デッセーとロランド・ブラゾンが代唱している。寒い戦場で歌ったのだから、少しぐらい音程が狂っても、俳優が歌うべきだったろう。見ていると、口が合っていない。その意味では、ポップスではあるが、『ビヨンドtheシー ~夢みるように歌えば』のケヴィン・スペイシーも、『ウォーク・ザ・ライン』のホアン・フェンイクスはとりわけ、アメイジングである。
(角川ヘラルド試写室/角川ヘラルド・ピクチャーズ)
2006-03-07
●間宮兄弟 (Mamiya-kyodai/2006/Morita Yoshimitsu)(森田芳光)

◆森田芳光の作品は、けっこう見ているが、近年は、『模倣犯』でも『阿修羅のごとく』でも『海猫』でも裏切られたので、躊躇しているうちに「追加試写」の時期になってしまった。大学の春の企画の相談にのってくれている植草信和さんと会うことになり、氏がこの作品を見る予定だというので、いっしょに見ることにした。
◆森田芳光は、プレスのなかで、「僕は一人っ子なので、子供の頃友達が自分の家に遊びに来てもいずれは帰ってしまうことに寂しさを感じていました。『兄弟っていいな、ずっと一緒に遊べるし、話が出来るな』と単純に思っていました。年を重ねて行くうちに、兄弟はそんな甘いモノじゃないことを知りました」と書いている。実はわたしも一人っ子として育ったのだが、わたしは、森田とは反対にそういう「寂しさ」を感じたことがない。だから、映画が始まるまえにプレスでこのことを知ってしまったので、この映画にたいして、森田とは全然ちがった印象を持つのではないかと思った。見終わって、その通りだったのだが、逆に、性格がまったく異なるために、全然異なる見方ができるような気もした。たとえば、映画に出てくるのは「兄弟」だが、これを同性愛のカップルの物語に「翻訳」したら、面白い側面が見えるのではないか等々。
◆ただ、森田が一人っ子だったということを知ってしまったせいか、この映画は、「一人っ子」が無理をして「二人っ子」を理解して作ったような印象をあたえる。これは、若者の表現もそうで、俳優たちは、彼や彼女自身が感じている感覚と少しズレた感覚表現を演技のなかで強制されているような気がするのだ。それは、とりわけ、北川景子やその姉役の沢尻エリカがそうであり、また、もう少し上の年令の学校教師を演じる常磐貴子の場合も、彼女の持ち味を殺した形でおどけたしぐさや三枚目を演じさせられているように見えた。その点で、終始楽しげに役を演じてしまったのは、間宮兄弟の母を演じる中島みゆきである。状況に動じないというのか、これが地だったのか、この映画のなかで一番リアリティがある。
◆映画にせよ小説(この映画は、江國香織の原作にもとづいている)にせよ、新たに創造すればいいのであって、現実に存在する既存のモデルをなぞる必要はない。観客は、既存のモデルを参照してリアリティを判定するわけではない。この兄弟にリアリティがないのは、映画のなかのキャラクターとして破綻しているからだ。
◆見ながらふと思ったのは、この映画は、兄弟を同性愛者として描いた方が面白かったのではないかということだった。兄が弟に「塩むすび」を作ってやるシーンは、兄=母親として描かれているが、非常に同性愛的な感じだ。それは、兄を演じる佐々木蔵之介と弟を演じる塚地武雄とのあいだでスパークした情感かもしれないが、このへんを思いきりブーストした方がよかったのではないか? 兄弟は、ガールフレンドを得るためであるかのように、カレー・パーティとか浴衣パーティとか、パーティを仕掛けて、北川、沢尻、常盤を自宅に招く。2人の男と3人に女がからんで、そのなかからカップルが生まれそうになるが、結局はうまくいかない。そこで笑わせるということなのかもしれないが、わたしには全然笑えなかった。わたしには、兄弟に「ホモイロティック」(準同性愛的傾向)があり、異性愛の女性たちとは基本的に合わないのだ。
◆【追記/2006-12-22】旧稿で「夕美」と「直美」をとりちがえるような書き方をしていて、読者のかたから再三厳しい指摘を受けた。言いたいことはストーリではなく、役者と登場人物とのあいだの齟齬についてだったので、細かい部分は削除した。役者名で書けばよいものを、頭のなかで登場人物名に「翻訳」したとき、混乱を起こした。原作の愛読者、映画のファンには多謝。まあ、一言で言えばバカみたいな誤りだ。この時期、速書きに生きがいをおぼえていたが、あまり意味ないと最近は思っている。また、あまりノレない作品については書かないほうがいいとも思っている。誤記も含めて「ノート」だとも思うが、検索すれば出てくるので、データベースとして使われることもあり、社会的な迷惑をかけかねない。
◆この映画で、一番ノリノリだったのは、兄弟の母親役の中島みゆきだった。距離を置きながら、根は暗くても、いや、根が暗いので、「明るく」ふるまわざるをえない日本の人間関係をこの人は実に巧みに演じていた。そういえば、この映画のなかで間宮兄弟は、パーティで必ずゲームをやるが、これは、日本で「現実」によく見る光景だ。わたしは、いまほど「パーティ」がはやっていないころ、大学のゼミで毎週誰かがホストとなってさまざまな形式のパーティを仕掛ける実験をやっていた。3年まえぐらいにそれをやめてしまったのは、気づくと、毎回必ずゲームをおりこむスタイルのパーティが増えてきたからだった。そういう方式だと、その最中はいっとき盛り上がるが、それによって何かが生まれるとか、尾を引くということがなく、party のparticipation(介入)的要素が骨抜きにされてしまうのだ。そのとき思ったが、日本でパーティをやると、会話や議論では長い時間もたない(あるいは会話や議論が怖い)ので、そういう空白が生まれるのを恐れて、ゲームを入れるらしいということだった。participationである以上、相手によってこちらが変わることは当然だが、それを避ける方法がゲームの採用なのだ。変わりたくない日本。
(アスミック・エース試写室試写室)
2006-03-02_2
●ナイロビの蜂 (The Constant Gardener/2005/Fernando Meirelles)(フェルナンド・メイレレス)

◆開場の6時半の15分ぐらいまえに行ったら、階段の3階下まで列が出来ていたが、比較的好きな席に座れた。周囲で弁当を食べている女性が多い。明らかに、「ラブストーリー」として売り込もうというねらいで、女性の観客を集めた感じ。しかし、この映画はまずもって政治映画であり、政治に関心がなければ、二人の「ラブ」の屈折もわからない。イギリス映画だが、監督は『シティ・オブ・ゴッド』のフェルナンド・メイレレスだから、切れ味がちがう。
◆アフリカと思える空港でレイチェル・ワイズが黒人の男(ユベール・クンデ)といっしょに旅立とうしている。見送るレイフ・ファインズは、明らかに恋人か夫。ワイズが持っていたバッグを、男が「持とうか?」と言って、手にする。2人の関係は? ファインズの表情にちょっと疑惑の色が浮かんだかなと思わせながら、ワイズとファイズの姿がシルエットになる。これは、2人がこのあと二度と会う機会はないのではないかということを予測させる。ここから映画の時間がバックする。
◆イギリスの外務省の一等書記官ジャスティン(レイフ・ファインズ)がスピーチをしたあと、聴衆のなかから、テッサ(レイチェル・ワイズ)が質問をする。「英国はどうして国連を無視してイラクへ軍隊を派遣したのか・・・」。ジャスティンはやや当惑しながらもていねいに答えようとするが、彼女は激昂し、激しい口調でイギリス政府の批判をし、まわりの聴衆はあきれ、軽蔑した顔で席を立ち、最後には部屋にいるのは、ジャスティンと彼女だけになる。活動家の女性の一つのパターンだが、ジャスティンは、「傾聴型」の人物、あるいは(「サド」か「マゾ」かといえば)「マゾ」っ気のあるタイプのようで、そういう男とテッサのような攻撃型の女とが出会うと、その先は予想がつく。
◆ジャスティンは、テッサを外に連れ出し、コーヒーに誘う。そのときの台詞が、「Can I buy your coffee?」。これは、「コーヒーをおごらせてくれる?」だが、その昔、わたしは、初めて会った女性に「Can I buy your dinner?」と言われて、鼻白んだことがある。むろん、わたしの不明を恥じなければならないのだが、わたしは、英語の「buy」が「おごる」という意味だとは知りながら、「買う」という響きが不快だったのだ。日本の古い(?)習慣に染まっていたわたしは、「買う」か「買わない」かが問題じゃあねぇだろうと思ったのである。しかし、コーヒーにしろディナーにしろ、金を払わなければ手に入らないのだから、buyでいいわけだし、それが「普通」の英語表現なのだ。
◆コーヒーを飲んだあと、ジャスティンは、テッサを家に連れて行き、そのままベットイン。みんな手が早いんだねぇ。事が済んだあと、彼は、「ワンダフルなギフトをありがとう」と言い、テッサは、(そんな言い方だと)「わたしが慈善家みたいじゃない」と言って笑う。セックスをしたあと、「ワンダフルなギフトをありがとう」と言うのは、ジャスティンの性格をよくあらわしていて面白い。ジャスティンは、やがてケニヤの英国大使館の一等書記官になり、離れ離れになりたくない二人は結婚する。テッサは、ケニアでますますアクチュアルになり、冒頭に出てきた黒人は、医師のアーノルド(ユベール・クンデ)で、彼女は、彼といっしょに、貧しい人々や病人やHIV患者の救済活動に挺身する。
◆原題のThe Constant Gardenerは、ジャスティンを指すのか、それともテッサを指すのかは、この映画を見る観客しだいである。constantには、「不変の」、「変わらぬ」、「誠実な」、「不屈の」といった意味があるが、映画のなかで庭いじりをしているのはジャスティンの方だとしても、テッサが「不屈」に貧しい人々を助けるボランティア活動をやっていることを考えると、「不屈の庭師」=テッサだと解釈することもできる。
◆原作はジョン・ル・カレの小説だが、ル・カレは、いつも、エンタテインメントとアクティヴィズムとのあいだで創作活動をしている。そのため、読む方も、一つの世界を追体験させられる面白さと同時に、能動的な発見と何らかのコミットメントをうながされる。監督のフェルナンド・メイレレスは、ル・カレのそうしたハイブリッド性をばっちりと映像化している。
◆80年代にヨーロッパで製薬会社が有志に金を払って(危険なこともありえる)新薬のテストをしているという話を聞いたことがあるが、この映画では、DYPRAXAという製薬会社が、英独、ケニャ政府内の閣僚等とつるんでアフリカで新薬の人体実験をしている。これに気づき、摘発の活動に深入りしていくテッサと、立場上、苦しくなるジャスティン。もしあなたが男で、妻がラディカルな活動家で、こういう立場に立たされたらどうしますか?
2006-03-02_1
●僕の大事なコレクション (Everything Is Illuminated/2005/Liev Schreiber)(リーヴ・シュレイバー)

◆2日続けてワーナーの試写室に来てしまったが、今年はワーナーの配給作品でいいものが多い。なぜか、少しまえから、例の「映画が盗まれている・・・」のスポットを最初に流さなくなった。今日はセキュリティ・ウーマンもいなかった。
◆最近見た映画では、ベストに入る作品。アメリカ映画にして、アメリカ映画らしくない。監督は、『クライシス・オブ・アメリカ』でWASP(白人でアングロサクソンでプロテスタント)っぽいWASPを演じたリーヴ・シュレイバー(プレスでは「リーブ・シュライバー」と表記)。え~、彼にこんな才能があったの? と意外だったが、脚本と監督を今回初めて担当し、このすごい作品を作りあげた。
◆この映画のユニークさと面白さは、その文化的な複合性だ。ジョナサン・サフラン・フォアの小説にもとづいているが、リーヴのバックグラウンドも深く影を落としている。リーヴの本名は、「アイザック・リーヴ・シュレイバー」であり、ユダヤ系である。彼は、両親が離婚し、70年代の初めに母親とカナダからニューヨークに移り住んだ。10代を70年代後半のニューヨークで過ごしたわけだが、タクシードライバーをしながら彼を育てた母親は、カラー映画(モノクロはOKだったらしい)を見ることを禁じ、本を読むことを教えたという。だから、彼は、大学生のときは、作家志望だった。俳優になったのは、大学の教師に強く勧められたからだという。ちなみに父親は、俳優だった。
◆ユダヤ性というのは、通常、ヘブライ語やユダヤ教との関連で考えられることが多いが、ユダヤ性のもっともダイナミックな側面は、そのハイブリッドな要素だろう。つまり、さまざまなものが流れ込んでいる混成文化としてのユダヤ性である。それは、ヘブライ語よりもイーディッシュ語のなかに残っているが、そこでは、アラブ的なもの、ゲルマン的、ロシア的、スラブ的等々の要素がからみあい、混在する。
◆この映画は、アメリカのユダヤ人青年ジョナサン(イライジャ・ウッド)が、ウクライナ出身の祖父の過去を探す物語である。そのプロセスと出会いがファニーで面白く、味わいがあるが、さらに、そこから、一人の祖父の過去だけではなくて、ウクライナの屈折した反ユダヤ主義の歴史があらわになってくる。パーソナルで、ファニーでイデオシンクラティックなことを描きながら、歴史をあらわにする手並みは見事だ。
◆ウクライナは、ロシア革命後ソ連に統合されるが、その歴史はすんなりしたものではない。だから、ソ連の崩壊後は、ロシアとは一線を画した。ソ連の時代でも、ロシア人はウクライナ人を差別していた。そのために、チェルノブイリの原発もウクライナに建設されたのだという説もある。映画のなかで、ジョナサンが、ウクライナに入ると、沿道に放射能の危険を指示する標識が立っている。旧ソ連時代の官庁のビルらしきものが廃墟になっているのも見える。
◆ウクライナの歴史は屈折していた。ソ連との関係のほかに、ロシア革命以前からウクライナには多数のユダヤ人が住んでいた。そのなかでユダヤ人は、ロシア人だけでなく、ウクライナ人から差別も受け、多くのユダヤ人がアメリカなどに移住した。わたしがイーディシュ演劇の教えを受けるためにニューヨークに行ったとき、わたしにニューヨークという街の面白さを教えてくれたデイヴィッド・S・リフサン(彼を追悼した文章[英文]と映像[RealMedia]参照)の父も、20世紀の初頭にウクライナから移住したユダヤ人だった。
◆ウクライナのユダヤ人は、ウクライナ人から差別を受け、さらに、1941年、ナチス・ドイツがソ連に侵攻し、ウクライナを占領したとき、文字通り虐殺された。この映画でもその歴史的事実が描かれる。ウクライナで「ウクライナ独立」を推進しようとする反ロシアの独立派は、ナチス・ドイツを歓迎し、一時期、ウクライナの独立派とナチとのあいだに「連帯」が成立した。ナチスは、結局、ウクライナ人も弾圧するようになるのだが、ナチに協力して「ホロコースト」を手伝ったウクライナ人がいたわけである。だから、ウクライナ出身のユダヤ人は、ウクライナに対しては極めて深い疑いの目を向ける。このへんの屈折が、この映画の背景にはある。
◆ジョナサンは、ファミリーの歴史に興味があり、ファミリーに関係のあるものをビニール袋に収納して壁にとめつけ(→
 )、それらが一大コレクションをなしている。彼は、すでに亡くなっている祖父に関心をもち、高齢の祖母を訪ねて話を訊こうとする。祖母は、祖父が田園で祖母とは違う女性といっしょに映っている写真(→
)、それらが一大コレクションをなしている。彼は、すでに亡くなっている祖父に関心をもち、高齢の祖母を訪ねて話を訊こうとする。祖母は、祖父が田園で祖母とは違う女性といっしょに映っている写真(→ )をくれるが、写真の裏に名が書いてある「アウグスティーネ」という女性が誰であるかは語らない。家に帰ったジョナサンは、その写真を見ているうちに、アウグスティーネが胸につけているペンダントに見覚えがあることに気づく。それは、祖父からもらったもので、樹脂のなかにイナゴが埋め込まれていた。やがて彼は、祖父が「その女性のおかげでアメリカに来れた」ことの謎を解くためにウクライナのオデッサへ旅立つ。祖父が住んでいた「シュテットル」(ユダヤ人居住地)の「トラヒムブロート」(Trachimbrod)を探すために。
)をくれるが、写真の裏に名が書いてある「アウグスティーネ」という女性が誰であるかは語らない。家に帰ったジョナサンは、その写真を見ているうちに、アウグスティーネが胸につけているペンダントに見覚えがあることに気づく。それは、祖父からもらったもので、樹脂のなかにイナゴが埋め込まれていた。やがて彼は、祖父が「その女性のおかげでアメリカに来れた」ことの謎を解くためにウクライナのオデッサへ旅立つ。祖父が住んでいた「シュテットル」(ユダヤ人居住地)の「トラヒムブロート」(Trachimbrod)を探すために。◆祖母のベットのサイドテーブルには、「XANAX」という文字の見える薬のケースがあるが、これは、精神安定剤。そのそばにコップの水につけた入れ歯がある。その入れ歯も、ジョナサンの壁のコレクションになるシーンがすぐ続くから、この老婆は、その後すぐに亡くなったことを示唆する。
◆どのようなコネクションかわからないが、ジョナサンは、オデッサでガイドを見つけ、屋根の看板に英語で「Jewish Heritsage」とダビデの星のマーク(→
 )とロシア文字で「オデッサ」という文字が見える(ここで、わたしは、この車の持主が当然ユダヤ人だろうと思ったが、ストーリーは、当面、そうでない路線で進む)トラバント(「共産圏」で普及していた大衆車――ゴダールの『新ドイツ零年』や『ゴー・トラビ・ゴー』ではこの車が象徴的に使われている)で「トラヒムブロート」を探すことになる。案内するのは、オデッサに住む、盲目になったと信じ込んでいるのか、そうふるまっているのか不明の老変人(ボリス・レスキン)と、その孫で、山本太郎にどこか雰囲気の似ている、HipHop狂のアレックス(ユージン・ハッツ)である。ちなみに、この映画は、冒頭から、このアレックスのナレーションで進行する。
)とロシア文字で「オデッサ」という文字が見える(ここで、わたしは、この車の持主が当然ユダヤ人だろうと思ったが、ストーリーは、当面、そうでない路線で進む)トラバント(「共産圏」で普及していた大衆車――ゴダールの『新ドイツ零年』や『ゴー・トラビ・ゴー』ではこの車が象徴的に使われている)で「トラヒムブロート」を探すことになる。案内するのは、オデッサに住む、盲目になったと信じ込んでいるのか、そうふるまっているのか不明の老変人(ボリス・レスキン)と、その孫で、山本太郎にどこか雰囲気の似ている、HipHop狂のアレックス(ユージン・ハッツ)である。ちなみに、この映画は、冒頭から、このアレックスのナレーションで進行する。◆ユージン・ハッツは、ロマ・クレズマ・パンク・バンド Gogol Bordell で有名なミュージシャンらしい。ウクライナの首都キエフの出身で、1972年にアメリカに移住した。映画のなかで見せるブレイク・ダンス(【追記/2006-03-27】よく見ると、踊っているあいだユージン・ハッツの顔が見えないように撮られており、ラースト・クレジットには別の名が出ていた)とロシアなまりの英語に説得力がある。アメリカにあこがれているが、実際のアメリカを知らないアレックスは、「ニグロ」が差別語であることも、「ヴェジタリアン」という言葉の意味も知らない。そのズレが笑わせる。
◆ジョナサンとアレックスとその祖父との3人が、オデッサから「トラヒムブロート」へ旅するなかで、変わるのは、ジョナサンよりも、アレックスとその祖父である。その変化と祖父の隠された事実が胸を打つ。演じるボリス・レスキンは、『コードネームはファルコン』や『メン・イン・ブラック』などに出ているらしいが、この映画での演技は特筆すべきだ。(【追記/2006-03-27】なお、最初、ジョナサンに、「メス犬とユダヤ人は後ろの席に乗れ」などと言っていたこの老人が、「トラヒムブロート」という「シュテットル」を探すのだと言うと、アレックスは、「シュテットルって何?」と言うのに対して、すぐに「ユダヤ人居住区をあらわすイーディッシュ語」であることを理解するシーンと、それ以後の急速な態度の変化は重要だ。自分がユダヤ人であることを隠している屈折と鬱積を無言で表現するボリス・レスキンの演技は見事)。
◆【追記/2006-04-4】劇場パンフレットをわたしに書かせた千葉玲子さんによると、原作では、「ジョナサンと落ち合う場所は、ポーランド国境近くのリヴォフになっています。ジョナサンはプラハからの列車でここに着き、そこからトラキムブロド探しに出発します。トラキムブロドはリヴォフから比較的近いところで、ポーランドとの国境あたり、という設定でした」とのことで、わたしは、うかつにも、ジョナサンが到着する駅を「オデッサ」だと思っていた。いいかげんだ。考えてみれば、オデッサ駅にしてはひと気が少ない。そういえば、Trailerにロシア文字の駅名で出ているシーン(→
 )があったことを思い出し、調べてみると、「
)があったことを思い出し、調べてみると、「 」の文字が見えた。これは、アルファベットでは「LVOV」ないしは、「L'VOV」のこと。
◆ジョナサンたちが訪ねるウクライナの「トロヒムブロート」(Trochimbrod/Trachimbrod)は、実在の場所で、もともとここにはユダヤ人が住んでいたが、ナチは占領後近隣に住むユダヤ人をこの地に集め、「ゲットー」をつくった。そして1942年8月、その数千人のユダヤ人を虐殺したという。ところで、ジョナサン・サフラン・ショアの原作小説 (Evderyone is Illminated/2002) とこの映画には、多くの批判が起きたが、その批判は、こうしたユダヤ人虐殺の事実は認めながらも、この小説と映画のなかでウクライナ人がユダヤ人に冷淡であったように描かれているというものであった。いくつかの指摘によると、ウクライナ人のあいだにもパルチザン活動があり、ゲットーのユダヤ人レジスタンス・グループと連帯し、ナチと闘ったという。しかし、この映画は、トロヒムブロートのユダヤ人が抑圧されてひどいなぁという、お涙頂戴の話ではなくて、多くの人が知らなかった歴史を描き、そのなかで生まれる邂逅や友情を描いているところに意味がある。
」の文字が見えた。これは、アルファベットでは「LVOV」ないしは、「L'VOV」のこと。
◆ジョナサンたちが訪ねるウクライナの「トロヒムブロート」(Trochimbrod/Trachimbrod)は、実在の場所で、もともとここにはユダヤ人が住んでいたが、ナチは占領後近隣に住むユダヤ人をこの地に集め、「ゲットー」をつくった。そして1942年8月、その数千人のユダヤ人を虐殺したという。ところで、ジョナサン・サフラン・ショアの原作小説 (Evderyone is Illminated/2002) とこの映画には、多くの批判が起きたが、その批判は、こうしたユダヤ人虐殺の事実は認めながらも、この小説と映画のなかでウクライナ人がユダヤ人に冷淡であったように描かれているというものであった。いくつかの指摘によると、ウクライナ人のあいだにもパルチザン活動があり、ゲットーのユダヤ人レジスタンス・グループと連帯し、ナチと闘ったという。しかし、この映画は、トロヒムブロートのユダヤ人が抑圧されてひどいなぁという、お涙頂戴の話ではなくて、多くの人が知らなかった歴史を描き、そのなかで生まれる邂逅や友情を描いているところに意味がある。◆アメリカでは、この映画に対してアメリカ系ウクライナ人から批判が起こった。たしかに、映画のなかでは、はっきりと、「ウクライナでナチ以前に反ユダヤ主義があった」という台詞が出てくる。3人が泊まるホテルの大柄の女主人(?)とか、道すがら彼らがトロヒムブロートの所在を尋ねる労働者たち――すべて「ウクライナ人」――の彼らに対する対応は、よくは描かれていない。ウクライナ人の描き片が好意的でないという批判はこういうところにもあるのだろう。しかし、わたし自身の経験でも、たとえば、ニューヨークのセカンド・アヴェニューのウクライナ人コミュニティのレストランは、他のエスニックレストランにくらべて「人種差別的」な印象をあたえた。70年代の話である。その分、内輪の結束は固く、チェルノブイリの事故のニュースが流れると、何週間にもわたった祈りの集まりが続いた。
◆トロヒムブロートに到着すると、一面ひまわりの畑(→
 )が広がるシーンが美しい。そのなかに一軒の家があり、そこに一人の老女が住んでいる。「あなたたちの来るのをずっと待っていました」という彼女の一言が非常に重く、また感動的だ。が、彼女は誰か? あのアウグスティーネか? これは、映画を見てのお楽しみ。この老女を演じるのは、西側の映画ではほとんど未知のラリッサ・ローレット。すごい俳優である。
)が広がるシーンが美しい。そのなかに一軒の家があり、そこに一人の老女が住んでいる。「あなたたちの来るのをずっと待っていました」という彼女の一言が非常に重く、また感動的だ。が、彼女は誰か? あのアウグスティーネか? これは、映画を見てのお楽しみ。この老女を演じるのは、西側の映画ではほとんど未知のラリッサ・ローレット。すごい俳優である。◆【追記/2006-04-04】この女性の言葉は、彼女のコレクションの意味と対応している。彼女は、ナチに殺されたユダヤ人の遺品を集めては箱に入れ、自宅に収集してきたのだったが、それは、遺族がいつの日かその死者に会いたいと思ったときのためにそうしているのだという。彼女が、そういう主旨をとうとうと語るわけではないが、妹アウグスティーネが姉に預けた遺品に、「万が一のために」というメモがついていたことを説明しながら彼女が言う言葉から、そういう意味が読み取れる。このシーンは、記憶への執着というユダヤ的「伝統」を思い起こさせると同時に、人を想う、人を愛するということは、その記憶を保持し、継承することなのだということを暗黙に言っている。
◆月にこだわったシーンがいくつかある。これは、原題「Everything Is Illuminated」(すべてが照らされる=すべてが明らかになる)を考えれば納得がいく。
(ワーナー試写室/ワーナー・ブラザース映画)
2006-03-01_2
●君とボクの虹色の世界 (Me and You and Everyone We Know/2005/Miranda July)(ミランダ・ジュライ)

◆パフォーマンス・アーティストのミランダ・ジュライの初めての長編映画だというが、主演もしている彼女の風貌がこの映画の弱点を大いにカバーしている。彼女のノホホンとした風貌のおかげで、いくつものパフォーマンス・アートをつなげたようなこの映画の「ルース」な感じが退屈でダラけたものに感じられない。とくな人だ。というよりも、彼女のイデオシンクラシーが、映像と一体化することによって、この映画のユニークサが生まれた。
◆構成は、モジュール状になっている。一つのモジュールは、クリスティーン(ミランダ・ジュライ)。彼女は、ビデオとサウンドのパフォーマンスのようなことをやる一方、高齢者のためのタクシー運転手をしていて、その常連の客にマイケル(ヘクター・エリアス)がおり、彼が老人ホームで知り会ったエレンは病気で死にかけている。もう一つのモジュールは、リチャード(ジョン・ホークス)。彼は、黒人の妻パム(ジョネル・ケネディ)とのあいだに6歳のロビーと14歳のピーターという2人の子供がいる。家庭内離婚をしており、子供たちはネットのチャットにはまっている。これらに、隣人がからむいくつかのモジュールがある。
◆これらのモジュールは、映画のなかでたがいに組み合わさり、それぞれのドラマ(といってもハリウッド的なドラマではなく、非常に日常的でミクロな繊細さにあふれた出来事)を生み出す。マイケルは、なぜ妻と別れたのかはわからない。彼が、庭で手にアルコールをかけて、ライターで点火するのも、パフォーマンスを見る感覚ではごく「自然」に見える。彼は、普通の「夫」や「父親」にはなれないらしい。そのくせ、ちゃんと、靴屋で店員をしている。この映画は、キャラクターを「ドラマティック」に型取らないところがいい。それっぽいキャラクターは一人もいない。といって、それは、「特異」な印象をあたえるわけではない。ごく「自然」に「変なこと」をしているのを見ているような感じだ。そして、その「変なこと」は、パフォーマンス・アートに慣れている人には、ごく「自然」なことなのである。
◆この映画は、パフォーマンス・アートを見慣れている人には、ごく「自然」に入ってくるだろう。パフォーマンス・アートといっても、銃で自分の手を撃つようなものもあったが、そういうのではなく、ミニマリズム系というか、興味のない人には「退屈」としか見えないタイプのパフォーマンスだ。しかし、たとえば、男がバス停の金属のポールをコインで叩いていて、それを子供(ロビー)が見ていて、「何をしているの?」と訊くと、「バスを待っているんだよ」と答え、そのコインをロビーに渡してバスに乗っていくという最後の方のシーンにしても、それが、絵的にも、サウンド的にも一つの「作品」になっており、見る人次第でこの映画は、さまざまな輝きを見せる。
◆壁に張った写真を見ながらクリスティーンがマイクにナレーションを吹き込んでいるシーンがある。それは、作品を作っているという設定のようだが、サウンドパフォーマンスのようでもある。そのとき、なぜか、古いテレビの前面のツマミに手をやり、あたかも音を調整しているようなしぐさをする。こういう作業の成果なのか、彼女は、「Center for Contemporary Art」という美術館にビデオテープを持っていく。エレベータのなかでキュレイター(トレイシー・ライト)に会ったので、それを見てくれと頼むと、その(若いころのスーザン・ソンタグに似た)女は、美術館の住所に送ってくれと言う。「だって、ここでしょう?」とクリスティーンが言っても、きいてくれない。このあたり、キュレイターという種族に対するミランダ・ジュライの印象が出ているようで面白い。
◆このナンシーというキュレイターは、この映画では、徹底的に嘲笑されている。黒ずくめの服も、この種の連中が好んで着る衣装である。彼女は、部外者に冷淡だが、自分がキュレイトしているアーティストには無批判で、彼が無造作に床に放置したただの紙コップを彼の「作品」だと思い、賞賛する。おつにすましているが、チャットにはまっていて、卑猥なチャットに目がない。その末に、公園でオフラインで会いましょうということになるが、そこにやってきた相手が驚き。が、このとき、彼女は何かを悟ったかのようにとてもいい表情をする。この瞬間、この映画は、単にこの人物を嘲笑しているのではないことがわかる。このへんの、しなやかさというか、俗なロジックにくみしないというか、そのへんが、この映画のいいところだ。
◆ピーターとロビーがチャットをやっているシーンも、ある種のネットパフォーマンスとしての面白さがある。コンピュータには、「コンピューター・リテラシー」が必要だなどとのたまう者は、このシーンを見て、よく考えた方がいい。コンピュータによる表現は、「リテラシー」とはちがうのだ。ちゃんと文章を書けない(打てない)としても、字面(じづら)を見て、コピー&ペーストをすることも可能なのがコンピュータである。このへんの洞察がなかなか鋭い。
(映画美学校第2試写室)
2006-03-01_1
●ファイヤーウォール (Firewall/2006/Richard Loncraine) (リチャード・ロンクレイン)

◆試写室のあるビルの1階ロビーにコーヒースタンドがある。エスプレッソを注文したら、「これは、量が少なくて、味が濃いものですが、よろしいですか?」と念を押された。エスプレッソなるものを知らないで注文して、品物が出てきてから、「こんな濃くっちゃ、飲めねぇじゃねえか!」と文句を言うお客がいるのだろうか? でも、この店のエスプレッソの量はひどかった。ダブルで頼んだにだが、スプーンに2杯ぐらいしかないのだった。これだと文句を言うお客もいるかもね。
◆先日の劇場試写を見送ったのは、IMDbに載っていたクソミソのレヴューのせいもあって、あわてて見る必要はないと思ったからだったが、インターネットと関係があるはずのタイトルがついているので、いずれ見るつもりだった。これまで、『ザ・インターネット』(The Internet/1995/Irwin Winkler)などと銘打っても、ネットは飾りで、最後はフロッピーの争奪戦になるといったパターンがあって、ネットの特性をばっちりおさえたハリウッド映画はほとんどなかった。ネットを可視的にするのはむずかしいので、仕方がないとしても、あいかわらずこの「伝統」は消えない。
◆銀行のセキュリティ部門の幹部という設定のジャック(ハリソン・フォード)が、家族を人質にとられて、脅される。彼のセキュリティ技術を使って銀行の金を所定の場所にトランスファーしろというのである。しかし、その技術的な方法は、映画ではかなめにはならず、冷酷なロジックで計画を進める犯人ビル(ポール・ベタニー)とのフィジカルな攻防が見せ場になっている。最初から、犯人が誰であるかを明示したのち、その執拗で冷徹な指令をどうはずしていくかを描くのだが、最後は、64歳のハリソン・フォードが殴りあったり、とっくみあったりして解決に導く。
◆家族を腕力で守る父親というパターンは、ハリウッド映画では重要かつ人気のパターンだが、この映画を見ると、なんかハリソン・フォードがかわいそうという感じがする。クリント・イーストウッドも、(彼の場合、守るのは必ずしも家族とはかぎらないが)そういう役柄をある年令まで続けたのち、ある時期から、あえて「老い」や体力の衰えをも隠さずに描くようになった。ハリソン・フォードの場合は、注文仕事のためか、あいかわらず昔の「タフ男」を演じ続けている。
◆IMdbでクソミソに言っている批評では、12、3歳の娘サラ(カーリー・シュレーダー)と小学生の息子アンディ(ジミー・ベネット)の父親としては歳をとりすぎているというのがいくつかあった。しかし、映画は何も「世間的標準」を描く必要はないのだから、言いがかりである。再婚したと考えればいいではないか。映画では、2人の子供が、同じ母親(バージニア・マドセン)の子供だとはどこでも示唆していない。むしろ、最初に方で、出かけるジャックに、息子の方が「パパ」と呼ぶのに対して、娘の方は、「バイ、ジャック」と(テレビゲームをやりながら)惰性的に言うのである。むろん、実の親子でも、親をファーストネームで呼びあうことはある。思春期のなまいきさがそういう呼び方をさせたのかもしれない。いずれにしても、この家族を単純に受け取る必要はないし、歳をとって「再婚」したと考えれば、それだけ、家族を自力で守らなければならないという意識が強まらざるを得ないというのが、アメリカでは受ける。
◆家族を守ることと、犯人との攻防ということにウエイトが置かれた結果、銀行の幹部の役で、ローバート・パトリック、ロバート・フォースター、アラン・アーキンといった芸達者をそろえながら、会社組織の内側と犯罪との関係は表面的にしか描かれない。主犯のビルに脅され、秘書(メアリー・リン・ライスカブ)を即刻クビにし、ただちに彼女は荷物をまとめてオフィースを出ていくといったシーンがあるが、これはあまりに非現実的である。基本的にこの映画は、サスペンスにしか面白さがない。妻も子供たちも、いっしょになって犯人を倒すわけではなく、夫・父だけが、ひたすら頑張る。だから、サスペンスといっても、もっと錯綜した組織観、家庭像、人間関係を軸にしている『24』にはとうてい及ばない。
◆銀行のサーバールームが映るが、そこにずらりと並んだブレード・サーバーは、DELL製だった。ジャックのテーブルの上のコンピュータもすべてDELLであった。したがって、ネットを操作する際のコンピュータ画面に映るOSは、Windowsであった。
◆ジャックに銀行のなかを案内させ、現金の束を見て、ビルが、「リアルマネーなんかいらない。本当の金庫はここだ」とサーバーを指し、おれの関心は「ヴァーチャル・マネー」だと言う。このタンカの切り方は、ベタニーのクールな演技とあいまって、なかなかいいのだが、だとしたら、そのヴァーチャル・マネーの盗み方も、ヴァーチャルにやらなくてはならない。だが、そういうレベルに映画の表現が追いつかないので、モニター画面からデータを写し取るといった原始的なやり方をして観客を納得させようとする。しかし、ジャックは、FAXをばらしてはずしたスキャナー素子とiPod(これをハードディスク代わりに使うのだという)を組み合わせた自作装置でそれをやるのだから、観客は納得できまい。そのとき、ノートパソコンも使うのだから、なら、(どうしても画面からスキャンしたいのなら)USBカメラでもよかったのだ。
(ワーナー試写室/ワーナー・ブラザース映画)